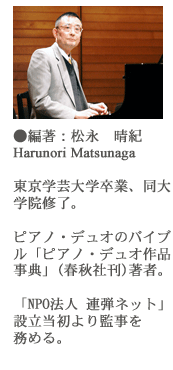はじめに
この事典は,春秋社刊「ピアノ・デュオ作品事典[増補改訂版]」の補遺にあたります。
「事典」執筆当時は入手困難であった多数の楽譜が,ここ数年の間に IMSLP などのサイトから容易に入手可能となりました。書物としての「事典」の大幅な増補改訂は容易ではありませんが, サイト上のコンテンツとしてデータを増やしていくことは比較的容易なので, こうしたかたちで補遺編の作製を意図しました。
したがって,この補遺編の編集方針や「使い方」は「ピアノ・デュオ作品事典」と基本的に同じなので, そちらを参照して下さい。作曲家の略歴についても,「事典」に既に記述があるものは,生没年以外を割愛しました。
そして,この補遺編も公開されてから1年余りが過ぎ,多くの方々のご協力を得ながら,
少しずつ掲載された作曲家数も作品数も増えつつあります。これまでは IMSLP で入手可能な作品を取り上げてきましたが,
IMSLP にない作品でも楽譜が出版されているものは取り上げることにいたしました。
その場合は,出版情報:OOOとして出版社名と(IMSLP無し)と記してあります。
またファイルがIMSLPにあっても、特徴ある楽譜(スコア形式のものなど)が出版されている場合も, 出版情報:OOOとして出版社名を記しました。この場合は(IMSLP無し)の表記はなく,IMSLP のファイルの入手と, 新たな出版譜の購入を選択することができます。
補遺編としても,「事典」としての内容が整うまでには,まだ相当の期間が必要でしょう。 どうか辛抱強く,末永くお付き合い下さい。
2013年4月
![]() :「ピアノデュオ作品事典」増補改訂版に追加
:「ピアノデュオ作品事典」増補改訂版に追加
![]() :「ピアノデュオ作品事典」補遺版(このページ)で新規登載
:「ピアノデュオ作品事典」補遺版(このページ)で新規登載
アルカン Alkan,Charles Valentin(1813~88)フランス

終曲 Op.17
Finale[1838頃]
連弾(オリジナル)=Costallat & Cie.
★二短調―二長調 Assez vite : 力強く快活な軍隊行進曲風の曲想で,Sも力強い旋律を弾く。4手ともに連打音が頻出し,4手は接近しがち。(3'00″)[S:4/P:4]

「ドン・ジョヴァンニ」による4手のための幻想曲 Op.26
Fantasie à 4 mains sur Don Juan[1844刊]
連弾(オリジナル)=Bureau Central de Musique
★リストによる数々の作品に代表される,人気の高いオペラの旋律に基づく華麗なパラフレーズは19世紀中に広く流行したが,この作品は数あるパラフレーズ中でも,最も技巧的な作品のひとつ。Pの両手による厚い和音によるトレモロと,Sの両手によるトリルと音階の進行という,「地獄」の雰囲気を彷彿とさせる劇的なホ短調の序奏に始まり,モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」の1幕の終りの舞踏会の場面で,レポレッロによって歌い出される「さあ,こちらへおいで下さい」のテーマ(ハ長調)に基づく5つの変奏に続く。イ短調の第1変奏からPには至難な技巧が要求され,特に速い動きと器用さが必要。へ長調の第2変奏ではP,Sともにオクターヴの技巧が要求される。二短調~二長調の歌謡的な第3変奏では技巧的な面は後退するが,変ロ長調の第4変奏はまさに「連弾のための至難な練習曲」で,大半が4手ともにユニゾンによる急速な動きの連続。卜短調の第5変奏は深刻な曲想となり,再びハ長調に転じて「酒の歌」による終曲が軽快に始まり,徐々にテンポと音量を上げて壮絶で巨大なクライマックスに到達する。最後には41小節間に渡ってペダルを踏み続ける指示もある。音が多くて厚く,技巧的にもバランスの取り方も非常に難しい。特殊な調号の書き方にも注意が必要。(13′00″)[S:5/P:5]
***imslpには上記のほかに「サルタレッロ Saltarelle」(「チェロとピアノのための協奏的ソナタ Op.47」の終曲のアルカン自身による連弾用編曲)のファイルがあるが,誤って P.11が2回スキャンされているため P.13が欠落しており,ここでの記述を見送った。

アレンスキー(1861~1906)Arensky,Anton

リャビーニンの主題による幻想曲 Op.48
Fantasia on themes of Ryabinin [1899]
2台ピアノ(自編)=Jurgenson【原曲】ピアノと管弦楽
★ホ短調 Andante sostenuto - Allegretto - Tempo I:
ロシアの英雄叙事詩ブィリーナの歌い手,イヴァン・リャビーニンの歌をモスクワで聞いたアレンスキーが,
その旋律を書き留め,後にこの作品の主題とした。
重々しいオーケストラ(II)に続き,ソロ(I)による幅広く華麗なアルペッジョに乗せた,
いかにもロシア風の濃厚な抒情に満ちた感傷的な主題が登場する。中間部はリズミカルで軽快。
後半はさらに盛り上がり,ソロによる鍵盤の幅一杯のアルペッジョに乗って,はじめの主題が
II によって堂々と奏される。Iは連続オクターヴや幅広いアルペッジョのほか,素早い動きが必要とされる。
(9′00″)[I:5/II:3] 
12の小品 Op.66(全12曲)
Douze pièces [1903]
連弾(オリジナル)=Jurgenson
★晩年の傑作。この曲集中の作品には,旋律の進行によって二度の響きが生じる場面が多く, それがある瞬間には甘美に懐かしく,またある瞬間には痛切に悲しく響く。 健康面や生活状況の悪化からであろうか,曲想は枯淡の境地に達している。 「中くらいの難度」の表記がある。レッスンや発表会に,またリサイタルのアンコール・ピースとしても効果的。
[1]前奏曲 Prélude ホ短調 Aagio: バロック風のスタイルによる,とてもロマンティックな曲想。哀愁と孤独が色濃く感じられる。 (2′30″)[S:2/P:2]
[2]ガヴォット Gavotte 卜長調 Allegro non troppo : 繊細で優美。陽射しとその温もりが流れる雲によって遮られるように,長調と短調の間を滑らかに移ろう。 (1′30″)[S:2/P:2]
[3]バラード Ballade 卜短調: 前後の部分は歯切れのよい行進曲風。対照的に中間部は伸びやかな旋律を持つ。 (2′45″)[S:2/P:2]
[4]メヌエット Menuetto 変ホ長調 Allegro non troppo : 可憐な旋律を持つ。中間部の P と S によるカノンの動きが面白い。 (1′30″)[S:2/P:2]
[5]エレジーElégie ハ短調 Andante: 二度の甘美で痛切な響きが際立つ。中間部の耽美的な和音は, 2台のピアノのための「組曲 第4番」に通じるところがある。 (2′40″)[S:2/P:2]
[6]慰め Consolation ト長調 Allegretto:極めて繊細に澱みなく流れる即興曲風。 (0′45″)[S:3/P:3]
[7]ワルツ valse ハ長調 Allegro non troppo: 明るく優美な中にも,透明な憂いが混じる。生命力が昇華しつつ減衰していく風情。 (3′20″)[S:2/P:2]
[8]行進曲 Marche 卜長調 Allegro:活発で精気に満ちている。中間部の Sは, ショパンの「英雄ポロネーズ」の左手のオクターヴの進行さながらの迫力。 (3′00″)[S:2/P:2]
[9]ロマンス Romance ハ長調 Andante: 曲線的でロマンティックな旋律。完全に四声体で書かれ,1手が1声を担当するので, バランスや表現の格好の練習にもなる。(1′00″)[S:2/P:2]
[10]スケルツォ Scherzo ハ短調 Allegro: 2台のピアノのための「カノン形式の組曲」中の「小スケルツォ」と主題のリズムに共通点がある。 主部の中間部の夢見るような変ハ長調の部分が印象的。 (5′00")[S:2/P:2]
[11]子守歌 Berceuse 変口長調 Andantino: 限りない優しさに満ち,柔らかに下降する動きが穏やかな眠りを誘う。 (3′00")[S:3/P:3]
[12]ポルカ Polka へ長調 Allegro non troppo:
リズムや旋律が軽快なだけでなく,響きも明るく澄んでいる。
(1′00″)[S:2/P:2] 
アーン Hahn, Reynaldo(1874~1947)フランス

ベネズエラで主れ,3歳でパリに移住。パリ音楽院でマスネに作曲を,デュボワに和声を学ぶ。少年時代から美声の持ち主で,自作の歌曲の弾き語りはサロンで人気を博した。優雅で甘美な旋律を持つ多数の歌曲のほか,舞台作品も多く,晩年にはパリ・オペラ座監督に就任した。なお,生年は1875年説もある。
- ■アイルランドの歌による3つの前奏曲(全3曲)
Trois préludes sur des airs Irlandais[1895] - ■アリアと牧歌の形式による小品
Pièce en forme d'aria et bergerie[1896刊] - ■メランコリックなカプリス
Caprice mélancolique[1897] - ■子守歌集(全7曲)
Berceuses[1904刊] - ■カール・ライネッケの歌曲による子供の変奏曲
Variations puériles sur une mélodie de Carl Reinecke[1904] - ■傷病兵の眠りのために(全3曲)
Pour bercer un convalescent[1915] - ■ほどけたリボン(全12曲)
Le ruban dénoué[1915]
アイルランドの歌による3つの前奏曲(全3曲)
Trois préludes sur des airs Irlandais[1895]
連弾(オリジナル)=Heugel
★イギリスの作曲家,指揮者のチャールズ・スタンフォード編による歌集 “Songs of old Ireland:A collection of fifty lrish melodies ”(1882刊)中の作品に基づく。
[1]小さな赤いヒバリ The little red lark ト長調 Allegretto moderato: 主題はシンプルだが,その扱いは極めて入念で響きもピアニスティック。(1′05″)[S:2/P:3]
[2]私の恋人はイチゴノキ My love’s an arbutus ロ長調 Grazioso: アルフレッド・グレーヴスによる歌詞は,キラーニー地方のイチゴノキに例えて,その恋人を称えている内容。 民謡に伴奏付けしただけの作品ではなく,短い作品ながらも幻想曲風の自由な扱いが光る。(1′30″)[S:3/P:3]
[3]柳の木 The willou tree ハ短調 Presque lent,avec un sentiment très pathétique:
ゆっくりとした旋律,哀調を帯びた和声。 P,S ともに個々の技術的には全く難しくないが,
連弾曲として効果的に弾くのはかなりの経験が必要。(1′30″)[S:2/P:1] 
アリアと牧歌の形式による小品
Pièce en forme d'aria et bergerie[1896刊]
連弾(オリジナル)=Heugel
★あたかも「前奏曲とトッカータ」のような擬バロック的小品。
卜短調,Molto adagio の前半は,おもに P 自身でメランコリックなカノンを弾く。
特にこの前半は,非常にロマンティック。卜長調,Quatre fois plus vite の速い後半も,
やはり P 自身によるカノンの動きが多く対位法的。 P,S ともに素早く軽快な動きが必要。(3′00″)[S:4/P:4] 
メランコリックなカプリス
Caprice mélancolique[1897]
2台ピアノ(オリジナル)=Heugel (I・II分冊)
★嬰へ長調 Andantino poétique:
タイトルからは運動性に富んだ気紛れな曲想を想像するかもしれないが,
「ロマンティックなファンタジー」とでもしたほうが,ふさわしように思う。
一方のピアノがとてもさわやかでロマンティックな旋律を弾き,
他方が美しい響きのアルペッジョやトリル,対旋律などで優美な装飾を加える,とりとめのない素敵な夢のような作品。
2台のピアノの対話や掛合いの機会がこれほど多い作品も珍しいほどで,
ピアノ・デュオにこうした楽しみを求めるのに最適。(3′40″)[I:4/II:4] 
子守歌集(全7曲)
Berceuses[1904刊]
連弾(オリジナル)=Heugel
★親密で穏やかな雰囲気の,繊細な子守歌の曲集。 全曲中,fの指示は2曲目に一箇所登場するのみ。カノン風の動きが多く使われている。
[1]雲のない日の子守歌 Berceuse des jours sans nuages イ長調 Andantino: 2/4拍子でメッゾ・スタッカートの伴奏による,民俗舞曲風。 短い中間部の P と S による反行する動きがおもしろい。(0'50")[S:2/P:2]
[2]クリスマスイヴのための子守歌 Berceuse pour la veille de Noël へ長調 Allegretto molto tranquillo: 流れるような旋律の中に,落ち着いた喜ばしさがある。多声的でカノンの動きが多い。(1′30″)[S:2/P:3]
[3]海の子供のための子守歌 Berceuse pour les enfants de marins ハ短調 Un peu lent: P と S は互いに先になり,後になりしながら,密やかなカノンを奏する。(0'55")[S:2/P:2]
[4]秋の夕暮れの子守歌 Berceuse des soirs d'automne 変イ長調 Tranquille,discret: 穏やかで控え目な優しさに満ちている。(1′50″)[S:2/P:3]
[5]「セルフィアーナ」クレオルの子守歌 “Selfiana” Berceuse créole ホ長調: 快適に揺れるようなリズムに乗って,南国の民謡風の旋律が流れる。 旋律が音階的に下降する中間部が神秘的。「セルフィアーナ」は人名の固有名詞であろうか。(1′10″)[S:2/P:2]
[6]物思わしげな子守歌 Berceuse pensive イ短調 Andantino legato: 3連符による行きつ戻りつするターン音型が,答えが見出せないまま物思いに耽っている様子を表しているようだ。 P は右手のみで,この作品は3手用。(1′00″)[S:3/P:2]
[7]優しい子守歌 Berceuse tendre 卜長調 Allegretto moderato:
多声的な旋律はいずれも温和な透明感に満ちている。(1′10″)[S:3/P:3] 
カール・ライネッケの歌曲による子供の変奏曲
Variations puériles sur une mélodie de Carl Reinecke[1904]
連弾(オリジナル)=Heugel
★変ホ長調 Andantino espressivo : 弾くのをためらうような2小節の序奏に8小節のシンプルな主題が続く。
第6変奏まではそれぞれ8小節のため,一気に変奏が進行するが,第7変奏は14小節。
その後の第10変奏までは16,32小節と規模が大きくなる。
軽快で素早く動き回る第11,12変奏で再び8小節となり,
落ち着いたコーダを経てテンポも次第にゆっくりとなり静かに終わる。
各変奏は短いうえ,各種の技術的な課題ともなり,学習用としても有益。
原曲はライネッケの「子供の歌曲集 Op.91-3」(6′00″)[S:3/P:3] 
傷病兵の眠りのために(全3曲)
Pour bercer un convalescent[1915]
2台ピアノ(オリジナル)=Heugel
★深い安らぎと透明な悲しみに満ちた小品集。 第306歩兵連隊の軍曹として,フランス北東部の激戦地,エーヌ(Aisne)の戦闘で 重傷を負ったアンリ・バルダックに捧げられている。
[1]変ロ長調 Andantino sans lenteur:II による,静かに呼吸するかのような伴奏の上に, Iが息の長い旋律をやはり静かに弾く。(1′25″)[I:2/II:3]
[2]嬰へ短調 Andantino non lento:旋律線が常に下降線を描くワルツ。 悲しみの中にも憤りが感じられる。(1′25″)[I:4/II:4]
[3]イ長調 Andantino espressivo: 9/8 拍子の流麗なリズムに乗って,安らぎに満ちた旋律が歌われる。
(1′10″)[I:3/II:3] 
ほどけたリボン(全12曲)
Le ruban dénoué[1915]
2台ピアノ(オリジナル)=Heugel
★ピュイグ=ロジェと高野耀子の演奏による fontec盤のタイトルは「ひもときし手紙のリボン」。 楽譜の表紙には「2台のピアノのための12のワルツと 1曲の歌曲(『くちづけのゆえに』,ヴィクトル・ユゴー詩)」と記されている。 各曲はそれらの詩的なタイトル通りの,いずれも極めて濃厚なロマンと 豊かな情感をたたえた作品で,ピアニスティック。
[1]気まぐれな運命の戯れ Décrets indolents du hasard 嬰へ短調 Moderato: 3拍子と(3拍)4連符が交錯する,揺れるようなリズムを持つ。 非常にロマンティックな曲想。(1′30″)[I:3/II:3]
[2]アルビの黄昏 Les soirs d'Albi 嬰へ長調 vif et leste: 極めて活発で明快。ラテン・アメリカの民謡風の旋律を持つワルツも登場する。(2′20″)[I:5/II:5]
[3]思い出・・・未来・・・ Souvenir…Avanir… 二長調 Mouvt de valse lente: まさしく「懐かしい甘い記憶」と「飛翔する夢と希望」といった風情。(2′15″)[I:3/II:3]
[4]愛と哀しみの舞い Danse de l'amour et du chagrin ト短調 Même mouvt que la précédente: 同形のフレーズが調を変えて繰り返され,その反復に連れて哀しみが増す。 次のワルツに続く。技術的には曲集中,最も易しい。(1′30″)[I:2/II:2]
[5]甘き疲れ Le demi-sommeil embaumé 卜長調 Plus lent: 旋律も和声も極めて半音階的。途中,微かにラテン・アメリカの香りを感じさせるシンプルなワルツも登場し, 曲想も多彩でリズムも複雑。(5′50″)[I:5/II:5]
[6]失われた指輪 L'anneau perdu Molto vivo :2拍子の奇想曲風のリズミカルな部分と滑らかな旋律的な部分を持つ。 嬰へ短調で始まり,頻繁に調性が変わる。(1′40″)[I:3/II:3]
[7]不安と希望の舞い Danse du doute et de l'espérance 変ホ長調 Moderato: シューベルト讃。転調が絶妙。(1′55″)[I:4/II:3]
[8]聞かれた鳥籠 La cage ouverte ロ長調 Molto animato: 明朗で快活。I のみが2拍子となる小節があり,柔軟なルバートの効果がある。(2′20″)[I:4/II:4]
[9]雷雨の晩 Soir d'orage 嬰ト短調 Misterioso,non troppo lento: 光る稲妻,轟く雷鳴,といった荒々しさはないが,終始,憂鬱に弱音で奏される。(2′35″)[I:3/II:3]
[10]口づけ Les baisers ホ長調 Appassionato, non troppo presto: 揺れるようなリズムで始まり,2台のピアノの親密な会話,1曲目の回想と変化に富む内容。 次の曲に続く。(2′50″)[I:4/II:4]
[11]微笑 Il sorriso ホ長調 Stesso tempo: 2/4拍子の旋律に3/4拍子の伴奏が奏される。装飾音や3連符を含む旋律は,やはりラテン・アメリカの雰囲気だが, 静かで優雅。より穏やかな,子守歌風の中間部を持つ。(3′10″)[I:3/II:3]
[12]ただ一つの愛 Le seul amour 変イ長調 Presque lent,très senti:
じっくりと時間をかけて上昇していく主題が反復され,曲想も情熱的に盛り上がるが,
最後は静かに収まる。(5′00″)[I:5/II:5]

「事典」には全音ピースの2曲しか掲載できなかったが,実に優れた,そして親しみやすい連弾作品を多く残し,再評価されるべきドイツ・ロマン派の作曲家の一人。
- ■3つのピアノ小品 Op.18(全3曲)
Drei Klaviersücke[1864刊] - ■牧歌集 Op.43(全8曲)
Idyllen[1873刊] - ■婚礼の音楽 Op.45(全4曲)
Hochzeitsmusik[1873刊] - ■セレナード Op.59(全6曲)
Abendmusik[1877刊] - ■人生の絵 Op.60(全6曲)
Lebensbilder[1877刊] - ■シルエット Op.62(全6曲)
Silhouetten[1877刊] - ■2つの小品 Op.65(全2曲)
Zwei stücke[1881刊]
3つのピアノ小品 Op.18(全3曲)
Drei Klaviersücke[1864刊]
連弾(オリジナル)=Universal
★長い生涯には恵まれないまでも,多作なイェンゼンの連弾作品中, 初期の力作。「小品」というタイトルながら,特に2,3は長大なだけに,飽きさせないで聴かせるためには演奏上のさまざまな演出が必要。
[1]スケルツォ Scherzo ト長調 Lebhaft: 軽快なリズムの,いかにもPとSとの「戯れ」のような曲想。優美な旋律のトリオはかなり長く,徐々に快活な雰囲気に復帰する。(4′40″) [S3/P3]
[2]子守歌 Wiegenlied ハ長調 ln zarter,ruhig gleitender Bewegung:繊細で流麗な旋律に満ちた長大な作品。細かい動きの伴奏型や情熱的な盛り上がりは「舟歌」の趣。 (6′00″)[S3/P3]
[3]牧歌 Pastrale 変イ長調 Nicht zu schnell, mit heiterer Grazie:3拍子ののどかなレントラー風。長い絵巻物を見るように,次々と場面が移り変わる。低音域で音が厚い部分もあり,バランスには注意が必要。長い作品(見開きでP,S合計18ページ)だけに,舞曲に息づくリズムの面白さを表現する工夫が必要。(7′30″)[S3/P3]

牧歌集 Op.43(全8曲)
Idyllen[1873刊]
連弾(オリジナル)=Universal
★2手版もあり,そちらを「3つの牧歌」としている資料もあるが,初版を出版したハイナウアー社の19世紀のカタログでは,両版ともに全8曲。ピアニスティックなうえ,響きは多彩で曲想は極めてロマンティック。各曲の曲想も対照的で,響きも多様であり,連弾曲としての書法も申し分なく,注目に値する傑作。
[1]黎明 Morgendämmerung 口長調 In erwartungsvoller Erregung:冒頭には古代ギリシャ三大悲劇詩人の一人,アイスキュロスによる「アガメムノン」中の「ことわざ通りに,母なる夜から喜びの知らせが来たるように。~」という一節が掲げられている。タイトル通り,光りの階調が刻々と移り変わる雄大な夜明けの景色を眼前にする感があり,輝かしいクライマックスを迎える。(4′30″)[S4/P4]
[2]野の,森のそして草原の神々 Feld-,Wald-und Wiesengötter 嬰へ長調 Schnell,voll Anmut und Leben:黒鍵の使用が多いだけに響きは極めて輝かしく,軽快な曲想のスケルツォ風の楽章。まるで優美なバレエ音楽のようで,P,Sともに軽快で素早い動きが要求される。(6′40″)[S4/P4]
[3]森の小鳥 Waldvölein 二長調 Lebhaft und leicht:ギリシャ最大の喜劇作者アリストパネスによる「鳥」から,「愛しい妻よ,さあ起きなさい!清らかな歌の泉を湧き出させよう。・・・おお,父なるゼウスよ!小鳥はなんと楽しそうに歌うのか。甘い歌がなんと大小の葉を砂糖で包むのか」の部分が掲げられている。短い作品だが軽妙で愛らしく,また短調に傾きやすく,憂いもたたえている。終り近くのPによって2羽の鳥が鳴き交わす部分(2手版にはない)は秀逸。(1′30″)[S3/P3]
[4]ドライアッド Dryade ト長調 sehr lebhaft und zart:ギリシャ神話の木の精。Sによる,ショパンの「24の前奏曲 Op.28」の3曲目と同様のつぶやくような伴奏型の上に,Pはさわやかで明朗な旋律を奏でる。(2’50″)[S3/P3]
[5]真昼の静けさ Mittagsstille 変ホ長調 In ruhiger Bewegung:PとSによる表情豊かで抒情的な旋律のデュエット。特に後半,PとSとが手を交差させて弾く部分以降は非常に甘美なうえ,陶酔的でロマンティック。アンコール・ピースとしても極めて印象的,効果的な作品。「風にそよぐ松の樹下に来たりて座りたまえ。小川の水音にパンの笛は鳴り,魔力によって深い眠りに陥る。」というプラトンの言葉が掲げられている。なお,この出典は「ギリシャ詞華集(Griechische Anthologie)」(5′00″)[S3/P3]
[6]夕方近く Abendnähe 口長調 Mä ßig bewegt,ausdrucksvoll :「~我らは厚く敷かれたイ草と摘まれたばかりの葡萄の葉のベッドに安らかに横たわった。頭上にはポプラと楡の葉が揺れ,ニンフの岩屋からは清い泉が流れ,鳥たちは歌い,蜂は戯れる。~」といった,牧歌の元祖とも称されるヘレニズム時代の詩人テオクリトスの「エイデュリア(小景詩)第7歌」からの詩が掲げられている。Pによる情緒纏綿とした旋律。Sはほとんど伴奏を担当するが,伴奏型は極めて多彩で飽きさせない。(3′20″)[S3/P3]
[7]夜(眠りの神と死の神。) Nacht(Hypnos-Thanatos.) ロ短調 Leidenschaftlich:全編,暗い情熱に満ち,途中で何度も大きく盛り上がるが静かに始まり,静かに終わる。(4′00″)[S3/P3]
[8]バッカスの祭り Dionysosfeier 口長調 Heiter belebt:アリストパネスの「雲」から,「来ませよ,松明に照らされて,パルナッソスの山峡の歓楽の夜にいます君よ。デルフォイのバッカスの巫女たちを率いる,快楽の王ディオニュソスよ」の箇所が掲げられている。神事の始まりを告げるかのような格調高くさわやかなファンファーレで始まり,神々の祭りにふさわしい明朗で優美な,時にはユーモラスな旋律が次々に登場し,輝かしい響きで力強く終わる。(5′50″)[S3/P3] 
婚礼の音楽 Op.45(全4曲)
Hochzeitsmusik[1873刊]
連弾(オリジナル)=Hainauer,Universal
★ロマン派の濃厚な抒情に満ちた親しみやすい作品。Sも伴奏を担当するだけでなく,効果的で美しい旋律や対旋律を弾く機会が多く,P,Sともに楽しめる。また音が厚く,響きは多彩で艶やか。楽譜の扉にはアリストパネスの喜劇「鳥」の終り近くの,新婦の類稀れな美しさを褒めて婚礼を祝う内容の,伝令使の台詞が掲げられている。
[1]祝賀行列 Festzug ハ長調 Allegro risoluto:威厳に満ちた華やかなファンファーレで始まる明朗で快活な作品。中間部の陶酔的な高揚感が印象的。(3′40″)[S3/P3]
[2]花嫁の歌 Brautgesang ホ長調 Con tenerezza:半音の動きを含んだ穏やかな表情の流麗な旋律と,スタッカートの記号が多く付けられた軽快な旋律を持つ。Sによる伴奏もメロディアスで,Pとのリズム的な連携が緊密。(4′30″)[S3/P3]
[3]輪舞 Reigen 卜長調 Allegretto grazioso:Sの軽快で,しかも極めて多彩な伴奏に乗せて,Pが快活で輝かしい旋律を弾く。Pの両手は接近し,また連打音が多いため「指さばき」の器用さが必要。Sの対旋律も実に雄弁で楽しく,ピアニスティックな演奏効果も高い。Pによるはじめの旋律はシューマンの「アンダンテと変奏曲」中の一変奏を思わせる。(2′30″)[S4/P5]
[4]夜想曲 Notturno ハ長調 Andantino espressivo:雄大なスケールを持ち,盛り上がりは熱狂的。管弦楽曲の編曲では,と思えるほど音が厚く響きも多彩。 4/4拍子で2分音符=76というテンポ指示はかなり速く,技術的には難しくなるが,それだけに曲想は引き締まる。(4′15″)[S4/P4] 
セレナード Op.59(全6曲)
Abendmusik[1877刊]
連弾(オリジナル)=Hainauer
★技術的に難しくなく,比較的短い作品による組曲。しかしPとSとの連携が精緻で両者の旋律的,リズム的な掛合いも多く,全6曲の調性や曲想も変化に富む。このうち,1,2番(全音ピアノ連弾ピース。タイトルは「セレナーデ」)は「事典」に掲載済み。
[3]へ長調 Allegretto:スタッカートや装飾音の多い軽快,快活な旋律を持つ。(1′25″)[S2/P3]
[4]ハ長調 Andantino:繊細なリズムによる穏やかな曲想。Sも旋律を弾いて活躍する。途中,情熱的に盛り上がるが静かに終わる。(2′00″)[S3/P3]
[5]ホ短調 Moderato espressivo: Pがおもに32分音符による技巧的な動きの旋律を弾くエレジー風の曲想。PはSとの手の交差や自身の両手の交差がある。Pは旋律を機械的な動きを感じさせずに弾く工夫が必要。(2′20″)[S2/P3]
[6]終曲 Finale ハ長調 Allegro ma non troppo:Sの軽快な伴奏に乗せて,Pが明朗,快活な旋律を弾く。響きも透明で輝かしい。Pは両手が接近し,また両手の滑らかな「弾き継ぎ」が必要。(2′00″)[S3/P3] 
人生の絵 Op.60(全6曲)
Lebensbilder[1877刊]
連弾(オリジナル)=Universal
★人生の様々な場面を音で描いた作品で,「人生に対して肯定的」に始まるが,最後の曲が極めて暗く絶望的なのは,イェンゼン自身の後半生の健康が害されていたためであろうか。
[1]騎士の間にて Im Rittersall 変ホ長調 Allegro festivo:付点リズムが多用された行進曲風の作品。充実した輝かしい響きで精力的に進行するが,堅苦しさは全くなく,後半には夢見るように甘美な部分も用意され,「夢と冒険に満ちたロマン的な物語」の始まりを告げる。コーダ以外の前半部,後半部とも反復される。(4′10″)[S3/P3]
[2]泉で Am Brunnen ホ長調 Allegretto leggiero:清らかな泉が湧き出すかのような軽快な16分音符による音型が,PとSの間で受け渡される。終り近くは特にロマンティック。(2′25″)[S4/P4]
[3]兵士の行進 Soldatenmarsch ト長調 Allegro comodo:快活な行進曲。曲のはじめに登場する,2拍目やその「裏」にアクセントを持つ旋律がユニーク。旋律のリズムが面白いが,それだけにPはリズムや3度重音の連続が難しい。またSは主に伴奏を担当するが,指の「置き換え」や少数ながら9度音程の和音もある。変ホ長調のトリオで,Sは小太鼓のロールを奏する。(2′50″)[S4/P4]
[4]夏の喜び Sommerlust へ長調 Allegro risoluto:Sによる,終始無窮動風の動きの伴奏に乗って,Pによる晴れやかな旋律が踊り戯れる。前,後半ともに反復する。(2′45″)[S3/P3]
[5]ジプシーのコンサート Zigeunerkonzert イ短調 Presto molto agitato:名技的なヴァイオリンの旋律を模した作品。ジプシー風のエキゾチックなムード一辺倒ではなく,ドイツ・ロマン派風の抒情が混在している。Sは伴奏中心。(4′35″)[S3/P3]
[6]野辺の送り Letzter Gang ハ短調 Grave:死者を悼む荘重な作品。この種の作品では常套的な「ピカルディ3度」ではなく,ハ短調の主和音による終止のため,絶望的な喪失感が増す。(5′00″)[S2/P2] 
シルエット Op.62(全6曲)
Silhouetten[1877刊]
連弾(オリジナル)=Universal
★イェンゼンが得意な描写的な作品。さまざまな人物像を音で描いており,それぞれの登場人物はユニークなだけに,各曲の変化の振幅は大きい。
[1]ふたりで Zu Zweien ハ長調 Andantino:伸びやかで明朗な旋律をPとSがカノン風に交互に歌う。和音が非常にロマンティック。(2′00″)[S3/P3]
[2]コロンビーナ Colombina ハ短調 Risoluto:コンメディア・デッラルテでの女性の召使役。短調と長調が頻繁に交替し,焦燥と熱情に駆られて力強く疾走する。(1′30″)[S4/P4]
[3]騒々しい子 Sausewind へ長調 Molto vivace:明るく軽快なワルツ。3小節のフレーズを中心とし,不規則な小節数のフレーズが多く,落ち着かない印象を与える。(2′00″)[S3/P4]
[4]のんき者 Dolce far niente ホ長調 Andante quieto:連打音を多用した,温かい雰囲気の落ち着いた旋律が,ゆっくりと上昇する。 P,Sともにトレモロを使って大きく盛り上がる最後はまさに多幸多福の感が強い。(4′10″)[S3/P3]
[5]酒飲み(エセレルス,司教座聖堂参事会員とフーノルド) Die Zecher Ethelerus,der Kanonikus und Hunord ハ短調 Allegro ma non troppo:ユリウス・ヴォルフ作「ネズミ捕り男」より。エセレルスとフーノルド(ネズミ捕り男)は登場人物。力強く,気紛れなスケルツォ風の作品で短前打音が付加されたSの伴奏によって滑稽味も増す。特にPは軽快で素早い動きが要求される。(3′00″)[S3/P4]
[6]おばあちゃん Grossmütterchen ト長調 Allegretto comodo:年を取っても衰えとは全く無縁のようで,旋律は快活でリズムは軽快,そして洒落た和音が使われた舞曲風の作品。(1′45″)[S3/P3] 
2つの小品 Op.65(全2曲)
Zwei stücke[1881刊]
連弾(オリジナル)=Universal
★2曲とも曲想はロマンティックで親しみやすいが,凝った和声やリズムを持つ作品だけに技術的にやや難しい。
[1]薔薇のからまるあずまや Die Rosenlaube イ長調 Con espressione:ロマンティックで流動的な旋律は,繊細に変化する後期ロマン派風の豊かな和声に支えられている。Sの伴奏型は多彩なだけに,さまざまなテクニックを要求される。(3′15″)[S4/P3]
[2]オランダ人の踊り Holländer-Tanz 卜短調 Moderato poco pesante:哀調を帯びた旋律とやや重々しいリズムの舞曲。ト長調の中間部以降,細分化されたリズムによる旋律も和声も民族色が濃厚となる。Pは5点イ音(88鍵での最高音の3度下)も使われるが,両手は接近しがち。(3′25″)[S4/P4] 
- ヴィッテ Witte, George Hendrik

- ヴィルム Wilm,Nicolai von

- ヴィルムス Wilms, Johan Wilhelm

- ヴィンクレル Winkler, Alexandre

ヴィッテ(1843~1929)Witte, George Hendrik オランダ

ユトレヒトでオルガン製作者の家庭に生れ,ハーグ音楽院で学んだ後,ライプツィヒ音楽院でモシェレスやライネッケに師事。短いオランダ生活の後,ドイツに戻りエッセンで指揮者,作曲家,ピアノ教師として活躍した。多作な作曲家ではないが,ピアノ作品や歌曲のほか,チェロ協奏曲やヴァイオリン協奏曲を残す。同時代のドイツの音楽家たちとの関わりも深く,ピアノ連弾曲「3つの小品 Op.2」はクララ・シューマンに献呈されている。
ワルツ集 Op.7(全12曲)
Walzer[1868]
連弾(オリジナル)=Praeger&Meier
★ブラームスに献呈された作品で,ブラームスの「ワルツ集 Op.39」へのオマージュ。
ブラームスのわずか3年後の作品ながら,後期ロマン派風の甘美な香りが濃厚で,転調も興味深い。S も単純な伴奏だけでなく,P との掛合いや模倣的な動きが多く,弾いても聴いても楽しく,そして極めて効果的な作品。各曲は長くても1ページ半程度。

[1]ロ長調 Commodo:軽い短前打音によって旋律の優雅さが増す。短い作品ながら,意外な転調を伴って大きく盛り上がり,燃焼度も高い。(1′00″)[S2/P3]
[2]嬰へ短調 Tranquillo:淡い悲哀と感傷。S の右手による和音群から隠された旋律を探すのも一興。(1′15″)[S2/P3]
[3]イ長調 Moderato resoluto:優美で可憐。S の短くさりげない音型が実に効果的。(1′00″)[S3/P3]
[4]ホ長調 Poco vivace:PとSとによる,この上なく優雅でロマンティックな音の戯れ。特に後半のPの3連符のリズムは楽しい。響きはキラキラと輝き,リサイタルのアンコールにも最適。(1′00″)[S3/P3]
[5]卜長調 Allegretto con moto:流麗なリズムと旋律を持ち,ヘミオラの進行も面白い。2オクターヴに渡って順次進行で下降するバスも印象的。(1′25″)[S3/P3]
[6]口短調 Animato assai ― poco tranquillo:激烈な前・後半部とは対照的な穏やかなホ長調の中間部(ブラームスの「ワルツ集」の2番と同じモティーフ)を持つ。(1′35″)[S3/P3]
[7]卜長調 Moderato espressivo:曲線的なモティーフがカノン風に処理され,豊かな情感に満ちて長調と短調の間を繊細に行き来する。P と S の手が交差する。(1′30″)[S3/P3]
[8]ホ長調 Animato:優美な曲想でカノン風の処理が多い。P と S の手が交差する。(1′10″)[S3/P3]
[9]イ長調 Allegretto commodo:P による繊細な動きの旋律の二重唱。微妙な明暗の変化は極めて詩的。(2′30″)[S1/P3]
[10]二短調 Allegro impetuoso:シンコペートされた和音が,めくるめく華麗な激情の火花を散らす。(1′10″)[S4/P4]
[11]二長調 Tranquillo:P によるなだらかな旋律で静かに始まるが,音階的な上下動を繰り返しながらスケール豊かに盛り上がる(88鍵の最低音も使用)重厚なワルツ。最後は静かに収まる。(2′20″)[S3/P4]
[12]ト長調 Allegro con fuoco:力強く輝かしい。全曲を弾いた場合,特に最後の4曲に特徴的な「繊細」「激情」「重厚」「光輝」の変化による演奏効果は極めて大きい。(1′05″)[S3/P4]
ヴィルム(1834~1911)Wilm,Nicolai von ドイツ

ロシア(現ラトヴィア)のリガで生れ,ライプツィヒ音楽院でピアノやオルガンのほか,ヴァイオリンも学ぶ。ロシアで15年ほど教職に就いた後,ドレスデン時代を経てヴィースバーデンに住み,おもに室内楽曲やピアノ作品を書き続けた。多作な作曲家として知られ,そのデュオ作品はいずれも親しみやすい。特に演奏時間も適当で効果的な2台のピアノのための作品群は注目に値する。
- ■ワルツ即興曲 Op.2
Valse-Impromptu[1877刊] - ■序奏とガヴォット Op.60
Introduction und Gavotte[1887刊] - ■変奏曲 Op.64
Variationen[1887刊] - ■ワルツ Op.72
Walzer[1888刊] - ■スイス組曲 Op.130(全7曲)
Schweizer Suite[1894刊]
ワルツ即興曲 Op.2
Valse-Impromptu[1877刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Ries & Erler
★変イ長調 Molto vivace e leggieramente:軽快でさわやかな主題を持ち,全曲を通してIとIIの掛合いが多く,楽しく親しみやすい曲想は2台ピアノ作品の入門用にも最適。中間部の息が長く滑らかな主題は,IとIIが旋律と伴奏の役割を交替しつつ展開されるが,主部ではIIは「従的」な役割を担っている。(3′30″)[I:2/II:2]

序奏とガヴォット Op.60
Introduction und Gavotte[1887刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Ries & Erler(I・II分冊)
★ト短調 Maestoso 卜短調 Animato:(複)付点リズムを多用した荘重で悲愴なバロック的な序奏に,短調だが活気のあるガヴォットが続く。卜長調,Meno mosso の中間部は典雅でかわいらしい。IとIIの組合わせが極めて巧妙で,効果的であるだけでなく弾いて楽しい作品。「ガヴォット」は3度重音の進行や和音奏がやや難しい。(8′25″)[I:3/II:3]

変奏曲 Op.64
Variationen[1887刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Leuckart
★主題と10の変奏。ト長調,Andantino の瑞々しくロマンティックな8小節の主題がIによって弾き出されると,それに答えてIIが次の8小節を弾き継いだ後,両者の合奏となる。より曲線的な旋律の第1変奏でもこうしたIとIIの役割は維持され,IとIIとの軽快でリズミカルな掛合いとなる第2変奏,掛合いでも一転してゆったりとしてメロディアスな第3変奏と続く。精力的で大胆な足取りの第4変奏の後,荘重なテンポで途中で大きく盛り上がるト短調の第5変奏,再びト長調となり軽快な装飾音に彩られた第6変奏,オクターヴ以上の幅広いアルペッジョとオクターヴの進行を多用した堂々とした第7変奏,IとIIとの素早く力強い掛合いの第8変奏,澄んだ響きの子守歌風の第9変奏と続き,第10変奏では輝くようなアルペッジョとオクターヴの進行で最高潮に達した後,静かに収まり主題が回想されて終わる。各変奏毎にテンポが変化し曲想も極めて多彩であり,何よりも新鮮な抒情が際立つ作品。なお,この楽譜はスコア形式ながらI,IIそれぞれに専用(相手のパートは小さい音符で印刷されている)の贅沢な作り。 (16′40″)[I:4/II:4]

ワルツ Op.72
Walzer[1888刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Leuckart(I・II分冊)
★変口短調 Andante sostenuto ― 変ロ長調 Tempo di valse:いかにもドイツ・ロマン派的で重厚な序曲で,しかも管弦楽的で色彩感豊かな「Intrada(幕開き音楽)」に,華麗でピアニスティックなワルツ群が続く。イントラーダの重厚さと次々に表れるワルツ群の抜群の楽しさも対照的で,暗く深い森からいきなり遊園地に出る感がある。聴くだけでなく,IとIIの掛合いも多く,両者ともに弾いて面白い作品。華やかに盛り上がって終わる。(9′00″)[I:4/II:4]

スイス組曲 Op.130(全7曲)
Schweizer Suite[1894刊]
連弾(オリジナル)=Gebrüder Hug
★ヴィルムの得意分野の一つである描写的作品。各曲はドイツ・ロマン派風で親しみやすく,また組曲として変化にも富む。スイスの名所旧跡を訪ねる連弾による「スイス旅行」の趣。
[1]黎明と日の出 Morgendämmerung und Sonnenaufgang へ短調― へ長調 Grave:いかにも「闇」らしい低音で静かに始まり,さざめくようなトレモロとSの左手による半音階の悠然とした上昇で夜が明ける。次の曲に続く。(3′00″)[S2/P2]
[2]登山への出発 Aufbruch in's Gebirge へ長調 Allegro energico:活気に満ちた行進曲。登山道と景色もさまざまに移り変わる。雄大にそびえる山を目指すのであろう。曲想も壮大。最後はテンポを速めて山頂に駆け登る。(4′00")[S3/P3]
[3]フィーアバルトシュテッター湖上で Auf dem Vierwaldstädter See ハ長調 Allegretto:ルツェルン湖での舟遊び。 6/8拍子の優美でロマンティックな舟歌。PとSの連携が極めて緊密で楽しく弾ける。(3′20″)[S3/P3]
[4]ブリュムリスアルプで Auf dem Blümlisalp 変口長調 Animato:快活なレントラー風の舞曲。変ト長調の中間部はやや遅く滑らか。(4′45″)[S4/P3]
[5]シヨン城 Schlßs Chillon へ短調 Andante:レマン湖に浮かぶように見える城。主部は憂愁と感傷に満ちたゆったりとした旋律が歌われ,古城の遠い歴史や伝説を思い起こさせる。激しい曲想の中間部を持つ。(3′40″)[S3/P3]
[6]ラウターブルンネンの谷で lm Lauterbrunner Thal 変イ長調 Tranquillo assai:さわやかな曲想の舞曲風の作品。中間部では角笛が山々にこだまする。(2′30″)[S3/P3]
[7]リュトリ Das Rütli へ短調―へ長調 Moderato - Più animato:ウルナー湖畔に位置するスイス誕生の地「リュトリ」。ゆったりとしたファンファーレで始まり,徐々にテンポを上げて嵐のように激しく高まった後,民謡のメロディが力強く歌われて全曲の幕を閉じる。(4′10″)[S3/P3]

ヴィルムス(1772~1847)Wilms, Johan Wilhelm オランダ

ドイツ西部のヴィツヘルデンで生れ,はじめは父に,次いで兄にピアノと理論を学び,後にはフルートも学んだ。 1791年にアムステルダムに行き,音楽教師やピアニストとして活躍し,創設にも関与したエルディツィオ・ムジカではフルート奏者のほか,指揮者も務めた。このオーケストラは特にモーツァルトの作品をオランダに広めるのに貢献し,ヴィルムス自身もピアニストとしてモーツァルトやベートーヴェンのピアノ協奏曲を演奏している。またバプティスト教会のオルガニストを勤め,19世紀のオランダ国歌の作曲者としても知られる。7曲の交響曲や5曲のピアノ協奏曲のほか,多数の作品を残し,連弾のためのソナタは下記のほかに「二長調 Op.7」「ハ長調 Op.31」がある。
ソナタ Op.41(3楽章)
Sonate[1814]
連弾(オリジナル)=Peters
★P,Sともにソロを弾いたり,相手との対話や掛合い,模倣の機会が極めて多く,PとSが協奏曲のように扱われている華麗で実に楽しい作品。旋律の多くが古典派的,具体的にはモーツァルトやハイドンのそれに似てはいるものの,各部の大胆な変化や転調はロマン的な演奏がふさわしいユニークな作風である。現代とは異なる当時の楽器の特性として,低音域での密集和音が多く,その響きが重すぎないように弾く工夫が必要なのと,現代の機能的な楽譜に慣れた目には,リトグラフによる楽譜への多少の慣れが必要。コンサート用としてもレッスン用としても極めて貴重な存在である。

[第1楽章] 変口長調 Allegro:生気に満ちて溌刺としたリズムと快活で伸びやかな旋律を持つだけに,P,Sともに音階的な動きには明晰なタッチと素早い指の動きが要求される。[11′40″ S4/P4]
[第2楽章] 変ホ長調 Poco Adagio:多くの装飾音に彩られた表情豊かな旋律を備えている。全編が「歌」に満ちた艶麗な楽章だが,93小節以降のP自体による,そしてその後のPとSによるデュエットが特に魅力的。[7′00″ S4/P4]
[第3楽章] ロンド Rondo 変ロ長調 Allegro:実に快活で明快なロンド。華麗な名技的要素も十分に備えてPもSも奔放に遊び回り,主調から遠い口長調を経た後,賑々しい大団円を迎える。[6′40″ S4/P4]
ヴィンクレル(1865~1935)Winkler, Alexandre ロシア

ハリコフで生れ,ハリコフ大学で法学を学んだが,ロシア音楽協会の音楽学校でピアノを学び,更にパリではデュヴェルノワに,ウィーンではレシェティツキーに師事。ペテルブルク音楽院教授としてプロコフィエフを教えている。 1924年,フランスに亡命。生涯に残した作品は多くはないが,グラズノフやグリンカ等の多くのロシアの作品を連弾用に編曲している。
バッハの主題による変奏曲とフーガ Op.12
Variations et fugue sur un théme de J.S.Bach[1906刊]
2台ピアノ(オリジナル)= Belaieff
★変ホ長調:主題はバッハの「無伴奏チェロ組曲 第4番 BWV.1010」の「サラバンド」。主題と7つの変奏に終曲のフーガが続く。 20世紀初頭の作品だが,完全にロマン派風で極めてピアニスティック。ベテルブルク音楽院の学生のための作品で,I とIIで役割を交替する箇所が実に多く,多種多様のピアノ技巧の練習曲ともなっており,また各変奏ごとにテンポと拍子が変化する。主題は原曲をほぼ忠実に扱っているが,第1変奏は旋律が流麗に変奏されて旋律や和声に半音階的な動きが多く使われる。第2変奏は軽妙でかわいらしいポロネーズ。清冽な水の流れのような,急速な音階やアルペッジョの軽快な上下行をIとIIとが弾き交わす第3変奏,ロマンティックで美麗な旋律をIとIIとが歌い交わすノクターン風の第4変奏,一転して重厚なカノン風の第5変奏。きびきびとした動きの輝かしいスケルツォ風の第6変奏と続く。第7変奏は変ホ短調の「嘆きの歌」となり,変ホ長調に転じてフーガに流れ込む。フーガの主題は起伏に富み,極めて躍動的な性格を備え,強拍に親指を指定したやや特殊な運指(多分,ヴィンクレル自身による)によって,主題の力強さが一層鮮明となる。技術的には難しいフーガだが,両手による疑似オクターヴのトリルのような派手な演奏効果を撒き散らしながら華々しく展開され,輝かしく壮大なクライマックスに到達する。(17′00″)[I:5/II:5]

セレナード Op.20(3楽章)
Serenade[1892]
連弾(自編)=Breitkopf
★エルガー夫妻の3回目の結婚記念日の贈物としで作曲された作品。原曲に忠実な編曲で,3楽章ともにPとSの手の交差がある。まとまりが良く,連弾でも極めて効果的な作品。特にPの両手は接近しがち。
[第1楽章] ホ短調 Allegro piacevole:Sの連打音(ヴィオラ)を多用した伴奏に乗せて,Pが憂いと優しさに満ちた旋律(ヴァイオリン)を弾く。口長調の流麗な旋律の中間部を持つ。(3′10″)[S3/P3]
[第2楽章] ハ長調 Larghetto:多声的な書法によるロマンティックな緩徐楽章。原曲の弦楽器による演奏の魅力に対抗するためには,特に「歌うタッチ」が必要。(4′30″)[S3/P3]
[第3楽章] 卜長調 Allegretto: 12/8拍子の快適で穏やかなリズムを備えた前半に,第1楽章の回想である後半が続く。(2′20″)[S3/P3]

オーンスタイン(1892~2002) Ornstein,Leo アメリカ

類い稀な長寿に恵まれたピアニスト,作曲家。ロシアで生れ(正確な生年は不詳),ペテルブルク音楽院でグラズノフに学ぶが,1907年に家族とともにニューヨークに移る。1911年のデビュー後はヴィルトゥオーソ・ピアニストとして自作のほか,同時代のラヴェルやストラヴィンスキーらの作品を演奏し,1920年代にはアメリカで最も有名な音楽家であったが,その後,急速に忘れ去られたものの,近年に再評価されつつある作曲家の一人。特に初期の作品は強烈な不協和音と野蛮なリズムが特徴で,当時の「未来派」音楽として知られた。現在,オーンスタインの作品は,著作権保侍者である御子息のSevero氏によってパブリック・ドメインとしての使用が許諾されているため,IMSLPで公開されている。また Leo Ornstein(http://poonhill.ipower.com/index.htm)のサイトでは,楽譜や録音のファイルも豊富に公開されており,「未開人の踊り Wild Men’Dance」や「飛行機に乗って自殺 Suicide in an Airplane」といった注目作品や,オーンスタイン自身による演奏を聴くこともできる。
道化師のワルツ
Valse buffon[1921]
連弾(オリジナル)= Poon Hill Press(スコア形式)
★マグローによれば「2つの即興曲 Op.95」の2曲目。不協和音を多用した当時の典型的な前衛風の作品で,軽快なワルツのリズムに乗せて,終始,無調的なメロディが展開される。リズムが流麗であるだけに,メロディが皮肉にも感じられる。響きは時に刺激的で輝かしく,時に不気味でもある。P,Sともにオクターヴ以上の和音が頻出し,不協和音の多用により多数の臨時記号が生じ,特にPの右手はそうした和音による動きが多く譜読みも大変。164小節以降の手の交差をはじめ,Pの左手とSの右手の接近箇所も多く,技術的にも非常に難しい。強弱記号はごくわずかで,14小節の序奏後の主部にはわずか2箇所の p があるのみだが、全体的に弱音で弾かれるべき作品ではなく、迫力に富み名技的。(4′45″)[S5/P5]

先生とロシア見物(全10曲)
Seeing Russia with teacher[1925]
連弾(オリジナル)= Poon Hill Press
★一方は固定されたポジションの5音で弾ける教育的な意図を持つ作品で,全曲が見開き2ページに収まっている。そしてその多くは,初歩の作品として異例なほど深刻で重苦しい雰囲気を持つ。オーンスタインはユダヤ系であり,恐らくポグロムをはじめとする数々のユダヤ人への迫害の記憶や知識,そして当時のロシアの民衆への視点が,単なる懐古趣味や観光旅行風にとどまらない,このユニークな作品を生んだのではなかろうか。
[1]古い村の教会 The old village church ハ短調 Moderato con moto: Sの伴奏の低音に多く使われるオスティナートや,後半の音階的に沈み込む動きが,曲想をいっそう暗く憂鬱なものにしている。(1′10″)[S2/P1]
[2]木の人形を寝かしつける Putting the wooden doll to sleep ト短調 Andante con moto:優しい手触りが感じられるかのよう。中間部は少し明るい。(1′00″)[S2/P1]
[3]そりすべり The sleighride 嬰ハ短調 Scherzando:P は6度を中心とする重音の練習曲さながらで,指示通りのテンポでは至難。(0′35″)[S1/P4]
[4]囚人たちのシベリアヘの出発 The prisoners leave for Siberia ハ短調 Grave:悲しみと嘆きは深く,心は鋭く痛む。(1′00″)[S1/P3]
[5]回転木馬 The carrousel 二長調 Vivo ma non troppo:明るい曲想で軽快なリズムの作品だが,pp で終わる様子は幻が消え去るかのよう。(0′55″)[S2/P1]
[6]暗い森の中の農民 The moujik in the dark woods ホ短調 Andantino espressivo assai:暗く沈んだ色調。(0′50″)[S1/P2]
[7]昔話を語る Tells an old tale ハ短調 Andantino espressivo:滑稽な話や懐かしい話ではなく,深い情感が込められた深刻な内容。(0′55″)[S2/P1]
[8]馬を駆るコサックたち The cossacks ride by へ長調 Allegro ritomico:輝かしく力強い。Pは素早い和音の移動のテクニックが必要。Sは楽譜の運指に従うと「弱い指」でトリル音型を弾くので,指の独立と強化の練習にもなる。[0′45″S1/P4]
[9]ドニエプル川のはしけ The barge on the Dniepel ホ長調 Moderato con moto:極めてロマンティック。中間部の転調が印象的。(1′00″)[S3/P1]
[10]村の休日 Holiday in the village 卜長調 Allegro:P は軽快で歯切れの良い旋律を奏する。Sは10度音程が届く左手が必要だが,右手の助力を工夫すれば小さな手でも演奏可能。(0′25″)[S2/P1]

オンスロー(1784~1853) Onslow,Georges フランス

イギリスからフランスに渡った貴族の父を持ち,ロンドンではピアノをクラーマーに師事した後,パリではレイハに音楽理論と作曲を学ぶ。歌劇や交響曲も残したが,室内楽,特に合わせて70曲ほどの「弦楽四重奏曲」や「弦楽五重奏曲」で知られるほか,ピアノを含む室内楽も多い。
ソナタ Op,7(3楽章)
Sonate[1810]
連弾(オリジナル)= Breitkopf
★初期ロマン派の新鮮で瑞々しい抒情と古典派の明快さを兼ね備えた魅力的なソナタ。PとSの掛合いや模倣の機会が極めて多く,両者ともに弾いて楽しめる作品。各主題や楽想の変化が大胆で,対照的な性格を持つのが特徴。
[第1楽章] ホ短調 Allegro espressivo:暗い情熱と甘い感傷に満ちた第1主題で始まるが,73小節目からSのソロで始まる対照的な性格の歌謡的な第2主題を持つ。楽章の大半で P, Sの少なくとも一方は1拍が3連符によって分割されているため,リズムが活気に溢れている。(9′40″)[S4/P4]
[第2楽章] ロマンス Romance ホ長調:古典派風の落ち着いた歌謡的な主題で始まるが,P と S の対話による切迫したリズムの非常にドラマチックな中間部を持つ。前半は楽節の反復が多い。P と S との対話はコーダにも現れる。(7′00")[S4/P4]
[第3楽章] ホ短調 Agitato:力強い連打和音が特徴的な第1主題と,舞曲風の軽快な第2主題を持つ。P,Sともに素早いアルペッジョの動きが多い。(7′45″)[S4/P4]

ソナタ Op.22(4楽章)
Sonate[1822]
連弾(オリジナル)= Breitkopf
★前作に比べて,規模だけでなく華麗な名技性,劇的な迫力を含めてすべての面で一層拡大・拡充されている。実に真摯な力作であり,発表当時,極めて人気が高かったことやオンスローが「フランスのベートーヴェン」と呼ばれていたのが納得できる傑作。同時期の他の傑作連弾ソナタのチェルニーの Op.10 やフンメルの Op.92と比べると,これら2曲の持つ派手な外面的効果には及ばないものの,チェルニーよりも深みと奥深さがあり,フンメルよりもロマン的傾向が強い。
[第1楽章] へ短調 Allegro moderato e patetico:第1主題はSによる半音階で上下する伴奏に乗せて,Pは(複)付点音符による悲愴な旋律を奏する。対照的な性格の第2主題は多くの装飾音に彩られた優美で可憐な性格。(11′45″)[S4/P4]
[第2楽章] メヌエット Minuetto へ短調 Moderato:哀調を帯びたテーマの旋律線は,S の下降に対して Pは上昇するため,秘めた悲しみは一層深まる。優美な変ニ長調のトリオを持つが,その中間部は瞑想的。(6′40″)[S3/P3]
[第3楽章] 変イ長調 Largo:荘重な歩みには瞑想的で深い精神性が漂う。意外なほど大胆な転調が多く,次の楽章に続く。(2′35″)[S2/P3]
[第4楽章] 終曲 Finale へ短調 Allegro espressivo:連打和音に乗った焦燥感を帯びた主題が活気に満ちて展開される。熱情と抒情,きらびやかなパッセージと歌謡的な旋律の対照とバランスが良く,また P と S の連携が緊密で,両者の役割の交替の機会も多い。(7′15″)[S4/P5]

カリヴォダ(1801~66)Kalliwoda,Johann Wenzel ボヘミア

プラハ音楽院でピクシスにヴァイオリンを師事。ヴァイオリニストとしてデビューし,劇場オーケストラでも演奏していたが,1821年にプラハを出て各地を演奏旅行中,フュルステンベルク公と出会い,ドナウエッシンゲンの宮廷楽長の職を得て,22年以降,約40年間その職にあった。当時,優れた作曲家,ヴァイオリニスト,ピアニストとして知られ,2曲のオペラ,7曲の交響曲のほか,多数の管弦楽曲,器楽曲,声楽曲を残す。編曲を含めた楽しい連弾作品も多いものの,それらは残念ながらほとんど知られることなく,「忘れられた作曲家」の一人。
- ■交響曲 第1番 Op.7(4楽章)
Première symphonie[1826刊] - ■ワルツ集 Op.27,169(全2曲)
Walzer[1858刊] - ■喜遊曲 Op.28
Divertissement[1831刊] - ■序曲 第2番 Op.44
Seconde Ouverture[1843頃刊] - ■アレグロ Op.162
Allegro[1851刊] - ■大ソナタ Op.135(4楽章)
Grande Sonate [1846刊] - ■喜遊曲 Op.203
Divertissement[1855刊] - ■祝典行進曲 Op.227-1
Festmarsch[1859刊?]
交響曲 第1番 Op.7(4楽章)
Première symphonie[1826刊]
連弾(C.Czerny編)=Peters
★原曲は1825年にプラハで初演され,好評を博したカリヴォダの出世作で,特に旋律が魅力的。真摯な内容でありながらも親しみやすく,PとSとの対話や掛合いの機会も多く,連弾作品としても極めて効果的。なお,チェルニーはカリヴォダの交響曲の第4番までを連弾用に編曲している。
[第1楽章] へ短調 Largo - Allegro:Sによる音階的な上昇,Pによる下降という対立するモティーフで,緊張をはらんで静かに始まり,激しい付点リズムが落ち着くと,主部に入ってPのソロによる第1主題が登場する。この主題は序奏部の冒頭の音階的な上昇と下降の動きに,リズム的に巧妙な工夫を加えたもので,当時,将来を嘱望された初期のカリヴォダの創意がうかがえる。歌謡的な第2主題が,対位法的な伴奏から,より器楽的な伴奏への移行も,そして再現部での微妙な変化も印象的。(7′15″)[S4/P4]
[第2楽章] 変ニ長調 Adagio : タイトルはないが,その際立ってチャーミングな旋律は「ロマンス」にふさわしい。4手とも「歌」に満ちて始まり,PとSが楽しく,そして親密な,またある時は劇的な対話を繰り広げる。(9′40")[S3/P3]
[第3楽章] メヌエット Menuetto へ短調 Allegro:主部はPとSの力強いカノン。強弱の変化が急激で,悲痛な曲想。変イ長調のトリオは優美。(4'00")[S2/P3]
[第4楽章] 終曲 Finale へ短調 Allegro molto:力強く,また悲愴な序奏部から第1主題と,表情豊かで穏やかな第2主題(4手ともに旋律を弾き弦楽合奏風)を持つ。長・短調間を頻繁に行き来し,第1主題のモティーフが重厚なカノンで登場する展開部を経て,第2主題の再現の後,第1主題が弱音で遠い思い出のように短く回想されると,あたかも現実に戻ったかのように,へ短調で疾走して終わる。(5′30″)[S3/P3]

ワルツ集 Op.27,169(全2曲)
Walzer[1858刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★どちらも快活で親しみやすく楽しい旋律が続く。Sはほとんど伴奏を担当し,反復部分が多くリズムもシンプルなだけに,気楽に弾いて楽しめる利点はある半面,冗長感は否めない。このペータース版は1959年ころまで出版されていたためか,ほかに格段に優れた作品があるにもかかわらず,A.ローリー(Rowley),ガンツェ&クシェ(Ganze,Kusche)の著作では,この作品のみが紹介されており,それがカリヴォダの連弾作品の正当な評価に繋がったかは疑問。
[1]ハ長調 Allegro con brio : 華やかで力強い序奏の後,32小節目から登場する上昇する旋律には心も弾む。途中,幾度も現れるファンファーレ風の音型も華やかさに彩りを添える。(10′00″)[S2/P3]
[2]ト長調 Vivace : 前作と同傾向だが,より多彩で変化に富むため,冗長感は少なく,大いに楽しんで弾ける。(7′15″)[S2/P3]

喜遊曲 Op.28
Divertissement[1831刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf
★へ長調,6/8拍子,Andante の歌謡的な序奏で始まる。これは26小節と短いが,伸びやかな旋律を持ち,PとSの対話,Sによる多様な伴奏型,短調への転調,と極めて充実した内容を備えている。そして3/4拍子,Allegretto の8 + 8小節の主題が登場し,5つの変奏とコーダヘと続く。変奏は実に華麗で快活,しかもSが主役となる第2変奏,ポロネーズの第3変奏,ニ短調の第4変奏といずれの変奏も変化に富み,両者の掛合いも実に楽しい。テンポの速まる快活なコーダで,絢爛豪華な終りを迎える。主題と変奏のほとんどが,前・後半とも反復される。(8′40″)[S4/P4]

序曲 第2番 Op.44
Seconde Ouverture[1843頃刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Peters
★へ長調 Allegro vivace :SがPの両手の間で旋律を弾く,歌謡的なPoco Adagio の序奏に続き,Sの両手とPの左手による軽快な伴奏の上に,Pの右手による陽気で躍動的な第1主題が奏される。対照的に第2主題は,まさに「歌のような」旋律。Sは伴奏中心で,いかにも原曲が管弦楽曲らしく,トレモロや連打和音が多い。深遠な精神性などとは無縁だが,シンプルで愉快な作品で,いずれの旋律も心地好く魅力的であり,リズムも快調に進行する。伴奏の音が厚いので,リズムや響きが重くならないように注意する必要がある。(8′30″)[S3/P3]

アレグロ Op.162
Allegro[1851刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★ニ長調 Allegro risvegliato: 「ワルツ Op.27」の4拍子版とも言える内容。精力的で楽しい期待感に満ちた序奏の後,まさに次から次へと快活で華やかな旋律が繰り出される。PとSとの掛合いや,Sが旋律を弾く機会も多く,楽しく弾ける連弾曲を作曲する手際の良さや,第2主題の再現部での転調やフレーズが反復される際の微細な変化といった誠実な姿勢に貫かれた職人業,生き生きとした心地好い旋律を産み出す能力には感心するが,楽しさと華やかさ満載の「娯楽的作品」としての長所が,同時に短所にも通じている。かなり長い作品にもかかわらず,全曲が同質な楽しさと華やかさに満ち過ぎていて,変化に乏しい印象を受ける。その理由の一端として,数多くの主要主題と副次的な主題に短調のものが無く,一時的に短調に転調しても,すぐに長調に戻る点と,新たな主題を導く経過句の部分で,わずか2小節間,Pがソロとなるだけで,それ以外の小節は常に4手が音を出し続けているために響きの変化が少ない点が挙げられる。(9′15″)[S4/P4]

大ソナタ Op.135(4楽章)
Grande Sonate[1846刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★「卜短調」という調性のためもあろうが,全曲が極めて激しい熱気に満ち,しかも切迫した焦燥感だけではなく,憧憬や敬虔さをも含む,深い感情の広がりを持つ。また豊かな幻想にも満ちた,充実した内容を持つロマン派の大ソナタ。交響曲の編曲を想わせるほど多彩な響きでありながら,極めてピアニスティックで華麗。PとSとの掛合いや,Sが旋律を弾く機会も多い。なお,この作品とOp.203,0p.227-2はウニヴェルザール版[1910刊]に所収されている。
[第1楽章] 卜短調 Allegro non troppo : 暗く激しい情熱と力強い迫力,推進感に満ちている。提示部の反復はなく,展開部では第1主題が十分に展開され,再現部では第2主題が先に登場し,緊迫したフガートによる第1主題へと続く。コーダでテンポを速めて燃えるように高まって終わる。パッセージ的な進行も多いが,第1,第2主題は密接に関連しており,構成的にも堅固でまとまりも良い。(9′00″)[S4/P4]
[第2楽章] スケルツォ Scherzo 卜短調 A11egro:対位法的な処理が目立つ楽章。PとSによる,精力的で活発な旋律のカノンで始まり,ト長調の軽妙で歌謡的な部分と交互に置かれる。2度目のカノンはS自身によるもので,Pによる新たな旋律を加えて展開される。(3′30″)[S3/P3]
[第3楽章] ゆるやかに荘厳に Adagio maestoso 変ホ長調 Tempo di marcia:Sによって弾き出され,すぐにPが参加する心地好い旋律は格調高く,宗数的な気高ささえ漂う。その後,次々に現れる旋律は変化に富み,雰囲気も多様で飽きさせないが,練習番号4からの印象的なカノンの主題は,シューマンによる同時代の作品でデュオ愛好者にはお馴染みの「ベダル・ピアノのための(カノン形式による)練習曲 Op.56」(1845作)の第6番のものと酷似していて,特に興味深い。次の楽章に続く。(5′00″)[S2/P3]
[第4楽章] 終曲 Finale 卜短調 Allegro assai:焦燥感に駆られて疾走するような第1主題と,息の長い伸びやかな旋律の第2主題を持つソナタ形式の楽章。ト短調のままテンポを速めて緊迫の度を増し,ピカルディ終止で終る。Sも伴奏ばかりでなく,左手で旋律を弾く箇所もある。(5′30″)[S4/P4]

喜遊曲 Op.203
Divertissement[1855刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★ト短調,6/8拍子,Allegro appasionato の極めて感傷的な舟歌風の序奏部で始まり,ト長調,3/4拍子,Allegretto grazioso のレントラー風の主題,4つの変奏,コーダが続く。第1,第2変奏は生き生きとして実にきらびやか。ホ短調の第3変奏はかなり長く,第4変奏は卜長調で軽快なポルカ風。「お気楽」な曲想とは裏腹に,コーダは徐々に音価が細かくなり,特にPは速いテンポでは技術的に難しい。華麗で楽しい作品には違いないが,同じフレーズの反復が多く,「彼の曲の多くは,流行の小ぎれいなだけのものを求める声に屈した,大衆音楽の部類」(「ニューグローヴ世界音楽大事典」より)という辛辣なコメントにもうなずける内容。(9′45″)[S3/P4]

祝典行進曲 Op.227-1
Festmarsch[1859刊?]
連弾(オリジナル)=?(Universal)
★ホ長調 Allegro con fuoco:全体的に音が厚く,楽しさいっぱいの明快で華やかな行進曲だが,決して武張った堅さ一辺倒ではなく,柔らかな弱音やロマンティックな和声の箇所も多く,なによりも数多くのPとSとの掛合いが楽しい。リズミカルなコーダ(Sに短いが心地好い対旋律が用意されている)を経て力強く終わる。前半に反復が多いものの作品そのものがコンパクトで,まとまりも良い。(4′40″)[S3/P3]

カルク=エーレルト Karg-Elert,Sigfrid(1877~1933)ドイツ

ライプツィヒ音楽院でヤダスゾーン,ライネッケ,タイヒミュラーらに師事。グリーグの出版社への推薦により作曲に専念し またレーガーの薦めでオルガン作品の創作に向かい,オルガンとハルモニウムのための作品が主要作品となった。ピアノ作品も数多く,初期のロマンティックな作風は,後にはドビュッシーやスクリャービンからの深い影響を示すようになるが,いずれも極めてピアニスティック。ピアノ・デュオのための作品は下記の1曲のみだが,ハルモニウムとピアノのためのデュオ作品も残されている。
ワルツ=カプリス集 Op.16(全3曲)
Walzer-Capricen[1899頃]
連弾(オリジナル)=Friedrich Hofmeister
★3曲ともリズムや強弱,曲想の変化や転調が大胆で気紛れな要素が強く,まさに「カプリス」のタイトルにふさわしい。音が厚く,後期ロマン派風の濃厚な抒情に満ちて,色彩感豊かでピアニスティック。S も伴奏を担当するだけでなく旋律を担う機会が多い。
[1]ホ長調 Ruhig,behaglich:曲集中,最もロマンティックで明朗な曲想で親しみやすい。アンコール・ピースにも好適。(2′15″)[S3/P3]
[2]変ロ長調 Mässig rasch,sehr straff im Rhytmus:リズムや旋律,そして当然曲想も「硬」と「軟」の大きな振幅の間を揺れ,動く。(2′20″)[S4/P4]
[3]嬰ハ短調一嬰ハ長調 Sehr lebendig und ungestüm:鬱屈した怒り,遥かな憧憬,絶望的な焦燥,甘美な思い出,陶酔的な激情といった多彩な要素が巧妙にまとめられたスケール豊かでピアニスティックな作品。P自身の手の交差が多く,最後はPとSが手を交差させて輝かしいクライマックスに突き進む。(3′10″)[S4/P4]

キール(1821~85)Kiel, Friedrich ドイツ

- ■フモレスケ集 Op.42(全4曲)
Humoresken[1865] - ■ワルツ集 Op.47(全10曲)
Walzer[1866] - ■レントラー集 1,2集 Op.66(全2曲)
Ländler Heft 1,2[1876刊] - ■若者のための10の連弾小品 1,2集 Op.74(全10曲)
Zehn vierhändige Klavierstücke für die Jugent Heft 1,2[1880刊]
フモレスケ集 Op.42(全4曲)
Humoresken[1865]
連弾(オリジナル)=出版情報:Walter Wollenweber (IMSLP無し)
★いかにもドイツ・ロマン派らしい親しみやすくロマンティックな曲想を持つ。連弾曲として極めて効果的に作曲され,1曲だけを取り出しても楽しめる上に,全4曲の構成も絶妙な変化と対照を示す。
[1] へ長調 Allegro ma non troppo:優雅で明朗な曲想だが,リズムが面白く,鶏の鳴き声のような旋律はユーモラス。Sはおもに伴奏を担当。(2′45″)[S2/P3]
[2] イ短調 Andante con moto : 全く感傷的ではなく,その歩みは着実で力強い。PとSのカノン風の動きも面白く,両者のリズム的な連携が緊密。(1′40″)[S3/P3]
[3] イ長調 Andante:みずみずしい田園詩のような,のどかな旋律を持つ愛らしい作品。PとSとによる10度離れた音程の響きが魅力的。(1′30″)[S3/P3]
[4] ニ短調 Allegro agitato:主部はリズミカルで軽快,活発な民俗舞曲風。変ロ長調の明朗な中間部は,雄大な山々にホルンの音が鳴り渡るかのよう。(3′15″)[S4/P4]

ワルツ集 Op.47(全10曲)
Walzer[1866]
連弾(オリジナル)=Simrock
★各曲が見開き1ページに収まる,短く変化に富むワルツ集。P.3.4,つまり1曲目のPと2曲目のSのパートが欠落しているのは,作品が決して難しくない上に極めて魅力的なだけに誠に残念。10曲目以外は前半や後半,あるいは両方の反復が多く,各曲は独立してはいるが,本来は全曲の連続演奏が意図されており,その10曲目の最後は正格終止したのち,ワルツ1・2を反復する指示がある。
[3]ホ長調 Allegretto:Sの子守歌のような優しいリズムの伴奏に乗って,穏やかに始まるが,途中には大きな感情の動きがある。(0′40″)[S1/P2]
[4]嬰ハ短調 Risoluto:激情に満ちてリズムや調性も頻繁に変化する。後半はPとSとの二重対位法。中間の反復の箇所で,SにPと同様の1拍分の小節(休符)を補う必要がある。次のワルツに続く。(1′25″)[S3/P3]
[5]ホ長調 Più animato:Pは簡素で短いフレーズを反復するが,その都度,微妙な変化が加えられている。PとSとで反復の小節の相違に注意。(0′40″)[S1/P2]
[6]卜長調 Allegro:Sは音が厚いが,軽快な運動性と輝かしさが特徴的。(1′10″)[S3/P3]
[7]ハ短調 Maestoso:スフォルツァートやアクセント記号が多用され,力感に満ちて進行する。過度に厚い和音やオクターヴの進行の連続ではないが,輝かしく豪快に響く。(1′05″)[S2/P2]
[8]Allegretto e animato:変イ長調で始まり変ニ長調で終わるが,途中の頻繁な転調が実に効果的。非常にロマンティック。(1′40″)[S2/P3]
[9]嬰へ短調 Moderato:憂いと悲しみに沈む。減七の和音が悲痛。(1′40″)[S1/P2]
[10]ニ長調:対位法的な書法による作品で,P・S間のカノンが見られる。静かで落ち着いた曲想で,強弱の変化が繊細に指示され,深い情緒に満ちている。(1′05″)[S2/P3]

レントラー集 1,2集 Op.66(全2曲)
Ländler Heft 1,2[1876刊]
連弾(オリジナル)=出版情報:Dohr(スコア形式)(IMSLP無し)
★楽譜の序文によるとヴィオラとピアノのための作品が原曲とのこと。そのためかPとSとの掛合いや役割の交替の機会が多い。1集と2集の様相はかなり異なっていて,1集は7曲の「レントラー」によって構成され,それらの1曲を取り出しても演奏可能だが,本来はまとめて演奏されるように意図されている。ピアニスティックな演奏効果も高く,曲想はロマンティックだが,単に素朴で気軽な民俗舞曲集ではなく,各曲の個性は際立っており,曲集としての内容も豊富でスケール豊かな作品に仕上がっている。1集は便宜上,各曲毎に解説を加えた。2集は1集と比べると各曲の独立性は弱く(拍子記号が最初のみにある),曲想も穏健な「レントラー」が多い。
<1集>
[1]嬰ハ短調 Allegro:深刻で悲劇的な物語風の序奏。「舞曲」が始まっても晴れやかな時間は短い。(1′30″)[S3/P3]
[2]イ長調 Allegretto:中・低音域の3つの旋律のカノンによる「歌」に満ちた作品。特に後半は回顧的でとてもロマンティック。(1′20″)[S2/P2]
[3]ホ長調 L'istesso tempo:3度重音で上昇する旋律。明るく軽快。(1′00″)[S3/P3]
[4]ハ長調 Moderato:Pによる旋律のリズムは軽快だが,pesante(重く)の指示がある。Sの右手による雄弁な対旋律が特徴。(1′15″)[S2/P2]
[5]へ短調 Agitato:行きつ戻りつする憂鬱なフレーズが反復される。手元の楽譜では,Sの右手は119小節(この曲のはじめ)~127小節の1拍目までト音譜表だが,へ音譜表の誤り。(0′40″)[S4/P4]
[6]変ニ長調 Allegretto:弱音主体の,いかにも「レントラー」風の可憐な作品。(1′30″)[S2/P2] [7]嬰ハ短調 Tempo I:前半は[1]の再現。嬰ハ短調に移調された[5]に続き, 次第にテンポを速めて大きく盛り上がり,決然と終わる。(1′10″)[S4/P4]<2集>
★二長調,Allegro risoluto の厚い和音を使った,堂々とした輝かしい序奏で始まり,多くは可憐な,またある時は哀愁を帯びた舞曲が続き,
間奏曲風の謎めいた舞曲の後に再び冒頭の序奏と舞曲が登場し,華やかに盛り上がって終わる。各部の反復が多く,
反復を除くと演奏時間はほぼ半分に短縮できる。(7′15″)[S4/P4]

若者のための10の連弾小品 1,2集 Op.74(全10曲)[1880刊]
Zehn vierhändige Klavierstücke für die Jugent Heft 1,2
連弾(オリジナル)= Bote & Bock
★全10曲ともP=生徒,S=先生と役割が決められており,Pは旋律を担当。1集(7曲)の大部分で, Pは両手がオクターヴ離れたユニゾンによるもので,1曲目は固定されたポジション群の5つの音による極めて易しい作品。 そのPの運指も3曲目までで,「連弾小品集」のタイトル通り,初心者向けの漸進的な教則本の性格を持つものではない。 2集(3曲)は中級程度の難度となり,完全にロマン派の性格的小品集。
[1]ハ長調 Poco Allegro:明朗な曲想でイ短調の中間部を持つ。前後の部分の微妙な変化が好ましい。(0′40″)[S1/P1]
[2]へ長調 Allegretto:流れるような旋律を持ち,短調への転調が作品の陰影を増している。頻繁なポジションの移動に対し,運指は親切とは言いがたい。(1′00″)[S1/P1]
[3]イ短調 Allegretto con moto:活動的な舞曲風。イ長調の滑らかな動きの中間部を持つ。運指は2箇所のみ。 Pは左手を軽快に弾くのが難しい。(2′05″)[S2/P2]
[4]カノン Canon ホ短調 Andante con moto:落ち着いた主題だが,リズムも旋律の動きも1集中では難しい作品。 (1′05″)[S2/PS]
[5]賛歌 Hymne ホ長調 Moderato:Pは終り近くに両手ともに和音奏がある。滑らかな旋律で響きは雄大。 (0′50″)[S2/P1]
[6]レントラー Ländler 卜長調:ロマン派の小品らしいロマンティックな風情がある。 中間部の転調が魅力的。(2′00″)[S2/P1]
[7]ロマンス Romanze ハ短調 Andante:濃厚な情緒をたたえた作品。この作品からPの両手はユニゾンの動きから離れ,独立して動く。特にSの音は厚く,両手の重音での進行が初心者には難しい。 (2′50″)[S3/P3]
[8]変ロ長調 Allegretto scherzando:躍動的で快活な民俗舞曲風。Pの左手の装飾音や手の交差, 中間部のリズムは初心者には難しい。(2′10″)[S3/P3]
[9]ト長調 Andante sostenuto:Pは両手とも和音の連続。祝祭的で堂々として輝かしい。(2′25″)[S3/P3]
[10]タランテッラ Tarantelle 卜短調 Presto:Pの両手はほとんどユニゾンの動きで一気呵成に疾走する。 Sの内声の下降する動きに特徴があり,幻想的な雰囲気に満ちた魅力に富む作品。(1′30″)[S3/P3]

クラーマー(1771~1858))Cramer, Johann Baptist ドイツ

マンハイムの著名な音楽家一族に生まれたが,わずか1歳で家族とともにロンドンに移住。パリに居を構えた時期もあったが生涯のほとんどをロンドンで過ごした。クレメンティに師事し,表情豊かなレガート奏法を得意とする大ピアニストとしてベートーヴェンからも高く評価された。作曲家としても8曲の「ピアノ協奏曲」や100曲以上の「ピアノ・ソナタ」を残したが,今日ではそれらは忘れ去られ,わずかにビューローが編集した「クラーマー・ビューロー練習曲」にその名をとどめている。
大ソナタ Op.33(3楽章)
Grande Sonate[1815刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★作品番号はマグロー(McGraw)による。クラーマーの連弾ソナタのマグロー評は,「無味乾燥で明確な表現法の個性に欠ける」とあるが,少なくともこの作品に関してはそれが正当な評価であろうか。第1,3楽章の「ピアノによるコロラトゥーラ」とでも呼びたいほどの,華やかで技巧的なパッセージ。第2楽章の,あくまで古典的な明晰さを保ちながらもコンチェルタンテな名技性を発揮する変奏は,クラーマーの魅力的な特質ではなかろうか。容易に楽譜に接することができるようになった今,一部なりとも試奏してぜひその真価を見極めて欲しい。
[第1楽章]ト長調 Allegro spiritoso:歓喜のあまり走り出すような快活な第1主題と落ち着いて歌謡的な第2主題を持つ。両主題ともに装飾音が多く,特にあちこちにちりばめられたターンは,極めて華麗で優美な演奏効果を高めている。4手ともに素早く軽快なタッチが要求される。展開部のはじめに反復記号があり,曲尾にこれと対応する記号がないが,版刻時のミスではなく当時の記譜習慣かも知れない。演奏時間はこの記号を補って前・後半ともに反復した場合で,一般的な提示部のみの反復では約10分。(14′30″)[S:5/P:5]
[第2楽章]アンダンテと変奏 Andante con variazioni ハ長調 Grazioso:愛らしい主題に8つの変奏が続く。第2変奏は互いにソロを弾き合い,第5変奏では主役と脇役の立場が交替する。第6変奏は「コラール」と題され完全な四声体で書かれているが,全変奏とも単純な伴奏型は見られず,見事な対位法的処理が光る。楽譜には疑問の箇所もあり,特に第5,6変奏あたりの反復記号は疑問。第8変奏のP,S同時のトレモロや第5変奏のSの響きには特に注意が必要。(9′45″)[S:5/P:5]
[第3楽章]ロンド Rondo 卜長調 Vivace:楽しさ一杯の主題やクープレはP,Sともに16分音符の連続とスタッカートが多く,名技的で洗練されている。音が厚く,オーケストラ的な部分もあり,響きの透明度に注意が必要。(5′45″)[S:5/P:5]

大二重奏曲 Op.24(3楽章)
Grand Duet[?]
2台ピアノ(オリジナル)= Clementi, Banger, Hyde, Collard,& Davis,(I・II分冊)
★2台のピアノ,またはピアノとハープのための作品。残念ながら現在(2014.7) IMSLPにはIIのパートしかないため演奏不可能だが。モーツァルトの「ソナタ K.448」よりずっと易しく,その可愛らしく優美な曲想は弾いて楽しめるばかりでなく,教材としても最適なだけに誠に惜しい。以前,ニューヨークのガーランド社からの復刻版,"The London Pianoforte School" シリーズのXIX巻に所収されたこともあったが,IMSLPのファイルの方がより鮮明。ただしミスが多く読みにくい楽譜のため,ガーランド版の注記は極めて貴重。
[第1楽章]変ホ長調 Allegro:前・後半とも反復の場合。[11′20″](I:3/II:3)
[第2楽章]変口長調 Larghetto:[4′45″](I:3/II:3)
[第3楽章]ロンド Rondo 変ホ長調 Allegretto:[7′10″]

クロンケ(1865~1938)Kronke,Emil ドイツ

ダンツィヒ(現ポーランドのグダニスク)で生れ,ライプツィヒではライネッケに,ドレスデンでキルヒナーに師事し,22歳以降はドレスデンに定住し,その地で亡くなっている。作品番号は200以上を数えるが,今日ではわずかなフルート作品が知られている程度。初歩的な連弾作品にも再評価されるべき優れた,そして楽しく親しみやすい作品がある。ショパンの作品を数多く校訂(シュタイングレーバー版)した。
小組曲 Op.73(全5曲)
Kleine Suite[1910刊]
2台ピアノ(オリジナル)=kistner
★いずれも親しみやすく,ロマンティックな曲想の初心者向きの楽しい小品集。2台のピアノ間での役割の交替や掛合いの機会も多いが,対旋律が魅力的,且つ効果的で全体が情緒豊かな「歌」に満ちており,特に2台のピアノの音が組合わさった豊かな響きを楽しむのに好適な作品。
[1]メロディ Melodie ト長調 Il tempo comodo,cantabile:タイトル通り,2台のピアノがおもに3度や6度離れた音程でロマンティックな旋律を弾くため,全体の響きは非常に豊麗となる。中間部のカノンも楽しい。(2′30″)[I:3/II:3]
[2]ガヴォット Gavotte ホ短調 Il tempo comodo,ma preciso:主部は極めてロマンティック。中間部は軽快なアーティキュレーションで進行する。(1′45″)[][I:3/II:3]
[3]高貴なワルツ Valse noble ハ長調 Grazioso:優美なワルツ。対旋律が効果的。(1′50″)[I:3/II:3]
[4]ゴンドラの船頭 Gondoliera ニ長調 Con moto lento:Iの主旋律もIIの対旋律も,いかにも「舟歌」らしく滑らかで穏やか。(2′25″)[I:3/II:3]
[5]スケルツォ=カプリス Scherzo - Caprice 変ロ長調 Vivace,leggiero:スタッカートが多く,軽快で快活。中間部とコーダでのリズム的な掛合いが実に楽しい。(1′40″)[I:3/II:3]

グヴィ Gouvy, Louis Théodore(1819~98) 仏

- ■ソナタ 第3番 Op.51(3楽章)
Troisieme Sonate[1868刊] - ■自作主題による変奏曲 Op.52
Varations sur un thème original[1869刊] - ■フランスの歌による変奏曲 Op.57
Variations sur un air Français[1876刊] - ■6つの小品 Op.59(全6曲)
Six morceaux( ? ) - ■リリブルレロ イギリスの歌による2台のピアノのための変奏曲 Op.62
Lilli Bullèro Variations pour deux pianos sur un air anglais[1879刊] - ■行進曲 Op.63
Marche[1875] - ■ソナタ Op.66(3楽章)
Sonate[1877] - ■幻想曲 Op.69(3楽章)
Phantasie[1882刊] - ■スケルツォ Op.77-1
Scherzo[1885刊] - ■喜遊曲 Op.78(2楽章)
Divertissement[1883] - ■気紛れ Op.83(全8曲)
Ghiribizzi[1890頃刊]
ソナタ 第3番 Op.51(3楽章)
Troisieme Sonate[1868刊]
連弾(オリジナル)=S.Richault
★全楽章とも軽快な運動性に溢れ,加えて両端楽章は健康的な力強さと明るさに満ちている。マックグロウ(McGraw)の「無味乾燥で教育的な様式 dry instructional style」の評には賛成できないが,「無味乾燥」が適訳ではないにしても,3曲の「ソナタ」中,濃厚なロマンや激しい感情のうねりとは最も縁が薄く,明晰な曲想はある意味,「古典的」でさえある。熟達した書法が駆使され,明るい音質と優れたテクニックを持つデュオにとっては,極めて効果的な作品と言える。ファイルの画質は良くないが,十分に解読可能。
[第1楽章]へ長調 Allegro con brio:終始,16分音符による軽快な動きに支配されており,この楽章が広く親しまれていたならば,「紡ぎ歌」というニックネームが付いたかも知れない。展開部での2つの主題の同時の使用と,PとSとの掛合いが面白い。Sは中~低音域での16分音符の動きが多いため,軽いタッチを要求されるが,音階的な素早い動きは少なく,トレモロが多いため技術的には難しくない。[8′30″](S:3/P:5)
[第2楽章]イ短調 Andantino scherzoso:ソフト・ペダルが踏み通され,弱音とスタッカート中心でひっそりと進行し,素晴らしく優美な宮廷舞曲の趣がある。前後の楽章との対照も際立ち,アンコール・ピースとしても実に効果的で印象的な楽章。両者ともに,特にSには軽いタッチが要求される。[3′00″](S:3/P:4)
[第3楽章]へ長調 Allegro risoluto:第1主題はスタッカートを多用したメカニカルな動きを持ち,第1楽章の主題と関連が深く,後にフガート風に扱われる第2主題は第2楽章の主題と関連が深い。Sにも旋律的な動きが多く登場する。明晰さと力強さに満ちた,華麗で名技的な楽章。[5′45″](S:4/P:5)

自作主題による変奏曲 Op.52
Varations sur un thème original[1869刊]
連弾(オリジナル)=S.Richault
★変ニ長調:主題と7つの変奏は,PとSとの連携が極めて緊密で,複雑・高度な性格変奏の連続ではないものの,各変奏は変化に富む。Sは伴奏を多く担当するが第4,7変奏では旋律的にもPと対等に活躍し,第6変奏では旋律的な主導権を持つ。Moderatoの主題はスタッカートが多用されたポツポツとした,しかし流れの穏やかな旋律を持ち,フレーズ構造は4+4+6+6小節のユニークなもの。以後,第1,2変奏では流麗さを増し,軽快で優美な第3,力強い第4,可憐な第5,Pの伴奏が華やかな第6変奏と続く。長大な第7変奏は同一のリズムパターンが偏執的に反復されて雄大に盛り上がり,Pの短いカデンツァを経て主題の雰囲気が回想されて静かに終わる。全体的に明快でピアニスティック。[11′30″](S4/P4)

フランスの歌による変奏曲 Op.57
Variations sur un air Français[1876刊]
連弾(オリジナル)=S.Richault
★ハ短調:前・後半それぞれ8小節(後半反復)による痛切な Moderato の主題は,四分音符の動きを中心とする落ち着いた歩みのもので,前半の途中での変ホ長調への転調が,主題に変化と深みを与える。第1変奏は和声がより複雑で豊かになり,伴奏の八分音符の動きにより流動性が増す。第2~7変奏は,偶数変奏のロマンティックな曲想が実に魅力的で,激烈,劇的で迫力に富む奇数変奏と見事な対照をなしている。ハ長調の第8変奏は軽快なリズムでさわやかに進行し,さまざまな長調を経て,既出の特徴的な伴奏型も織り込みながら,にぎやかに終わる。Sは伴奏を多く担うが,伴奏型は極めて多彩で,各変奏の調性やテンポが異なり,曲想の変化の振幅も大きい。[12′45″](S4/P4)

6つの小品 Op.59(全6曲)
Six morceaux( ? )
連弾(オリジナル)=Alphonse Leduc
★全曲では演奏時間30分以上という大作だが,各曲は実に変化に富むうえ,輝かしい「前奏曲」で始まり,特徴的な曲を挟んで,優美な「主題と変奏」を経て明快な「ポロネーズ」で終わる構成は聴く者を飽きさせない。いずれも親しみやすい曲想を備えているので,1曲だけを取り出しても効果的。
[1]前奏曲 Pélude ハ長調 Allegro di molto:S,Pが交互に弾く素早いアルペッジョによる和音の響きの乗せて,複付点リズムを持つ旋律が,輝かしく壮快に歌わい交わされる。[3′15″](S:4/P:4)
[2]カプリス Caprice ホ長調 Allegretto:ユーモラスに,気紛れに動き回る軽快な旋律によるPとSとの戯れそのもので,両者間のリズム的な連携,旋律的な掛合いが極めて緊密。3つの部分で構成され,調性を変えて反復される。[6′15″](S:3/P:4)
[3]行進曲 Marche ハ長調 Allegro moderato:精力的で活気に満ちた曲想。全体的に音が厚く,音域も広く使われているため,響きも豊か。Sは伴奏を多く担うが,ドラムのロールが楽しい。ヘ長調のP自身による二重唱の旋律的なトリオを持つ。[5′20″](S:4/P:4)
[4]ムーア風舞曲 Danse mauresque イ短調 Allegro con brio:異国趣味の急速で活発な舞曲で,頻出する前打音がその趣を強める。Pの旋律は,両手とも連打を含む三度重音の動きがあり,軽快に弾くには優れたテクニックが必要。反復を要する長大な盛り上がりを経て,豪快に終わる。[4′50″](S:4/P:5)
[5]主題と変奏 Thême varié イ長調 Andante com moto:平穏で優美な主題に3つの変奏が続き,コーダでは主題(イ長調から嬰ヘ長調への転調)と第1変奏が回想され,沈潜しつつ柔和な雰囲気で終わる。第2変奏までは曲想は次第に軽快,活発になり,Sは伴奏中心だが第3変奏ではSが旋律的な主役となる。3つの変奏は前・後半ともに反復され,全曲が優雅さに満ちている。[8′25″](S:3/P:3)
[6]ポロネーズ Polonaise ヘ長調 A11egro moderato:冒頭の軽快な主題は,PとSとのカノン風な掛合いによって,また別の主題はP自身による掛合いや模倣によって展開される。旋回するような音型が特徴的なトリオを含めて極めて明快で,華麗でピアニスティックなコーダを経て豪快に終わる。[5′00″](S:3/P:4)

リリブルレロ イギリスの歌による2台のピアノのための変奏曲 Op.62
Lilli Bullèro Variations pour deux pianos sur un air anglais[1879刊]
2台ピアノ(オリジナル)=N.Simrock(I・II分冊)
★変ト長調:古くはパーセルが「音楽のはしため 第2部」に「新しいアイルランドの調べ」として載せた旋律による。主題は基本的には前半の4小節と後半の8小節が,それぞれ反復されるもの。反復を利用して主題部ではIとIIが交互にソロで弾き,以降の変奏では互いの役割を交替する。そのためデュオとしての両者の音楽的,技術的な差異の発露の多寡が,誠に興味深い。反復が多いが,主題の親しみやすさ,各変奏の楽しさ,きらびやかな演奏効果によって冗長感は薄い。各変奏はテンポや拍子の変化が多く,特に18/8拍子の第2変奏での短いフレーズのカノン風の扱いや,第5変奏のリズム的な掛合いは弾いても聴いても実に楽しい。弾むようなリズムで快適に前進する第6変奏に続く,コーダに相当する華やかな第7変奏で終わる。[11′30″](I:4/II:4)

行進曲 Op.63
Marche[1875]
2台ピアノ(オリジナル)=Richault et Cie.
★変ホ長調 Allegro:生命力に満ち,明朗で華麗な行進曲。I・IIともにオクターヴが多用されるが,低音域の音は薄いので響きが明快で,旋律の心地好さと快適な前進感が際立つ。両者の急速なパッセージの掛合いが楽しく,技術的にはオクターヴや連打を含めて俊敏な動きが要求される。[8′10″](I:5/II:5)

ソナタ Op.66(3楽章)
Sonate[1877]
2台ピアノ(オリジナル)=Richault et Cie.
★2台のピアノが対等に扱われ,ピアニスティックでスケール豊かな大作。重厚で熱気に満ちた第1楽章,ロマンティックな歌謡性に富む第2楽章,名技的で華麗な第3楽章と各楽章が特徴的で変化に富み,それらの対照も効果的。
[第1楽章]二短調 Largo maestoso - Allegro:序奏は重々しい和音と鋭い付点リズムが特徴的な,「いわくありげ」な幻想曲風で,主部の主要主題のモティーフを含んでいる。主部は嵐のような激しさと推進力に満ち,2台のピアノの役割が頻繁に交替する。展開部の前と,最後に序奏部が短く回想され,この楽章に深みと変化を増している。後のサン=サーンスに代表されるフランス風の明快さも感じられる。[10′10″](I:4/II:4)
[第2楽章]変口長調 Adagio catabile:IIのソロにより,半音階的進行と転調が多用された歌謡性に富む旋律が弾き出され,Iのソロと交替する。中間部はややテンポが速まり,行進曲風の趣となる。2台のピアノ間のソロ,掛合い,協調が効果的に使われている。[7′00″](I:3/II:3)
[第3楽章]二長調 Allegro vivo:両者の短く軽快な応答の後に,無窮動的で華麗なパッセージが続く。第1楽章の特徴的なモティーフによる主題も登場し,両者が役割を交替しつつ活気に満ちて展開され,テンポを速めて大団円に向かって突進する。[4′55″](I:5/II:5)

幻想曲 Op.69(3楽章)
Phantasie[1882刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Breitkopf & Härtel(I・II分冊)
★各楽章それぞれが,熱気と緊迫感,濃厚な抒情,軽快な運動性と特徴がある上にそれらの変化がバランスが良くまとまった,ロマン派の大曲。管弦楽版もあるが,デュオ作品としてピアニスティックな演奏効果も高い。IとIIの役割の交替も頻繁で,どちらにもソロの部分もあり,デュオの楽しさを満喫できる。
[第1楽章]ト短調 Grave - Allegro molto moderato:2台のピアノの応答による劇的で重々しい序奏に,トレモロが多用されて緊張感と迫力に満ちた主部が続く。主部では幅広い和音による重厚な主題と,流麗でロマンティックな主題の対照が効果的。「力任せ」の印象を避けるために,両者の揃った息の長い cresc.が必要。[10′00″](I:4/II:4)
[第2楽章]変口長調 Adagio:短い楽章ながら,ソロ,協調,掛合いといったデュオならではの書法が駆使されている。転調も頻繁で,ロマンティックで歌謡性に富んだ旋律を弾き交わすが,スコア形式でないため,両者揃ってのバランスと「間」の取り方はより難しくなる。次の楽章に続く。[3′20″](I:3/II:3)
[第3楽章]ト短調 A11a breve:IIのトレモロに乗って,歯切れ良い主題がカノン風に畳み掛けるように登場し,活発に展開される。音階的な伴奏上の滑らかな主題との対照も実に効果的。対位法的で軽快な動きのコーダが素晴らしい。[6′20″](I:4/II:4)

スケルツォ Op.77-1
Scherzo[1885刊]
連弾(オリジナル)=Rieter-Biedermann
★ト短調 Allegro vivace:全2曲の「スケルツォとオーバード Op.77」の1曲目のみ,IMSLPにある。特にPが無窮動のように急速に動き回るヴィルトゥオーゾ的小品。繊細な銀線細工のような曲想は,PとSとのリズム的,旋律的な連携も極めて緊密で,両者ともに精密なタッチとリズム感を要求される。[5′30″](S:4/P:5)

喜遊曲 Op.78(2楽章)
Divertissement[1883]
2台ピアノ(オリジナル)=Kistner(I・II分冊)
★タイトルにもかかわらず,第1楽章は真摯な曲想の変奏曲。楽章間は複縦線で区切られているが,完全に終止しているため,1楽章のみの演奏も可能。第2楽章の軽快な運動性と明るさに溢れる曲想は,第1楽章と大きな対照をなす。
[第1楽章]ハ短調 Andante con moto:弱音中心で落ち着いた歩みの主題は8+12小節のもので,後半は反復される。4小節ずつIIとIが交替で弾き進み,最後の4小節は2人で弾く。突然の強音が刺激的な第1変奏,打ち寄せる波のような3連符の動きとトレモロが多用された第2変奏,更に速度を速めて後半の1小節毎のfとpの交替が一層激しさを増す第3変奏,一転してハ長調 Adagio となり,装飾音に彩られた繊細でロマンティックな旋律を互いにソロで弾き交わす第4変奏と続く。第5変奏は再びハ短調となり,幅広い和音,オクターヴの跳躍,上行する急速な音階,ffから p への移行が駆使される激烈な曲想。Iにはオクターヴ以上の和音も使われ,第6変奏では弱音主体で主題の雰囲気が回想される。後半の反復の省略により,4分ほど短縮可能。[11′40″](I:4/II:4)
[第2楽章]ハ短調 Lento‐ハ長調 Allegro vivace:11小節の序奏は次第に速度を増して主部に入る。主部の第1主題は,IとIIの細かいリズムの組合わせにより旋律が一体化されるもので,しかもその役割の交替も頻繁なため。表情豊かでスムーズな演奏のためには,両者の技術と音楽性はもとより,2台のピアノの音色や音量の一致が必要。短調の別の主題も登場して。終始,ピアニスティックで活気に満ちてきらびやかに展開され,速度を上げて明快に終わる。[5′00″](I:4/II:4)

気紛れ Op.83(全8曲)
Ghiribizzi[1890頃刊]
連弾(オリジナル)=Kistner
★全2巻12曲のうち,8曲目までが IMSLPにある。「気紛れ」のタイトルながら真摯で多彩な曲想のロマンティックな小品集。小品ながらもスケールの広がりとともに,グヴィの作風の驚くべき多様さと高度に洗練された書法を示し,全曲の楽譜が揃わずに誠に残念。これら8曲は少なくとも初心者向きではなく,音楽的にも技巧的にも中程度以上。
[1]前奏曲 Prélude 嬰へ短調 Lento:PとSによる,オクターブ離れたカノンで進行する。曲想は深刻だが,旋律の流れは 9/8拍子のリズムに乗った動的なもの。特にPの右手には重音でのレガート奏法が要求される。次の曲に続く。[2′40″](S:2/P:4)
[2]シチリアーノ Siciliano 嬰へ短調 Andantino:一種の変奏曲で,重層的な旋律を持つ主題部はイタリア風の豊かな歌謡性に溢れている。第1変奏は繊細なスタッカートが素晴らしく効果的で,第2変奏ではカノン風に展開される。[3′00″](S:3/P:3)
[3]舟歌 Barcarolle イ長調 Moderato:極めて甘くロマンティックな旋律は,転調が効果的。Sは伴奏中心。後半は単なる反復ではなく,微妙な変化が施され,また転調もなされて凝った造りとなっている。[3′20″](S:3/P:3)
[4]ブルレスカ Burlesca 二短調 Allegro vivace:短く歯切れ良い動機が,壮快でリズミカルな前進感を伴って展開される。PとSのリズム的な連携が緊密で,さまざまな調を巡る。特にPは両手が接近しがち。[3′40″](S:4/P:4)
[5]即興曲 Impromptu 二短調 Vivace:極めて技巧的な作品で,Pの右手は急速な16分音符の連続による複雑なパッセージを休みなく弾き続ける。Sの右手は対旋律を弾き,主旋律よりは易しいが,軽いタッチが要求される。[1′05″](S:3/P:5)
[6]ファンファーレ Fanfare へ長調 Adagio - A11egro con brio:目覚めるようにゆったりと始まる序奏に.PとSの二重奏による快活でリズミカルな主部が続く。そのさまは2群に分かれた金管群が,壮快に気分良く吹きまくるよう。明快で力強い曲想はI巻の終曲にふさわしく,指定のテンポは速く名技的。[4′20″](S:4/P:4)
[7]バガテル Bagatelle ト短調 Allrgro:急速なガヴォット風の曲想でキビキビとしたリズムで進行する。後楽節での反復される小節と,瞬間的だが短二度の衝突による刺激が諧謔的な雰囲気を高めている。[2′40″](S:3/P:3)
[8]ポルトガルの歌 Chanson portugaise へ長調 Allegretto:この曲集には珍しく,Pは旋律,Sは伴奏と役割が固定されている。民謡風の旋律は伸びやかで温かく,重音が多用される。伴奏はギターを模したリズミカルなもの。歌声が風に乗って消え去るように,ppで終わる。[2′55″](S:3/P:3)

グリエール(1874~1956)Leinhold Glière 露

12の小品 Op.48(全12曲)
12 Morceaux[1911刊]
連弾(オリジナル)=Jurgenson
★極めてロマンティックで親しみやすい連弾曲集。各曲は十分に個性的で変化に富み,全曲演奏(約18分)でも,また発表会やアンコールに1曲だけを取り上げても効果的。 88鍵をフルに使って4手による幅広い和音の轟音を響かせるタイプの曲ではなく,全曲中に pp は頻出しても ff は皆無。詩情に富み,繊細な旋律と和声,微妙な転調を備え,長調と短調の間を自在に移動する曲が多い。従来から広く親しまれている数多くの連弾曲集に,新たに加えられる価値と魅力を備えている。
[1]前奏曲 Prélude ロ長調 Moderato:ロマンティックな和声に彩られてゆったりと上昇する動きが,曲集への憧れに満ちた期待を高める。(2′00″)[S:2/P:3]
[2]ワルツ Valse イ長調 Moderato:シュネラー(逆モルデント)のある軽快な旋律をP,Sともに弾き合う。短調に傾きがちで,心地好く感傷的。(1′10″)[S:3/P:3]
[3]素描 Esquisse 二長調 Vivace:5拍子による軽妙なトッカータ風の曲想。(1′00″)[S:2/P:3]
[4]嘆き Plainte 変ホ短調 Andante:上昇しようとする旋律と下降するモティーフの,派手な動きはないが激しい葛藤。上昇は下降に勝てずに終わる。Sの左手以外の3手は接近しがち。(2′00″)[S:2/P:3]
[5]練習曲 Etude 変ロ長調 Allegro moderato:優美で軽快な動き。(1′00″)[S:3/P:3]
[6]羊飼いの歌 Chanson bergère へ長調 Allegretto:5音音階による旋律は中国風でもある。見開き1ページの短い作品ながら,広々とした草原をイメージさせる。(0′40″)[S:1/P:2]
[7]アラベスク Arabesque ハ長調 Animato:流れるような旋律とリズムを持つ音詩。転調してロ長調で終わる。(0′40″)[S:1/P:2]
[8]夢 En rève 変イ長調 Andante:Sの揺れるようなリズムの伴奏に乗せて,Pが優しい子守歌風の旋律を弾く。途中,切迫して大きく盛り上がる。2拍子ではなく4拍子。(2′10″)[S:3/P:3]
[9]マズルカ Mazurka ホ長調 Grazioso:P による旋律はシュネラーの多い運動性に満ちたもの。後半,PとSとのデュエットの箇所がいかにも連弾的。(1′20″)[S:3/P:3]
[10]フゲッタ Fughetta 二短調 Andantino:厳粛な主題による3声の小フーガ。(1′10″)[S:2/P:2]
[11]スケルツォ Scherzo 変イ長調 vivace:3部形式で,スタッカートを駆使して空高く飛び去るような軽快で華麗な主部を持つ。少しテンポを落とした中間部はPが歌謡的な旋律を弾く。(2′00″)[S:3/P:4]
[12]オリエンタル Orientale Allegro:Pがフリギア旋法による神秘的な旋律を静かに弾く。幻想的な曲想は極めて印象深い。(2′00″)[S:2/P:3]

グルリット(1820~1901)Gurlitt, Cornelius ドイツ

2つの性格的な小品(全2曲)
Zwei Characterstucke[1910刊?]
2台ピアノ(オリジナル)= Ries & Erler
★2曲とも親しみやすい。初心者向きの2台ピアノ作品。
[1]カプリッチョ Capriccio 卜短調 vivace:まったく性格が異なる3つのセクションから構成されており,短いフレーズや長いメロディの掛合いが楽しい。高度ではないが,さまざまなテクニックが要求され,教材にも発表会にもお薦めの作品。(3′25″)[I:3/II:3]
[2]ワルツ valse 嬰へ短調 Vivace non troppo : 感傷的な主題は魅力的だが,反復される部分が多く,やや冗長。(3′30″)[I:3/II:3]

ロンド ホ短調 Op.175-3
Rondo in E minor[1890]
2台ピアノ(オリジナル)=Schirmer(I・II分冊)
★ホ短調 Allegretto appassionato:初心者向きの2台ピアノ作品として有用な「3つのロンド」中の1曲で,1987年の同社のカタログには見当たらなくなっていたが,ここでの復活は嬉しい。グルリットの作品にしては珍しく激しい情熱に満ちた主題を持ち,長調の明朗なエピソードとの対照感も素晴らしい。2台のピアノ間の役割の交替も頻繁でリサイタルのアンコールとしても効果的な作品。レッスンには小節数を書き込んだ方が便利。(5′00″)[I:3/II:3]
ケーニヒスペルクで生れ,ベルリンのシュテルン音楽院でピアノをビューローから,作曲をウルリヒから学ぶ。後にはスイスのヴィンタートゥーアやチューリヒで活動したが結核のため若くして世を去った。出世作のオペラ「じゃじゃ馬馴らし」のほか,交響曲,ピアノ協奏曲,合唱曲,室内楽曲,ピアノ曲を残したがいずれも作品数は多くない。
ソナタ Op.17(3楽章)
Sonate[1865]
連弾(オリジナル)=Kistner & Siegel
★知名度こそ高くはないが,19世紀後半の連弾ソナタ中の屈指の傑作。真摯な作品ながらも全編に溢れる瑞々しいロマンと激しい熱気,巧妙な対位法的な書法,引き締まった構成が特徴で,厚い和音を使っていないにもかかわらず十分な迫力とピアニスティックな演奏効果を備えている。
[第1楽章] ト短調 Langsam-Sehr lebhaft:PとSのカノンによる,厳粛なバロック的な序奏で始まり,序奏の音型の一部を使った第1主題にごく自然に移り込む。特に熱烈な展開部は連弾としての多様な課題…同時にそれは魅力にも転じるが…に満ちている。(9′30″)[S4/P4]
[第2楽章] 変ホ長調 Mässig bewegt:PとSのデュエット。両者による「歌」は常にメロディアスでロマンティック。ゲッツの高度な対位法の確かさとメロディ・メーカーとしての資質が見事に発揮された楽章。(5′50″)[S3/P4]
[第3楽章] ト短調 Langsam - Graziös,und nicht zu rasch:葬送行進曲風の序奏の後に優美な,しかし哀感の漂うワルツの主部が続く。葬送行進曲が短く再現された後,テンポを速めて疾風のように終わる。(7′00″)[S4/P4]

ゴルトマルク(1830~1915)Gordmark, Károly(karl) ハンガリー

ケストヘイでユダヤ系の貧しい両親のもとで20人兄弟の一人として生れ,苦学しながらもウィーン音楽院でヨゼフ・ベームからヴァイオリンを学ぶ。優れたヴァイオリニストやピアノ教師としても活動したが,作曲家としても1860年の「弦楽四重奏曲 Op.8」が高く評価され,「交響曲 第1番 田舎の婚礼 Op.26」をはじめ,歌劇やヴァイオリン協奏曲,室内楽曲やピアノ作品も残している。作曲をおもに独学で学び続けたためか,独創的な個性を発揮する作品もある。当時のウィーンでの名声は高く,留学中のシべリウスの指導もしている。
- ■3つの小品 Op.12(全3曲)
Drei Stücke[1891刊] - ■舞曲集 Op.22
Tänze[1876刊] - ■春に 序曲 Op.36
Im Frähling Ouverture[1889] - ■スケルツォ Op.45
Scherzo[1894刊]
3つの小品 Op.12(全3曲)
連弾(オリジナル)=Dunkl
★「舞曲集 Op.22」が伝統的なロマン派作品なのに対し,この作品は作品番号が前(出版は後?)にもかかわらず,あくまでも後期ロマン派の作風ではあっても,平行和音の使用や陶酔的な盛り上がりに非凡な個性が強く感じられる作品。その含蓄に富み,味わい深い曲想は,間違いなく「埋もれた傑作」であり,復活の価値があるが,特に半音階的進行の多い3曲目は臨時記号の欠落が多く,慎重な補填が必要。3曲とも三部形式。IMSLP のファイルのタイトルは「3 Piano Pieces」。
[1]ニ長調 Allegretto:楽譜にタイトルはないが,マックグロー(McGraw)の記述には「牧歌(Pastrale)」とあり,確かに穏やかでデリケートな明るさを持つ前後の部分の曲想にはその形容がふさわしい。また物語風に多彩に展開されるかなり長い中間部は,濃厚な抒情に満ちて短調と長調が頻繁に交替し,陶酔的に盛り上がる。Sは単純な伴奏に止まらず,Pとの連携が極めて緊密に書かれている。(5′20″)[S:3/P:3]
[2]イ短調 Moderato:力強く重厚なポロネーズ。Sの伴奏中の半音階的な動きに憂鬱さが漂うが,それだけに音楽が奥深い。対照的に変イ長調~ホ長調のトリオは非常に滑らかで夢見るようにロマンティック。(2′30″)[S:3/P:3]
[3]イ長調 Moderato:穏やかに始まるが,曲想も,そして当然強弱の指示も急激に大きく変化し,さまざまな感情が大きくうねる。PとSとの情熱的なデュエットや,ちょっとしたSのソロも用意されている。波乱に満ちた内容のバラード風の作品だが,最後は浄化されて天上に昇るかのように静かに終わる。(6′30″)[S:3/P:3]

舞曲集 Op.22
Tänze[1876刊]
連弾(オリジナル)=Schott
★ファンファーレ風の短い序奏の後に,まずニ長調のゆるやかなテンポのワルツが置かれ,その後,少しテンポを上げて(Mässiges Walzertempo),調性も曲想もさまざまな,いずれも親しみやすいウィーン風のワルツが続く。この作品は華麗さよりも優雅さが際立ち,後半になるに連れて少しずつ盛り上がり,自然にテンポが速まる性格のワルツが配置されているが,最後は落ち着きを取り戻し,変ニ長調で消えるようにppで終わる。Sは伴奏中心だが,Pとの掛合いや対旋律を弾く機会もある。各ワルツの旋律の多くは特に連弾に適したしたもので,細やかな表情の変化を付けることによって,それらの魅力が一層引き立つ。IMSLP のファイルのタイトルは「Hungarian Dances」だが,何かの誤りであろう。(6′25″)[S:3/P:3]

春に 序曲 Op.36
Im Frähling Ouverture[1889]原曲 管弦楽曲
連弾(オリジナル)=Schott
★イ長調 Allegro moderato:全編,待ち望んだ春の到来への,はじけるような喜びと瑞々しい明るさに満ちており,さながら「春への賛歌」といった風情。この作品以外にも IMSLP には代表作の「交響曲 第1番 田舎の婚礼」をはじめ,「序曲 シャクンタラー Op.13」「序曲 サッフォー Op.44」等の管弦楽曲の作曲者自身による四手版があるが,連弾として最も効果的なのはこの作品であろう。Sも伴奏の音型を担うだけでなく,重要な旋律やPとの掛合いも用意され,木管楽器による「鳥の鳴き声」を弾く機会もある。両者とも音が厚く,一部には重複を避ける配慮もなされてはいるが,なお重複する箇所は残る。(11′00″)[S:4/P:5]

スケルツォ Op.45
Scherzo[1894刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Peters
★イ長調:半音階的にゆっくりと上昇した後に下降する序奏に,Allegro vivaceの軽快な運動性を持つ主部が続く。主部はPによる急速な連打和音(弦楽器)の下で,Sがホルンの力強い第1主題を弾いて始まり,カノンも含めて両者の掛合いが多く,弾いて楽しめる作品。両者ともに軽快な運動性が必要で,特にPは急速な連打和音が多い。原曲はウィーン楽友協会の作曲コンクールの応募作品として1850年代に作曲された。(8′00″)[S:4/P:4]

サン=サーンス(1835~1921) Saint-Saëns, Charles Camille フランス

- ■タランテッラ Op.6
Trentelle[1857] - ■ブルターニュの賛歌による3つの狂詩曲 Op.7(全3曲)
Trois rhapsodies sur des cantiques bretons[1866刊] - ■二重奏曲 Op.8 bis(全4曲)
Duos[1898刊] - ■カヴァティーナ 「6つの二重奏曲 Op.8」より
Cavatina from“6 Duos”[1858] - ■小二重奏曲 Op.11
Duettino[1861刊] - ■あなたの声にわが心は開く 「サムソンとダリラ Op.47」より
Mon cæur s'ouvre à ta voix from “Samson et Dalila”[1876] - ■バッカナール 「サムソンとダリラ Op.47」より
Bacchanale from“Samson et Dalila”[1876] - ■アルジェリア組曲 Op.60(全4曲)
Suite Algérienne[1880] - ■アルバムのページ Op.81
Feullet d’album [1887] - ■パソ・ドブレ Op.86
Pas redoublé[1887] - ■英雄的奇想曲 Op.106
Caprice héroique[1898] - ■連合国の行進曲 Op.155
Marche interalliée [1918] - ■アルジェの学生に捧げる行進曲 Op.163
Marche dédiée aux étudiants d'Alger[1921] - ■エティエンヌ・マルセル(全7曲)
Étienne Marcel[1878]
タランテッラ Op.6
Trentelle[1857]
2台ピアノ(自編)=Durand
★イ短調 Presto ma non troppo:原曲はオーケストラの伴奏に乗って,独奏楽器のフルートとクラリネットが縦横に活躍するが,サン=サーンスはそれらの3者を2台のピアノに巧妙に,そして公平に配分している。よりピアニスティックな音型への書き替えもあり,両者の掛合いの機会も多く,弾いて楽しめるばかりでなく,4小節のバッソ・オスティナート上に.I とII とが3度音程で旋律を奏する箇所は2人のバランスや歌い方を合わせる,デュオとしての高度な練習にも最適。(6′30″)[I:4/II:4]

ブルターニュの賛歌による3つの狂詩曲 Op.7(全3曲)
Trois rhapsodies sur des cantiques bretons[1866刊]原曲 オルガン曲
連弾(自編)=Durand
★「派手で華麗な作品の作曲家」,サン=サーンス。という偏ったイメージを見事に覆す,敬虔で真摯な雰囲気の中にも甘美な抒情を秘めた注目作。原曲にほぼ忠実な編曲だが,ピアニスティックな演奏効果を高めるために,作曲者ならではの様々な工夫が施されている。原曲は弟子のフォーレを伴ったブルターニュ旅行後に作曲され,フォーレに献呈されている。
[1]ホ長調 Allegretto:原曲の速度標語は Andantino con moto。滑らかに流れるような旋律をPとSとが交互に弾き合う。(3′00″)[S2/P3]
[2]ニ長調 Allegro moderato e pomposo:堂々とした和音奏による快活な主部に,主部のモティーフと関連ある主題を持つフガートが続く。中間部でのPの長いトリルに伴奏されて,Sが弾く無垢な旋律が印象的。(4′30″)[S3/P3]
[3]イ短調 Andantino:いかにも民謡風の素朴な旋律で始まり,ヘ長調,Allegretto の牧歌的で流麗な部分(他人の空似だが「主よ,人の望みの喜びよ」のオブリガートが一瞬,顔を出す),コラール編曲風に力強く盛り上がる部分を経て,再び素朴な旋律が再現された後,牧歌的な部分も再現されて静かに収まって終わる。(5′45″)[S3/P3]

二重奏曲 Op.8 bis(全4曲)
Duos[1898刊]原曲 ハルモニウムとピアノのための
2台ピアノ(自編)=E.Girod
★ハルモニウムとピアノのための「6つの二重奏曲」に基づく。原曲では,当然ながらハルモニウムのパート(I)にはいわゆる「ピアニスティックな」書法はまったく使われてなく,技術的には I のほうがずっと易しい。そのためIとピアノのパート(II)とを配分し直して難度を平均化するだけでなく,デュオとして面白く演奏できるように両者の役割を適当に交替させている。また2台のピアノでは,楽器の音質が同じなので特に音量のバランス上の工夫が必要となるため,単音をオクターヴや和音に変え,原曲の長い音価の音符をトレモロにしたり,また新たに旋律的な動きを加えている。そして原曲の全6曲を4曲とコンパクトにし,「終曲」の後半は新たに作り直され,献呈者も原曲とは異なり,プレイエル社の4代目社長でダブル・グランドピアノの発明者,ギュスターヴ・リヨンに献呈されている。安直な編曲作品ではまったくなく,サン=サーンスらしい力感と輝かしさに満ちたデュオ作品である。
[1]幻想曲とフーガ Fantasia et fuga ハ長調 Allegro moderato:急速な下降音階の連続が特徴的な,輝かしく壮大な幻想曲。フーガも活発で華麗そのもの。I・IIともにオクターヴが連続する箇所が多く,また急速な下降音階の練習曲と化すので,跳躍と,黒鍵が混じる時の運指が難しい。(8′00″)[I:4/II:4]
[2]コラール Choral ホ短調 Agitato:原曲ではIIの重音の連続が非常に難しいが, ここではそれらが2台のピアノに分配され,また音の省略もあるので,ずっと弾きやすい。ジグザグな動きの劇的なトッカータ風の部分と,敬虔なコラール(バッハの「わが魂は主をたたう BWV.10」に基づく)が交互に置かれ,両者が一体化されて盛り上がった後,静かに収まって終わる。(4′00″)[I:3/II:3]
[3]スケルツォ Scherzo 嬰へ短調 Presto:原曲との違いが最も少ないのは,それだけ原曲自体がピアニスティックな演奏効果が高いことを示していよう。2台のピアノが軽快な動きに終始しつつ,対話を繰り広げる。(3′40″)[I:4/II:4]
[4]終曲 Finale ハ長調 Allegro:ファンファーレ風の主題の付点リズムが取り去られ,原曲の 4/4 がリズムがシンプルになった主題にふさわしい 2/2拍子に変えられているが,輝かしく祝祭的な雰囲気は原曲に勝るとも劣らない。後半には1曲目のフーガ主題が堂々と登場し,2つの主題が同時に展開されて華麗で豪華なクライマックスを迎える。(4′40″)[I:4/II:4]

カヴァティーナ 「6つの二重奏曲 Op.8」より
Cavatina from“6 Duos”[1858]
2台ピアノ(オリジナル)=Jobert
★ニ長調 Andante con espressione,un poco adagio:ここで「オリジナル」としたのは,「6つの二重奏曲」は「ハーモニウムとピアノ」のための作品だが,楽譜には「または2台のピアノのための」と表記されているため。しかしこの表記は出版社が楽譜をより多く売るための常套的な手段であり,全6曲のうち,少なくとも「幻想曲とフーガ」や「終曲」は,そのままでは2台のピアノによる演奏では効果的とは言えない部分を多く含んでいる。サン=サーンス自身,この「表記」を知らなかった可能性もあるし,同意したにせよ,「しぶしぶ」であったろう。そうでなければ,改作の必要はなかったはずだ。“Op.8 bis”から除外されたこの「カヴァティーナ」は,IIの伴奏上の,Iによる極めて情緒豊かな小さな「アリア」。Iは1段譜に単音で書かれ,片手で(その気になれば1本の指でも)弾けるところが誠にユニークである。Iのパートをチェロで弾いても実に効果的な小品になりそうな旋律。(4′30″)[I:1/II:2]
*なお imslp にファイルが無いため,記載しなかった他の1曲「奇想曲 Capriccio」は,かわいらしくも微笑ましい曲想で,2台ピアノ用としても効果的なだけでなく,デュオのための高度な「エチュード」としても好適な事を記しておく。

小二重奏曲 Op.11
Duettino[1861刊]
連弾(オリジナル)=Hamelle
出版情報:ヤマハ(スコア形式) 「動物の謝肉祭他[連弾]」に所収
★卜長調 Andantino grazioso:9/8 拍子の優美で,しかも気品のある旋律を持つ部分に 3/8 拍子,Allegretto の舞曲風の快活でさわやかな味わいの部分が続く。「小二重奏曲」のタイトル通り,Sにも単なる伴奏というPの従属的な役割だけでなく,Pと共に音楽を創り上げるさまざまな要素が込められており,両者が連弾演奏の醍醐味が味わえる。ただし Hamelle版のP.13の1段目でいくつかの音符とスラーが乱れており,正しく弾くためには何らかの工夫が必要。(6′30″)[S:3/P:3]

あなたの声にわが心は開く 「サムソンとダリラ Op.47」より
Mon cæur s'ouvre à ta voix from “Samson et Dalila”[1876]
連弾(P.Dukas編)=Durand 原曲 歌劇
★変ニ長調 Andantino:古今のあらゆるオペラ中でも,最も有名で人気のある「アリア」の一曲。第2幕中で歌われ,デュカスによる連弾用編曲ではP.124~133 。 決して厚い音を使っていないにもかかわらず,非常に美しく響く,極めて効果的な優れた編曲で,ロマンティックで官能的な原曲の雰囲気を良く出している。(5′00″)[S:3/P:3]

バッカナール 「サムソンとダリラ Op.47」より
Bacchanale from“Samson et Dalila”[1876]
連弾(P.Dukas編)=Durand 原曲 歌劇
★ニ短調 Allegro moderato-ハ長調 Doppio più lento:官能的なエキゾチズムに溢れたバレエ音楽で,管弦楽曲としてもしばしば演奏される。ロマンティックな中間部での,原曲では管楽器によるPの高音の連打音は,過度に刺激的,機械的にならないように。またPは左手も急速な動きと歯切れの良いタッチを要求される。デュカスによる連弾用編曲ではP.165~185 。(6′00″)[S:4/P:5]

アルジェリア組曲 Op.60(全4曲)
Suite Algérienne[1880]
連弾(G.Fauré 編)=Durand 原曲 管弦楽曲
★「アルジェリア旅行の絵画的印象」の副題が示す通りの異国趣味が特徴的な作品。サン=サーンス自身による2台4手用編曲もあり,そちらは2台のピアノを「競争的」に扱っているが,フォーレによる連弾用編曲は,一方がソロで弾ける箇所でも,PとSに分担させた箇所も多く,より「共奏的」で「協奏的」。2台4手版の方が,より華麗でピアニスティックな箇所があるのも事実だが,連弾版も透明感のある響きが美しく,迫力や色彩感や演奏効果に全く不足はない。また,PとSとの重複する音を極めて丁寧に避けた編曲。
[1]前奏曲(アルジェに向かって) Prélude(En vue d'Alger) ハ長調 Molto allegro:期待感に満ちた曲想。Sもメロディを弾く機会やPとの手の交差もある。(3′30″)[S:3/P:3]
[2]ムーア風狂詩曲 Rapsodie mauresque ニ長調 Allegro non troppo:冒頭は,原曲のピッツィカートの旋律の弦楽器群による分担を,巧妙にPとSとに配分している。中間の急速なカノンの動きや,エキゾチックな舞曲風の後半を含め,全体的にリズムが難しい。(5′20″)[S:4/P:4]
[3]夕べの夢想(ブリダにて)Rèverie du soir (à Blidah) イ長調 Allegretto qua si andantino:魅力的な愛らしい旋律はほとんどPの担当。Sが旋律を弾く出番は,第1,2ヴァイオリンによるデュエットの箇所を,Pの手と接近させて弾く。(4′00″)[S:2/P:3]
[4]フランス軍隊行進曲 Marche militaire française ハ長調 Allegro giocoso:明るく活発な行進曲。いかにもフランス風の軽妙さがある。Sも旋律を弾く機会が多い。(4′20″)[S:3/P:3]

アルバムのページ Op.81
Feullet d’album [1887]
連弾(オリジナル)=Durand
★変ロ長調 Andantino quasi allegretto: はじめはP,次にSによって弾かれる優美な旋律が,Pの左手,次いで右手による穏やかに下降する音型と組み合わさって,柔らかに揺れるリズムを生み出す。幸福を感じつつも微妙に揺れ動く心理を,そのまま音にした趣がある。Sも旋律を担うが,中間部での(特に左手による)音階を重々しくならないように弾く必要がある。(3′00″)[S:2/P:3]

パソ・ドブレ Op.86
Pas redoublé[1887]
連弾(オリジナル)=Durand
★変ロ長調 Molto allegro:ファンファーレで始まる,一貫して快活そのものの舞曲。特にテンポの不安定さやリズムの「もたつき」は許されず,P・Sともに音階やスタッカートの多い旋律を弾くのには,軽快でしかも歯切れ良く確実なタッチが必要。終り近く,Pの両手に3度重音のトリルがあるが,「長い習練の末,これを克服すれば作品の深い精神的内容が表現できる」というタイプの作品ではまったくないので,(簡略化せずに弾こうとすれば)これらの3度重音のトリルが軽々と弾けなければ早く他の作品を探した方が良い。(4′20″)[S:4/P:5]

英雄的奇想曲 Op.106
Caprice héroique[1898]
連弾(オリジナル)=Durand
★調性もテンポも性格もさまざまに変わる各部分…精力的な部分,メランコリックな部分,優美だが気紛れな気分のワルツ…が続く。このワルツが展開されて情熱的に盛り上がると,緊迫感に満ちたファンファーレとなり,はじめの精力的な部分の一部も力強く顔を出す。そして真面目で古風なフガートに続くが,このフガートの見事な伏線が,分散オクターヴによる終結部の楽しさと華やかさを際立たせている。全体が極めてピアニスティックで演奏効果抜群な上,それぞれの各部分自体が素晴らしく,その対照と変化も実に面白い爽快な傑作。 (9′15″)[I:5/II:5]

連合国の行進曲 Op.155
Marche interalliée [1918]
連弾(オリジナル)=Durand
★ヘ長調 Allegro:楽しい旋律が次から次に登場する快活な行進曲。旋律は主にPが担うが,Sもバスの動きや対旋律が面白いだけでなく,終り近くで弾く堂々とした旋律がカノン風に処理されていく所などは,さすがに大作曲家の片鱗がうかがえる。 P・Sともに連打和音を軽快に弾くテクニックが必要。(4′45″)[S:4/P:4]

アルジェの学生に捧げる行進曲 Op.163
Marche dédiée aux étudiants d'Alger[1921]
連弾(オリジナル)=Durand
★変ホ長調 Allegro:合唱(随意)付きの軍隊バンド版もあり,そちらをオリジナルとする資料もある。反復音の多い歯切れの良い旋律を持つ,非常に快活な行進曲。Pは大部分が両手が1オクターヴ離れたユニゾンで弾き,極めてにぎやか。楽器も実に良く響くように書かれている。合唱部分の反復が転調されていたり,装飾に変化が加えられている点にサン=サーンスの職人的技巧が示されている。(4′30″)[S:3/P:4]

エティエンヌ・マルセル(全7曲)
Étienne Marcel[1878]
2台ピアノ(C.Debussy編)=Durand(I・II分冊) 原曲 歌劇
★原曲は第3幕のバレエ音楽。1890年,デュランから編曲を依頼されたドビュッシーにとって,生活費のためのこの仕事は意に沿わないものであったが,編曲そのものは響きが極めて美しく,2台のピアノ間での役割の交替が多く,IもIIも楽しく弾ける。特に3~5曲の旋律は魅力的。
[1]序奏 lntroduction ト長調 Animato:陽気で元気の良い行進曲風。特にIの右手とIIの左手にはオクターヴによる動きが多い。(1′00″)[I:2/II:2]
[2]大学生と娼婦の入場 Entrée des ecoliers et des ribaudes:変ホ長調 Allegro non troppo:快活な旋律をIとIIが交互に弾く。多くのトリル,トレモロ,急速な音階によって華やかに彩られる。(1′55″)[I:3/II:3]
[3]戦士のミュゼット Musette guerriére 変ロ長調 Allegro moderato:タイトルからは全く予想外の繊細で柔和な曲想。落ち着いたリズムの優美な主旋律はIとIIが交互に弾く。主旋律ではない方も,やはり優美な舞曲風。(2′00″)[I:3/II:3]
[4]パヴァーヌ Pavane ニ短調 Allegro moderato:優しく典雅な主題が軽快な伴奏上で歌われ,反復の際の変化が印象的。IIは伴奏中心だが,音階的に下降する対旋律が効果的。(1′50″)[I:2/II:3]
[5]ワルツ Valse ト長調 Allegro molto:短い序奏で始まる,親しみやすく華麗なワルツ。ドビュッシーの編曲の腕の冴えが見事に発揮された編曲で,薄い書法ながらもピアニスティックで充実した響きを持ち,IIも魅力的な旋律を担当する。各ワルツも変化に富み,ロマンティック。ほとんど知られていないのが誠に惜しい楽しい作品。(4′00″)[I:3/II:3]
[6]ジプシーの男女の入場 Entrée des Bohémiens et des Bohémiennes イ長調 Allegro Maestoso:IとIIがユニゾンで奏する力強い旋律が序奏風に置かれ,嬰へ短調の短いトリルを交互に弾き合う,異国風な雰囲気の優美な3拍子の舞曲に続き,再びイ長調,Molto allegro に転じてスタッカートを多用した飛び跳ねるような舞曲を経て,快活に終わる。(6′00″)[I:4/II:4]
[7]終曲 Final ト短調 Allegro:終始,前進的なリズムで躍動的に展開され,次第にテンポを速めて盛り上がりが最高潮に達すると,1曲目が晴れやかに回想される。(2′40″)[I:4/II:4]

- シャミナード Chaminade, Cécile

- シャルヴェンカ Scharwenka, Xaver

- シャルヴェンカ Scharwenka, Philipp

- シュット Schütt, Edouard

- シュミット Schmitt, Florent

- シンディング Sinding,Christian


シャミナード Chaminade, Cécile(1857~1944)フランス

- ■間奏曲 Op.36-1
Intermède[1887刊] - ■コンチェルトシュテュック Op.40
Concertstück[1888刊] - ■ロマンティックな小品集 Op.55(全6曲)
Pièces romantiques[1890頃刊] - ■朝 Op.79-1
Le matin[1895刊]
間奏曲 Op.36
Intermède[1887刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Enoch(I・II分冊)
★変ロ長調 A11egretto:主部は極めてロマンティックで軽快な洒落たワルツ。2台のピアノは旋律と伴奏を分担し,役割の交替もある。嵐のように激しい中間部を持つが,弱音に収まってトリルとアルペッジョに彩られて終わる。シャミナード自身による連弾版もある。なお,0p.36-2は「シンバルの踊り Pas de cymbales」。(5′00″)[I:4/II:4]

コンチェルトシュテュック Op.40
Concertstück[1888刊]
2台ピアノ(自編)=Enoch(I・II分冊)
★シャミナードによる重量感に満ちた大作の一つで,代表作の1曲でもあり,自身でも頻繁にソロ・パートを演奏したほか,2台ピアノ版も演奏している。単楽章の短い作品ながら,ソロ・ピアノ(I)による鍵盤上を駆け巡る急速な音階や名技的なアルペッジョ,華やかなトレモロがいかにもコンポーザー・ピアニストの作品らしく,ロマンティックな甘美さとともにエキゾチックな雰囲気を特徴とする。Iにも一部にオーケストラの音が加えられ,単にソロ・パートの練習用以上にピアノ・デュオが意識されており,IIもピアニスティックな演奏効果を発揮する。(13′00″)[I:5/II:5]

ロマンティックな小品集 Op.55(全6曲)
Pièces romantiques[1890頃刊]
連弾(オリジナル)=Enoch, 出版情報:カワイ(スコア形式)
★1曲目のタイトルはイタリア語,「秋のセレナード」はスペイン風であり,シャミナードのイメージ上での「連弾による世界旅行」が感じられる小品集。キャッチーな各曲のタイトル。親しみやすく生き生きとして多彩な曲想,ピアニスティックな演奏効果は一世を風靡したシャミナードのピアノ作品群の特質を備えている。
[1]春 Primavera へ長調 A11egretto:暖かくなって花々が咲き乱れ,あたりには甘い香りが漂う季節感が音によって見事に活写されている。(2′50″)[S:3/P:3]
[2]駕籠(かご) La chaise à porteurs イ短調 A11egretto:「全曲ソフト・ペダルを踏み続けて」の指示があり,Sは伴奏に徹するが,その和声もPによる旋律も極めて繊細で洗練された作品。「駕籠」は日本独自の乗り物ではなく,曲想にも日本的なものは何もなく,むしろフランスのクラヴサン音楽の伝統を感じさせる。しかしローカルな音楽文化が伝わり難かった19世紀から20世紀初頭のジャポニスムによる音楽作品に,日本的情緒を求めることもまた困難であり,シャミナードがジャポニスムを意識したかどうかは不明。(1′50″)[S:3/P:3]
[3]アラビアの牧歌 ldylle arabe へ長調 Mouvt modédé valse:明朗で親しみやすい旋律と,いかにも異国風な鈴を模したような音との対比が面白い。Sの左手には(アルペッジョの指示があるが)10度音程の和音が頻出する。(2′45″)[S:3/P:2]
[4]秋のセレナード Sérénade d'automne ニ長調 Andantino:中間部は旋律も,Sによるギターを模した伴奏もスペイン風。主部は伴奏が重層的に書かれており,バランスが難しい。(2′35″)[S:3/P:3]
[5]ヒンドゥ教徒の踊り Danse hindoue イ短調 A11egro tempo giusto:音楽の主導権はSにあり,Pは一貫してにぎやかな装飾を担当。インパクトのある激烈な舞曲。(2′25″)[S:3/P:3]
[6]リゴードン Rigaudon ハ長調 A11egro:宮廷舞曲らしい優美さと落ち着き,そして威厳を備えている。伴奏の音が厚く,すっきりとした響きのためには特にバランスに注意が必要。(2′20″)[S:3/P:3]

朝 Op.79-1
Le matin[1895刊]原曲 管弦楽曲
2台ピアノ(自編)=Enoch
★卜長調 A11egro:I が軽快な連打和音に乗せてさわやかな旋律を奏する間に,IIがシンプルだが実に効果的な合いの手を入れる抒情的な部分と,力強い行進曲風の部分が交互に置かれている。極めてピアニスティックで,その清々しさはコンサートのオープニングにもふさわしい。「管弦楽のための2つの小品 Deux pièces pour orchestre」の1曲目で,もう1曲は「晩 Le soir」。シトロン(M. J. Citron)によればスコアは未出版で,シャミナード自身,2台ピアノ版をしばしば演奏した。(4′10″)[I:4/II:4]

シャルヴェンカ Scharwenka, Xaver(1850~1924)ポーランド

兄フィリップと同じくザムターで生れ,15歳でベルリンのクラク音楽アカデミーに入学してクラクに学び,後には兄とともにアカデミーのスタッフに迎えられる。 1881年に兄弟でベルリンにシャルベンカ音楽院を設立。 1891年にはニューヨークにも分校を設け,アメリカやカナダでヴィルトゥオーソ・ピアニストとして活躍した。作曲家としては4曲のピアノ協奏曲のほか,歌劇や室内楽曲,そして多数のピアノ作品を残した。なかでも「ポーランド舞曲 Op.3-1」は当時の大ヒット作品。連弾作品も多いが,今日ではほとんど演奏されない。
- ■北国風 Op.21-1
Nordisches[1875刊] - ■舞踏組曲 Op.41(全4曲)
Suite de danses [1877刊] - ■ワルツ集 Op.44(全2曲)
Walzer[1879刊]
北国風 Op.21-1
Nordisches[1875刊]
連弾(オリジナル)=Carl Simon
★へ長調 Allegro moderato:全2曲のうち,imslpにあるのは1曲目のみ。主部は3/4拍子で,力強く堂々とした序奏風の部分に続き,「イングリッドの歌」(ノルウェー民謡「そして狐は大きなカバの木の根元に横たわる」)の快活な旋律が歌われる。テンポが速まり2/4拍子の軽快な民俗舞曲風の中間部を挟んで主部が反復されるが,静かに収まって終わる。全体的に音が多いが,厚い響きと薄い響きの対比や,PとSとの掛合いや模倣も頻繁で,連弾作品として熟達した書法で書かれている。各部の反復が多,冗長感を避けるための変化の工夫が必要。(4′40″)[S3/P3]

舞踏組曲 Op.41(全4曲)
Suite de danses [1877刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★全体的に音が厚いが,Sも伴奏の役割だけでなく,旋律や対旋律を弾く機会が極めて多い。またPとSとの対話や掛合いも多く,熟達した連弾書法で書かれている。1曲目のモティーフが各所で使われ,組曲としての統一感を高めている。
[1]行進曲風 Alla Marcia ハ長調:2つのトリオに相当する部分を備えた,快活で堂々とした行進曲だが,そのリズムは実用的な「行進」のための単調なものではなく,極めて多彩。第1のトリオは「スウェーデンの歌」と題された,短調だが雄々しい旋律を持つ。第2のトリオはトリルと増六度の和音が特徴的。第1のトリオの後,短い主部の行進曲を経て,第2のトリオ,転調された第1のトリオ,主部の行進曲と続き,息の長いcresc.を伴って大きく盛り上がって終わる。4手ともに厚い和音を弾く豪快な響きの箇所も多く,壮麗で輝かしい。(6′30″)[S4/P4]
[2]メヌエット Menuetto 変イ長調 Moderato grazioso:Pによる主部の旋律は優雅な上に極めて伸びやかなもの。Sによる伴奏は音が多いだけに,多声的で「歌」に富み,和声も豊か。トリオに1曲目の第2のトリオの性格が顔を出す。(4′15″)[S3/P4]
[3]ガヴォット Gavotte へ長調:曲集中,最も短く技術的にも易しいが,軽いスタッカートで演奏される旋律は,かわいらしい上に典雅な趣がある。(2′20″)[S2/P3]
[4]ボレロ Bolero イ短調:1曲目のモティーフを使った主題による,リズミカルで軽快な舞曲。イ長調のトリオで,3拍目が4つの16分音符群のリズムやトリルになるのも1曲目の第2のトリオと関連がある。イ短調で力強く終わる。(4′20″)[S3/P4]

ワルツ集 Op.44(全2曲)
Walzer[1879刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★華やかで親しみやすい。Sはほとんど伴奏に徹しているが,伴奏型は極めて多彩な上,効果的な対旋律も弾く。
[1]二長調 Con spirito,卜長調,変ホ長調 Un poco meno mosso,ト短調 Più Allegro,ニ長調 Allegro come primo の5曲のワルツが続く作品。1曲ずつ独立して書かれているが,続けて演奏されるよう意図されている。調とテンポだけでなく,当然各ワルツの気分も変わり,最後ははじめのワルツに戻って堂々と華やかに終わる。(7′40″)[S3/P3]
[2]変ホ長調 Allegro comodo :1曲ずつ独立して書かれてはいないが,次々にワルツが流れて行き,コーダで初めのワルツに戻って堂々と華やかに終わる。1曲目よりも各曲の雰囲気の変化が大きく多彩で,よりピアニスティック。(8′00″)[S3/P3]

シャルヴェンカ Scharwenka, Philipp(1847~1917)ポーランド

ポズナン近郊のザムター(現シャモトゥウィ)で生れ,ベルリンのクラク音楽アカデミーでR.ヴュエルストとH.ドルンに学び,後にアカデミーの理論と作曲の教員となる。l881年,弟クサヴァーとともにベルリンにシャルヴェンカ音楽院を設立。1891年,弟とともにアメリカに渡るが翌年には帰国してシャルヴェンカ音楽院で教職を続けた。演奏家としてよりも作曲家,教師として活躍し,2曲の交響曲や管弦楽曲,室内楽曲のほかに,3曲の「ソナタ」含むピアノ作品も多数残した。
- ■ポーランドの舞曲の旋律集 Op.38 第1,2集(全6曲)
Polnische Tanzweisen Heft 1,2[1882刊] - ■歌と舞曲の旋律集 Op.54(全6曲)
Lieder und Tanzweisen [1884刊] - ■春の輪舞 Op.75-2
Lenzreigen[1887刊] - ■3つのスケルツォ Op.91(全3曲)
Drei Scherzi [1893刊]
ポーランドの舞曲の旋律集 Op.38 第1,2集(全6曲)
Polnische Tanzweisen Heft 1,2[1882刊]
連弾(オリジナル)=Praeger & Meier
★さまざまな曲想のマズルカ集。そして各曲の曲想自体も単調ではなく,対照的な中間部を持つ。Sは伴奏中心。*現在(2012.8),IMSLP には第2集の3曲のファイルのみだが,全6曲について記す。
[1]ホ長調 Vivace:飛び跳ねるようなリズムの,軽快で快活な主部と憂いに満ちた中間部の対照が魅力。Sは伴奏中心。各フレーズの反復が多い。(4′20″)[S2/P3]
[2]変ロ長調 Comodo:Sのソロによってクヤヴィアクの性格を持つ旋律が静かに弾き始められ,ポリフォニックに展開される。歯切れの良い幅広い和音による伴奏を伴って,さながら大広間での威厳と壮大さに満ちた大舞踏会の様相を呈する。旋法的な,また平行和音の動きが個性的。(4′50″)[S2/P3]
[3]変ロ短調 Moderato:感傷的で繊細なクヤヴィアク。長調の部分が,短調の主題の悲哀をより深く感じさせる。変ロ長調の中間部は装飾音の多い旋律を持つ活発なマズル風。親しみやすい曲想で,技術的にも弾きやすく,この曲集を弾き始めるのに適している。(4′15″)[S2/P3]
[4]ト短調 Allegretto:短調の主題の力強く悲愴な雰囲気に対し,長調の主題は付点リズムにより軽快で楽しそう。卜長調の中間部は一方の3連符と他方のトリルの組み合わせが,優美で繊細な軽やかさを出している。(3′10″)[S3/P3]
[5]ホ短調 Non troppo allegro:主部は痛切な悲哀に満ち溢れている。ホ長調の中間部は英雄的で壮大。(3′00″)[S3/P3]
[6]イ長調 Vivo:主部は付点リズムによる明快で溌刺としたマズル。中間部の細かい音型の反復はオベレク風。終曲にふさわしく鍵盤の幅を広く使って壮大に盛り上がるが,同一フレーズの反復が極めて多く,冗長さを感じさせずにスケールの大きさを出すのが演奏のポイント。(4′30″)[S3/P3] 
歌と舞曲の旋律集 Op.54(全6曲)
Lieder und Tanzweisen [1884刊]
連弾(オリジナル)=Carl Simon
★全6曲とも親しみやすい上,PとSとの緊密な連携を備え,各曲の変化と対照も面白く,ほとんど知られていない作品だが,再評価されるべき作品。
[1]行進歌 Marschlied ホ長調 Lebhaft und Kräftig:P,Sともに音が多く,響きも厚く,旋律も力強い。ドラムのロール音を模した3音のシュライファーが効果的。トリオの雰囲気が主部と大きく違わないため,前半を楽譜通りに反復するといかにも冗長。(6′20″)[S3/P4]
[2]少女たちの輪舞 Mädchenreigen 変ロ長調 Mässig geschwind:軽快で優美な3拍子の舞曲。(2′00″)[S3/P3]
[3]愛の歌 Liebeslied へ短調 Langsam,doch nicht schleppend:「哀歌の」とある通り,暗く深刻な雰囲気。その曲想は別にして,連弾曲としてPとSとの対話が大いに楽しめる作品。(3′30″)[S3/P3]
[4]ポーランドの舞曲 Polnischer Tanz 嬰ハ短調 Sehr bewegt:活発なマズルカ。途中,PとSとで旋律がカノンになる箇所が特徴的。(2′20″)[S3/P3]
[5]民謡風の歌 Lied im volkston 変ホ長調 Langsam,mit inniger Empfindung:情緒に満ちて,ゆったりと落ち着いた旋律は「親密な気分で」の指示にふさわしい。技術的には難しくないが,極めて対位法的に書かれているため,旋律を十分に歌いながらの両者の打鍵の一致,バランスの取り方,デュナーミクの合致,ペダル使用の問題など連弾特有の課題に満ちている。連弾の学習用として特に有用なだけでなく,真の連弾の醍醐味が味わえる作品。(3′30″)[S3/P3]
[6]メヌエット Menuett ニ長調 Mässig bewegt, mit Grazie:Pによる,スタッカートと前打音の多い旋律は実に軽快。中間部はP,Sともに音が多いが,やはり軽快に弾く必要がある。(3′00″)[S3/P4] 
春の輪舞 Op.75-2
Lenzreigen[1887刊]
連弾(オリジナル)=Hainauer
★イ長調 Moderato con grazia:「5つの舞曲の情景 Fünf Tanzscenen op.75」の2曲目。典型的なドイツ・ロマン派風の性格的小品。主部は穏やかで温かな雰囲気に満ち,軽快な装飾音に彩られた旋律は,繊細なアーティキュレーションと優美なリズムを持つ。SとPとのリズミカルな掛合いが楽しい中間部の後,ほとんど完全に主部が反復され,ごく短いコーダで可憐に終わる。曲集中の他の作品がないのは残念だが,ハイナウアー社の美麗な表紙も楽しめる。(4′20″)[S2/P2] 
3つのスケルツォ Op.91(全3曲)
Drei Scherzi [1893刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf&H?rtel
★3曲とも「スケルツォ」というタイトルながら,それぞれの曲想は全く異なり,拍子も1曲目こそ 3/4 だが,他は 4/4 ,6/4 という異色作。急-緩の「緩」の部分(1曲目は「息の長い主題」)が再現では転調されている。連弾作品として極めて充実した作品で,1曲だけを取り出しても,また3曲まとめての演奏も効果的。
[1]ホ短調 Vivace:長大な作品ながら軽快な運動性と精力的な前進感,劇的な緊張感に満ちて全く飽きさせることなく,曲全体にスポーツ的な爽快感が漲っている。息の長い主題と断片的なモティーフの反復の対比も面白く,ホ長調に転じて壮麗に盛り上がった後,短いコーダで pp に落ち着き,次第に光が増すように輝かしく終わる。極めてピアニスティック。3曲中,最も一般的な「スケルツォ」のイメージにふさわしい作品。(6′40″)[S3/P3]
[2]へ長調 Allegro con spirito:大半が急速な16分音符が連続し,スタッカートが多く使われている軽快でユーモラスな部分と Andante tranquillo の,ゆったりとして表情豊かな部分が交互に置かれている。前半の Andante の部分(へ長調)はロマンティックな旋律を豊麗に歌い上げ,ここを展開部と見れば曲全体を「ソナタ形式」とみなすこともできる。終わり方は,まるで楽しい「オペラの序曲」のよう。(7′00″)[S4/P4]
[3]ロ短調 Allegretto tranquillo:第1部は連打和音上に,ラプソディックな民謡風の旋律が歌われて始まる。この第1部は非常にユニークで,印象主義音楽に接近しており,(半)音階的に上昇して,徐々に川の水が増えて溢れ出すように盛り上がると,のどかな旋律が牧歌的に歌われる第2部に入る。新たな主題も織り込みながら,基本的には第1部と第2部が反復された後,コーダに相当する短縮された第1部(主要主題が逆順で登場)での長いトリルに導かれてロ長調で明快に終わる。(8′30″)[S3/P3] 
シュット Schütt,Edouard(1856~1933)露→オーストリア

生地のセント・ペテルスブルク音楽院でピアノを学び,ライプツィヒ音楽院でもヤダスゾーンやライネッケに学んだ後,ウィーンに出て個人的にレシェティッキにも師事。ウィーンを活動の中心とし,「学術ワーグナー協会」の指揮者も務めた。作曲家としては2曲の「ピアノ協奏曲」や室内楽等の大作も残したが,現在ではシュトラウスIIによるワルツのパラフレーズやごく少数のピアノ小品が知られているに過ぎない。しかし優美で親しみやすく,甘美な曲想とピアニスティックな演奏効果を持つデュオ作品群は再発見される価値が十分にある。なお下記の作品のほか,0p.58-1は "Valse-Paraphrase" , 0p.79-2は "Scherzino" で,いずれも2台ピアノ作品。
- ■創作主題による変奏曲 Op.9
Variationen über ein Originalthema[1880刊] - ■田園の情景 Op.46(全4曲)
Scènes champêtres[1895刊] - ■ワルツの夢 Op.54a(全3曲)
Walzer-Märchen[1897刊] - ■ロココ風即興曲 Op.58-2
Impromptu-Rococo[1899刊] - ■思い出のワルツ Op.61(全5曲)
Souvenir = valses[1901刊] - ■アンダンテ・カンタービレ Op.79-1
Andante cantabile[1907刊] - ■ロシア民謡
Russian Folk-Song[1922刊]
創作主題による変奏曲 Op.9
Variationen über ein Originalthema[1880刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Cranz
★嬰ト短調:主題に10の変奏が続き,主題の回帰で終わる。Andante の創作主題は哀調を帯びた子守歌風のもの。第1変奏はその主題が高音域で歌われ,夢の中で遠く聞こえる子守歌の感があり,続く変奏のオクターヴによる進行のリズムの力強さ,重量感に満ちた響きとは実に対照的。第3変奏は変イ長調に転じて優美で軽快なワルツ。第4変奏は嬰ト短調に戻り,IIによる旋律はハンガリー風に長調と頻繁に交替し,Iはツィンバロム風の装飾的なパッセージを奏する。ここでのIは,まず不規則な連符の数を数える必要がある。続く変奏は,Iが重音を含むアルペッジョを滑らかに奏する上に,IIがスタッカートによる軽快な変奏を弾く。第6変奏は嬰ハ短調の荘厳な葬送行進曲。ホ長調の第7変奏は明朗で牧歌的。嬰ト短調の第8変奏は嵐のような両手のオクターヴ進行。響きが非常にロマンティックなフガートの第9変奏に続き,終曲としてかなり長い躍動的なタランテッラが置かれ,主題が変イ長調で平和に再現された後,タランテッラのリズムで疾走して終わる。シュットの多くの小品の特徴となっている甘美さは乏しいが,半音階的な和声進行や大胆な転調が多い意欲作であり,極めてロマンティックで各変奏の対照感が際立つ真摯な大作。(14′00″)[I:4/II:4]
田園の情景 Op.46(全4曲)
Scènes champêtres[1895刊]
連弾(オリジナル)=Simrock
★「4つの性格的小品」の副題が示す通り,単に親しみやすいだけでなく,各曲の曲想はそれぞれに性格的=個性的で極めて変化に富み,また4曲とも三部形式で主部とは対照的な性格の中間部を持つ。
[1]小屋で Dans la cabane イ短調 Andante sostenuto イ長調 Allegro:エレジ ー風の主部の深々とした情感が印象的。中間部は快活な民俗舞曲風で力強く盛り上がる。再現部では両者の旋律が交じり合う。(3′45″)[S:3/P:3]
[2]草原で Dans la prairie ニ長調 Allegretto grazioso:主部の旋律は軽快なリズムの民謡風のもの。しかし「粗野」な性格とはほど遠く,優雅で洗練されている。Sの左手は,不規則なアルペッジョを滑らかに,しかも表情豊かに弾く必要がある。変ロ長調の中間部の旋律はのどかな安らぎに満ち,ここではSも旋律を担う。(3′00″)[S:3/P:3]
[3]森で Au bois 変イ長調 Poco moto:主部は牧歌的で穏やかだが,フリギア旋法風 の旋律(一部だが),大胆な動きの旋律によるカノン,低音域のトレモロが印象的な中間 部は,深い森の奥での異国の民による踊りを見るかのよう。(2′50″)[S:3/P:3]
[4]村で Au village 変ロ長調 Allegro risoluto ed animato:鍵盤のほとんどを占 める広い音域を使って,精力的なリズムで快活に展開される舞曲風の主部を持つ。対照的にSのソロで始まる変ト長調の中間部は,歌謡的で甘美。終曲としての華麗さと豪快さを備えている。(3′35″)[S:4/P:4]
ワルツの夢 Op.54a(全3曲)
Walzer-Märchen[1897刊]
連弾(オリジナル)=Simrock
★Op.54はピアノ,ヴァイオリン,チェロのための三重奏曲版だが,この連弾版でもPとSの連携が非常に緊密であり,P=旋律,S=伴奏のように役割が単純化された作品ではない。シュットの得意分野であるワルツだが,単に気楽で心地好い旋律をしゃれた和声と軽快なリズムに乗せたものではなく,豊かな情緒と興味深い転調に満ちた洗練されたワルツ集。テンポの変化の指示とともに特にIでは "espressivo" の指示が極めて多く,この作品の魅力を発揮させるためには,それらの指示を巧みに生かす必要がある。
[1]イ短調 Allegro moderato:闇に少しずつ光が差し込むかのような,かなり長い幻想的な序奏の後,懐かしさと諦観に満ちたワルツの旋律が静かに流れ出す。序奏の旋律を挟みながら,さまざまな調を経てイ長調で華やかに終わる。(5′00″)[S:4/P:4]
[2]ニ長調 Allegretto:軽快で短い序奏の後,テンポを少し落としてロマンティックで可憐なワルツが登場する。豊富な対旋律が作品の情緒に濃さと彩りを添えている。練習記号Gからはテンポを速めて別のワルツが登場し,I以降,2つのワルツの旋律が同時に奏され,穏やかな光が消えていくように終わる。手の交差がある。(3′30″)[S:3/P:3]
[3]イ長調 Allegro vivace:極めて快活で躍動的なワルツとテンポの遅い滑らかな旋律のワルツが交互に置かれている。2曲目の旋律も短く登場した後,輝かしく力強く終わる。(5′30″)[S:4/P:4]
ロココ風即興曲 Op.58-2
Impromptu-Rococo[1899刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Simrock
★へ長調 Allegro grazioso:厚い和音(I・IIともに左手にはオクターヴ以上の和音も使われる)が多用されているが,曲想は極めて軽快で優美。I・IIの対話や模倣の機会も多く,変ロ長調 Moderato con moto の中間部では,情緒豊かな旋律を両者が歌い交わし,伴奏の幅広いアルペッジョは華麗でピアニスティック。両手のオクターヴや厚い和音進行によって堂々と終わる。(5′00″)[I:4/II:4]
思い出のワルツ Op.61(全5曲)
Souvenir = valses[1901刊]
連弾(オリジナル)=Simrock
★長いものでもS・P見開きで計4ページという短いワルツ集。ロマンティックで親しみやすく技術的に難しくはないが,作品の魅力を発揮するために「粋」に弾くにはそれなりのセンスが必要。
[1]ニ長調 Allegro energico e vivo:軽快。Pは旋律,Sは伴奏の役割。ほとんどの 部分が反復される。(1′40″)[S:2/P:3]
[2]変ト長調 Moderato un poco moto:旋律も和声も,そしてリズムも耽美的でノスタ ルジック。派手さはないが,その繊細で微妙な美しさはまさに小さな宝石。(1′30″)[S:2/P:3]
[3]イ長調 Allegro grazioso:いかにも連弾らしく。二人が優美な旋律と対旋律を弾き交わす。(1′45″)[S:2/P:2]
[4]ト短調 Poco Allegro cantabile:Sの両手による反行する短いモティーフの特徴的な伴奏に乗せて,Pが透明な響きの悲哀に満ちた旋律を奏する。(1′45″)[S:2/P:2]
[5]ニ長調 Allegro energico e vivo:1曲目が再現され,Sのトレモロを伴うコーダ でテンポを速めて華やかに終わる。(1′00″)[S:2/P:3]
アンダンテ・カンタービレ Op.79-1
Andante cantabile[1907刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Simrock
★ホ長調 Andante cantabile:主部は穏やかな雰囲気の旋律が静かに,しかし豊かな和声に彩られて語られる。中間部は動きを増した旋律と頻繁な転調が,不安と希望が交錯して心を乱すかのようであり,主部の再現では I が旋律を悠々と,II は音階的な動きによる伴奏を奏し,両手の厚い和音やトレモロによって雄大に盛り上がった後,コーダではスクリャービン風の和音の香りも発しながら静かに収まって終わる。ミスプリントの疑いもあり,II の15小節の4拍目のバスの Ais は H?P.5の3段目の1小節目から3小節間,I の下段はへ音記号か。(4′00″)[I:4/II:4]
ロシア民謡
Russian Folk-Song[1922刊] 原曲 歌曲
連弾(自編)=Schirmer
★ニ長調 Moderato - Con poco moto:シャーマー版の表紙によればシュットはこの旋律をピアノ独奏用にも編曲している。甘く切ない郷愁を誘う穏やかな旋律がPやSによってしみじみと歌われ,派手さはないが実に効果的なフィギュレーションの伴奏が,旋律を見事に引き立てている。聴衆の心を落ち着かせ,うっとりとさせるアンコール・ピースとして最適の作品。なお,ロシアで長く活躍したヘンゼルトは同じ主題を使い,ピアノ独奏曲「楽しく,そして悲しい O.K.クレムによるロマンス」を残している。(2′00″)[S:3/P:3]
シュミット Schmitt, Florent(1870~1958)フランス

- ■7つの小品 Op.15(全7曲)
Sept pièces [1901刊] - ■旅芸人の音楽 Op.22(全6曲)
Musiques foraines [1901] - ■気晴らしの小品集 Op.37(全3曲)
Pièces récréatives [1907] - ■8つの短い小品 Op.41(全8曲)
Huit courtes pièces [1909刊] - ■セレナード
Sérénade[1911刊] - ■ユモレスク Op.43(全6曲)
Humoresques[1912刊] - ■リートとスケルツォ Op.54
Lied et Scherzo [1910]
7つの小品 Op.15(全7曲)
Sept pièces [1901刊]
連弾(オリジナル)=Alphonse Leduc
★洗練された響きでロマンティックな「歌」に満ち,常に複数の「歌」が聞こえると言っても過言ではない。そのため全体的に音が厚く,微妙な転調に伴う繊細で多彩な色彩感の表出と的確なバランスが難しいが,またそれがシュミットの連弾作品の魅力に通じている。Sはより多く伴奏を担うが,単調な伴奏型は見られずPとSとの連携も緊密。両者の手は接近しがちで,交差も度々あるが,鍵盤上での手の重複を避ける工夫も丁寧に記されている。初期の作品だが,経験豊かなデュオのための,演奏会用の極めて充実した大作。
[1]まどろみ Somnolence ホ長調 Très calme : ロマンティックな主部では,SとPに交互に現れる3連符を含んだ穏やかに揺れるリズムが安らかな眠りを誘う。カノンの動きで転調を繰り返す中間部は,とりとめのない夢の気分。両者の手が接近する。(3′10″)[S:3/P:3]
[2]リボーピエールの思い出 Souvenir de Ribeaupierre へ長調 Très paisible:弦 楽四重奏的な書法により,タイトル通りのノスタルジックな旋律が紡がれる。技術的には易しい。アルザスのリボヴィレにはリボーピエール家が所有した中世の古城跡があり,シュミットの生地,ムルト=エ=モーゼル県のブラモンにも近い。(3′45″)[S:2/P:2]
[3]きらめき Scintillement ホ長調 Vif:急速な3拍子の,軽快で華やかなスケルツォ風。変ニ長調に転調する流麗な旋律を持つ中間部を持つが,一方でそこではP,Sともに急速で軽快なリズムの伴奏を担当する。Pの左手とSの右手の交差の箇所は2人がキーの奥と手前を弾くことで容易に解決できるが,両者ともに敏捷な指の動きと軽快なタッチが必要。後半の一部でSの4小節がPの1小節に相当する記譜法を使用。(3′15″)[S:4/P:4]
[4]乙女の願い Souhaits de jeune fille ハ長調 Lent:穏やかな曲想だが,不規則なフレーズ,pp から f や ff への急激な音量の変化によって,夢想的で移ろいやすい印象が強まる。前半,Pは音域的には片手で弾けるほど両手が接近する。技術的には易しい。(2′45″)[S:2/P:2]
[5]池の散歩道 Promenade a l'étang 変ホ長調 Assez retenu:旋律そのものはシンプルだが,その和声付けや伴奏型はまさに「洗練の極致」。Sは16分音符が続く伴奏を静かに弾くために,タッチには絶妙なコントロールが必要。(4′10″)[S:4/P:3]
[6]北の祭り Fête septentrionale 卜短調 Animé:伴奏以上に,旋律そのものがいかにも民俗舞曲風のリズムを持つ活動的な部分と,ロ長調の歌謡的な中間部を持つ。舞曲は後半では熱狂的に高まって終わる。舞曲は技術的に難しいが,中間部での息が長くフレキシブルなリズムの旋律を,スムーズに,しかも表情豊かに弾くためには相当な演奏力が要求される。(4′10″)[S:5/P:5]
[7]幸福な航海 Traversée heureuse 変ニ長調 Nonchalamment rythmé:静かに揺れるリズム上での,PとSによるノスタルジックでゆったりとして抒情豊かな旋律のデュエット。伴奏型のリズムが細分化されるに連れて情緒が深まるが,次第に収まって pppで静かに終わる。(4′30″)[S:3/P:3]

旅芸人の音楽 Op.22(全6曲)
Musiques foraines[1901]
連弾(オリジナル)=Hamelle
★旅芸人のにぎやかな出し物の描写的な音楽だが,その夢と幻想に満ちた曲想は,その時代の風俗の簡素なイラストなどではなく,巨匠の筆による芸術的な絵画の感がある。全体的に音が厚く,転調が頻繁で書法も複雑なため,単純明快な解放感や万人向きの親しみやすさにはやや乏しいが,極めてピアニスティックで色彩的なうえ,曲想は奥行き深い。「限られた素材に基づく多様な変化」の見本のような曲が多いだけに,各部の変化が十分に生かし切れないと,特に全曲演奏の場合,単に執拗で冗長な作品に感じられる危険があり,そこにこの作品の魅力と背中合わせの難しさがある。
[1]客寄せ Parade 二長調 Animé:快活で輝かしい2拍子の行進曲風の音楽で,心躍る楽しい期待感とユーモラスな雰囲気に溢れている。曲想は変化に富み,ある部分では夢見るように美麗。(4′35″)[S:4/P:4]
[2]道化師の口上 Boniment de clowns 変ホ長調 Mouvement modéré de Valse:ロマンティックなワルツ。同一のフレーズの変化の妙が魅力。(2′30″)[S:2/P:3]
[3]美女ファティマ La belle Fathma イ長調 Très lent:近東や北アフリカのエキゾチックな民族衣装で着飾った,ベリーダンスのダンサーなどの女芸人。旋律もバスの動きも同一の音型が静かにゆっくりと反復される。(3′30″)[S:2/P:2]
[4]芸達者な象たち Les éléphants savants イ短調 Avec quelque solennité:巨体の象たちによる力強い動きは重々しく圧迫感がある。芸達者な象たちがさまざまな芸を披露するかのように,転調も,そして曲想も多彩。(4′30″)[S:4/P:4]
[5]女占い師 La pythonisse 卜長調 Sans lenteur:女占い師が優しい口調で語るのはロマンティックな未来のようだが,断言ではなく,神秘的な pp の四重トリルの後,ppp の最弱音で言葉を濁すように終わる。同一フレーズが幾多の転調と微細な変化を伴って反復される,ゆったりとしたワルツで,書法は対位法的で複数の旋律が同時に奏されるため,占い師の言葉は多義的に聞こえる。四手が接近しがちで両者の手の交差もある。(4′30″)[S:3/P:3]
[6]回転木馬 Chevaux de bois 変ニ長調 Mouvement de valse vite:第1主題はロンドのリフレインのように幾度も現れるが,その伴奏は万華鏡のように千変万化し,再現部では別の主題と同時に奏される。曲集中,最も華麗で輝かしいワルツで,大胆な手の交差もあり,アンコール曲にも最適。(5′10″)[S:4/P:4]

気晴らしの小品集 Op.37(全3曲)
Pièces récréatives[1907]
連弾(オリジナル)=Hamelle(スコア形式)
★シュミットによる4組の「5つの音」による作品集の2組目で,3曲とも短く軽妙。特に2,3曲目の乾いた抒情は「新古典主義」的。全曲,Pは固定された一つのポジションの5つの音で書かれ,調号はなく派生音は臨時記号を使って書かれている。 IMSLP の楽譜はなぜか偶数ページのみだが,欠落した小節はない。
[1]カドリーユ Quadrille へ短調 Animé : 通常のように5つの部分からなる舞曲ではな く,力強い足取りの快活な民謡風の旋律が変形されたり,さまざまに転調されて反復される。Sに臨時記号の誤りがあるが,容易に見出せよう。(1′30″)[S:3/P:1]
[2]ガヴォット Gavotte へ長調Très modéré:スタッカートが多用された軽快で歯切れの良い旋律を持つ。微細な変化を伴うが各部の反復が多い。(1′30″)[S:2/P:1]
[3]行進曲 Marche 卜短調 Assez animé:切迫する4小節の序奏にスタッカートが多用された軽快な主部と,少しテンポが緩むトリオ風の柔和な部分が続き,それらが反復される。Sの右手はPの両手の間で弾く箇所がある。(1′20″)[S:3/P:1]

8つの短い小品 Op.41(全8曲)
Huit courtes pièces[1909刊]
連弾(オリジナル)=Heugel
★シュミットによる4組の「5つの音」による作品集の3組目。全曲,Pが5つの音で書かれている。「学生の現代音楽(musique moderne)への準備のため」とあり,当時の学生たちの耳にはさぞ斬新に聞こえたことであろう。それから100年以上も後の今では,まったく難解ではなく,新鮮で親しみやすく,ユーモラスにも聞こえる。Pによる旋律は5つの音に限られるが,シュミット得意の転調が巧妙で単調さを感じさせず,PとSとの掛合いも面白い。
[1]序曲 Ouverture ハ長調 Mouvt de Marche:Pによる旋律は5つの音に限られているが,旋律線がSに続く箇所もあり,堂々として晴れやかな広がりさえ感じさせる。Pは音の長短,強弱や硬軟などのニュアンスの表現に集中でき,教材としても優れている。(3′30″)[S:3/P:1]
[2]メヌエット Menuet イ短調 Modéré:歯切れの良いフレーズと歌うような抒情的フレーズ,pと ff のフレーズの対比に乾いたユーモアが漂う。Sによる対旋律が魅力的。(2′00″)[S:3/P:1]
[3]歌 Chanson ハ長調 Presque lent:Pは子守歌のような旋律をゆっくりと静かに歌う。Sの両手の動きも「歌」に満ちている。(2′30″)[S:3/P:1]
[4]セレナード Sérénade ハ長調 Animé,sans exagération:景気の良い序奏に軽快なワルツが続く。ワルツはロマンティックでノスタルジックな雰囲気の中に軽い皮肉を秘める。(1′50″)[S:4/P:1]
[5]ヴィルレー Virelai 卜長調 Gai et sans précipitation:ヴィルレーは中世フランスの世俗歌曲の一形式。スタッカートを多用した歯切れの良い旋律を持つ,軽快で活発な舞曲風の作品。(1′10″)[S:3/P:1]
[6]ボレロ Boléro へ長調 Très modéré:リズミカルな旋律はP,Sによって交互に奏され,両者の掛合いが特に面白い。コーダでの Lent のレチタティーヴォ風の箇所が全体に絶妙な変化を与えている。(3′15″)[S:3/P:1]
[7]哀歌 Complainte ニ短調 Lent:15/8 (小節は破線によって9/8と6/8に分けられている)と9/8による変拍子の作品。タイトル通りの素晴らしい哀感が込められていて,両者とも技術的には難しくないが,的確な表現は極めて至難。演奏時間は任意の反復を行った場合。(3′10″)[S:2/P:1]
[8]行列 Cortège イ長調 Un peu solenne1,sans lenteur:4/4 ,3/4 ,2/4 ,7/4と
さまざまに拍子が変わるに連れて,伴奏型も旋律のニュアンスも刻々と移り変わる。堂々
として晴れやか。(1′50″)[S:3/P:1]

セレナード
Sérénade[1911刊]
連弾(オリジナル)=Pierre Rafitte
★ニ長調 Animé:雑誌"Album Musica No.108"に所収。Pは固定されたポジションの5つの音のみを弾く。 6/8から3/4拍子に変え,音価と小節数を倍にしたため,視覚的には異なる印象が強いが,実質的には「眠りの精の一週間(ヤルマールの夢)Op.58」の5曲目,「ふぞろいな文字のロンド」と同一曲。乾いた皮肉と優しい抒情の間を揺れ動く。恐らくこの「セレナード」が「ロンド」の原曲であろう。(1′20″)[S:3/P:2]

ユモレスク Op.43(全6曲)
Humoresques[1912刊]
連弾(オリジナル)=Philippo(スコア形式)
★単に「滑稽」な作品ではなく,全6曲の曲想は多彩な変化に富み,それぞれは豊かなイメージに満ちているが,多くの曲中で,音量の変化の意外性に面白さがある。第1,2,5曲はシュミットの作品中では特にPの書法が薄いため響きが明快であり,技術的に弾き易いだけでなく,このピアニスティックで機知に富んだ曲集の親しみやすさを増している。
[1]軍隊行進曲 Marche militaire ハ長調 Très rythmé:華麗なファンファーレで始まり,軍楽隊が遠くから近づき,眼前を通ってはるか彼方に去ったかと思いきや,クレッシェンドして ff で終わる様子がユーモラス。「ラ・マルセイエーズ」の香りがする。(3′10″)[S:3/P:2]
[2]ロンドー Rondeau ト長調 Assez animé:活発,明快で途中の3拍子と2拍子の交錯が,いっそう熱狂的な前進感と面白さを増す。一気呵成に進行するが,その和声は極めて繊細でロマンティックであり,速いテンポで通り過ぎるのが惜しいほど。(1′25″)[S:3/P:2]
[3]牧歌 Bucolique ホ長調 Paisible:冒頭のPの上声に現れ,その後は中声部やバスに現れる半音下がって終わる短いフレーズや,ゆらゆらと揺れるように下降するフレーズが多く,フォーレ風の優しく穏やかな抒情と微妙に揺れ動く感情に満ちている。テンポの変化や転調も多く,音が厚い。(4′30″)[S:4/P:4]
[4]小スケルツォ Scherzetto ハ長調 Vif:主部の旋律はスタッカートが多用された軽快なもので,タイトル通りひょうきんな性格。変イ長調の中間部でのはじめはSに,次いでPに現れる流麗な旋律は,極めてロマンティック。音量の急激な変化が特徴。(2′20″)[S:4/P:4]
[5]感傷的なワルツ Valse sentimentale 変ト長調 Pas vite:優美でロマンティックな旋律をPとSとが歌い交わし,後にはカノンを含むデュエットとなる。シュミットの数多くの連弾作品中でも,最も伝統的なロマン派の作風に近くて親しみやすい上,技術的にも易しい作品の一つ。(3′00″)[S:2/P:2]
[6]グロテスクな踊り Danse grotesque イ短調 Animé,sans éxagération,et avec quelque lourdeur:指示は「誇張なしに,いくらか重く」だが,音量の変化の幅が広く,誇張なしでも巨大で鈍重な熊の踊りのような印象を受けよう。さまざまな転調を経て最後はイ長調の性格が強まるが,終わりから2小節目の変ロ音でその明るさを中和するところが,いかにもシュミットらしい。(2′20″)[S:4/P:4]

リートとスケルツォ Op.54
Lied et Scherzo[1910]原曲 室内楽曲
連弾(自編)=Durand(スコア形式)
★原曲は2組の管楽五重奏のための作品。Sによる,徐々に発育する植物の芽のような「問い」のモティーフに,Pが急速でリズミカルな「答え」を弾く謎めいた序奏に続き,Sの伴奏と手を交差させながら,Pによる Lent のノスタルジックで透明な悲しみを秘めた3/4拍子の「リート」が登場する。この魅力的な「歌」は,はじめの「問い」から派生したもの。その後,Pのグリッサンドに導かれて,そのリズムが「答え」から派生している12/8拍子の行進曲風の快活な「スケルツォ」部分に続く。リズムの読み易さのためにPとSで拍子の異なる箇所もあるが,遅い部分での旋律の表情付けや複雑なリズムが難しく,両者の手の接近,交差も頻繁で後半にはSの右手がPの両手の上の音域を弾く箇所もある。熟練したデュオ向きの,繊細さとスケールの大きさを併せ持つ洗練された大作。(10′00″)[S:5/P:5]

シンディング Sinding, Christian(1856~1941) ノルウェー

ヴァイオリニストを志したが,ライプツィヒ音楽院在学中に作曲家に転向。今日ではピアノ小品,「春のささやき Op.32-3」のみが知られているに過ぎないが,ヴァーグナーとリストから強い影響を受け,オペラをはじめ4曲の「交響曲」,3曲の「ヴァイオリン協奏曲」,1曲ずつの「ピアノ協奏曲」と「ピアノ・ソナタ」や250曲以上の「歌曲」など,あらゆる分野に多くの作品を残した。ピアノ・デュオ作品は,音域を広く使った厚い書法により豪快な響きを発する作品が多く,下記の作品にはノルウェーの民俗音楽臭はほとんど感じられない。下記以外のオリジナル連弾作品として「8つの小品 Op.71」と「ノルウェーの舞曲と歌 Op.98」がある。
- ■変奏曲 Op.2
Variationen[1889刊] - ■組曲 Op.35a(全4曲)
Suite[1896刊] - ■二重奏曲 Op.41(全2曲)
Duette[1898刊] - ■ワルツ集 Op.59(全7曲)
Walses[1903刊]
変奏曲 Op.2
Variationen[1889刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Wilhelm Hansen
★変ホ短調,Andante の極めてシンプルな4小節フレーズを,IとIIが弾き交わす主題部に9つの変奏とコーダが続く。力感に溢れ,2台のピアノが発する豪快な響きと迫力が特徴のロマン派の巨人的大作だが,オクターヴ以上の和音はごくわずか。2台のピアノが対等に扱われているだけに,両者ともに強大なスタミナと各種の高度なテクニックが要求され,特に第1変奏での両手それぞれの繊細なトリルの連続や,第2変奏でのオクターヴと和音の連続は至難。リズミカルな第4変奏から第5変奏にかけての驀進するような盛り上がりも極めて効果的だが,決して力技一辺倒ではなく,可憐な第3変奏や明るいロマンに満ちた第7変奏,「葬送」と題されてはいても歌心に富んだ第6変奏が作品に豊かな変化を与えている。演奏される機会は少ないが,晦渋な変奏は皆無で親しみやすく,ともに変ホ長調の長大な行進曲風の第9変奏と短いコーダで,輝かしく豪快に終わる。単に「騒々しいだけ」に感じさせない工夫が必要。[17′00″](I:5/II:5)

組曲 Op.35a(全4曲)
Suite[1896刊]
連弾(オリジナル)=Peters
★後に「騎士道的エピソード Épisodes chevaleresque op.35b」として管弦楽化されたが,楽譜の表記は両版とも Op.35 。 管弦楽化も当然と思えるほど音が厚く,多声的でリズムも複雑であり,そのリズムや伴奏型は創意に満ちて実にユニーク。重厚な響きに満ちた,スケール豊かな典型的な後期ロマン派の大作で,全体的に音が厚く,バランスが難しいうえに4手とも動きが複雑なため,技術的に極めて高度。
[1]へ長調 Tempo di marcia:2拍子の快活な楽章だが,2,3,4小節フレーズが混在しているので流動的な前進感が強い。3小節フレーズによる変イ長調の中間部にはSの長いソロが用意されている。短いフレーズの反復進行で徐々に盛り上がる箇所はヴァーグナー的。[5′00″](S:5/P:5)
[2]変口短調 Andante funebre:他に類例がないほど壮麗な葬送の行進。Sは,厚い音の中で喇叭が聞こえ,ドラムのロールが重々しく鳴り響く。Sの8小節のソロに導かれる中間部は,極めて甘美でロマンティック。[9′50″](S:4/P:4)
[3]変イ長調 Allegretto:高貴で豪華な宮廷舞曲風の楽章。旋律の細かい装飾的な動きが優雅さを強調するが,Sの左手によるバスの動きはオクターヴが多く,重苦しい響きにならないように弾く必要がある。Sが旋律を担う中間部は,音が厚いが常に pp の指示があり,Pによる素早い音階的な伴奏の動きがユニーク。[3′50″](S:3/P:4)
終曲 Finale へ長調 Allegro moderato:S のソロによる歯切れ良く快活な舞曲風の主題で始まり,Pに主題が受け渡されて華やかに展開される。テンポを落とした中間部は,やはりSのソロで始まり,後にPが旋律を奏するが,ここでの両者の伴奏の動きもユニーク。Sによる低音部のトレモロを伴って大きく盛り上がった後,この「組曲」中では珍しく音の薄いコーダに入り,次第に盛り上がって終わる。[6′00″](S:4/P:5)

二重奏曲 Op.41(全2曲)
Duette[1898刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Wilhelm Hansen
★2曲は別々の楽譜で出版され,楽譜冒頭の上部には「2つの二重奏曲 Zwei Klavierduette」と書かれ,それぞれ Op.41a と 41b の作品番号が記されている。2曲とも幅広い和音やオクターヴを駆使して豪快にピアノを響かせ,1曲目は2台のピアノが2つの旋律を弾き合うさまが,2曲目は2台のピアノ間でのフレーズの応酬が,いかにも「デュエット」のタイトルにふさわしい。オクターヴ以上の和音も多く,独特の伴奏部やグリッサンドの多用が実にユニーク。
[1]変ホ短調 Andante:IIによって静かに歌い出される主題は,「五木の子守歌」との酷似に驚かされるが,Iによる伴奏部は旋律と素早いアルペッジョが組み合わされた個性的なもの。両者が役割を交替しつつ展開され,長調の主題は幅広い和音を豪快に響かせて壮大に盛り上がり,変ホ長調で堂々と終わる。ドビュッシー風に聞こえる箇所もある。[5′30″](I:5/II:5)
[2]ハ長調 Deciso ma non troppo allegro:主部は,リズミカルで祝典的な短いフレーズの2台ピアノ間での応酬が執拗に反復され,中間部では転調を伴うものの,同一のフレーズが反復され,特に後半の16小節間は同じ和音進行が続く。冒頭と中間部の2つのフレーズの反復によって,ほぼ全曲が構成されているといっても良く,ヴァーグナー風の壮麗な展開に心酔,共感できるかどうかが評価の判断基準となりそう。ピアノ・デュオ作品中,最も多くグリッサンドが使われる作品で,離れた音域への急速な跳躍も頻発する。[7′40″](I:5/II:5)

ワルツ集 Op.59(全7曲)
Walses[1903刊]
連弾(オリジナル)=Wilhelm Hansen
★シンディングのデュオ作品中では,音が薄く,ffの指示は一つもなく,サロン風の軽妙さと親しみやすさを持つロマンティックなワルツ集。転調が効果的で興味深く,技術的には易しい曲が多い。テンポの指示はなく。1集4曲,2集3曲に分かれているが番号は通し番号。
[1]ハ長調:Pによる,伸びやかに上昇しては半音進行を多く含んで下降する主題が魅力的。変ホ長調のワルツはSのソロで登場し,2度目にはPが華やかな装飾を加えるのがいかにも連弾らしく,愉悦感に満ちている。[4′05″](S:3/P3)
[2]イ短調:重々しく粘性に富む旋律を持つ。PとSとがデュエットを続ける。[2′45″](S:2/P:2)
[3]卜長調:Pの両手がオクターヴ,あるいは2オクターブ離れたユニゾンで,可憐な旋律を弾く。Sは伴奏のみ。[1′50″](S:1/P:2)
[4]ホ短調:情熱的な旋律をPが弾き出した後,Sがその旋律を受け持つとPは装飾的な動きを加える。中間部はト長調で華やか。[1′55″](S:2/P:2)
[5]変ニ長調:主部は優美な旋律を持つ。中間部はSのソロで始まり,Pが旋律を担当すると即興であるかのような変化と転調が加わる。(2′30″)[S:3/P:3]
[6]変イ長調:主部は明朗で精力的。へ長調で始まって転調を続ける中間部は,PとSとの掛合いがおもしろい。[2′35″](S:2/P:2)
[7]変ホ長調:アルペッジョ付きの和音が2拍子で上昇するSの動きが極めて優雅だが,Pによる旋律には,その動きやリズムに軽いユーモアが感じられる。中間部はP,Sともに3度重音が多い。高音域の響きが華やかだが,味わい深い弱音のコーダを経て終わる。[3′00″](S:3/P:3)

ダルベール d'Albert, Eugène (1864~1932) 独

イギリス人の母,ピアニストで作曲家のドイツ出身の父を持ち,スコットランドのグラスゴーに生れた。父に,次いでロンドンで王立音楽大学の前身の国立音楽養成校で学び,メンデルスゾーン奨学金を得てウィーンに留学し,ドイツ音楽に傾倒してドイツに帰化した。リストにも学んで高く評価され,世界最高のピアニストの一人にも数えられたが,次第にピアノ演奏から離れて作曲に専念した。代表作の「低地地方」を含む20曲のオペラのほか,「ピアノ協奏曲」2曲や「チェロ協奏曲」,その他管弦楽曲やピアノ作品等を残した。ピアノ・デュオ作品は下記の1曲のみだが,管弦楽曲がロベルト・ケラーやレーガーらによって連弾用に編曲されている。6度結婚し,テレサ・カレーニョは2番目の妻。
ワルツ集 Op.6(全13曲)
Walzer[1888刊]
連弾(オリジナル)=Bote & Bock
★全13曲のワルツ集。第5,7,8,9曲は曲尾が終止線でなく複縦線であり,第7曲には "attacca" と記され,第13曲のコーダで1曲目が回想されることか ら,全曲演奏が原則だが,1曲ずつ終止しており,アンコール等に1曲だけ取り上げることも可能。曲想は全曲が親しみやすく,ヘミオラが随所に使われて特にリズムが面白い。超絶的な技巧は使われてはいないが,ヴィルトゥオーゾ・ピアニストを偲ばせるスケールの大きさを感じさせるワルツもある。
[1]ホ長調 Frisch,belebtes Walzertempo:力強く活気に満ち,スケール豊か。中間部は対照的に軽快で柔和な表情。[1′50″](S:3/P:3)
[2]ロ長調 Gehalten:長調と短調の間を移ろい,弱音中心だが粘着質で情熱的。Sの伴奏の中の半音の動きが,粘性をより高めている。[2′30″](S:3/P:2)
[3]ト長調 Belebt:軽快なリズムで明快。ユーモアもある。[0′40″](S:3/P:2)
[4]ハ長調:畳み掛けるフレーズを持ち,歓喜に満ちて激情的。中間部のゼクエンツが極めて甘美でロマンティック。[1′15″](S:3/P:4)
[5]変イ長調 Wiegend:軽快なリズムの優美なワルツ。後半はPと手を交差させながらSも旋律を弾き,いかにも連弾的。[1′40″](S:3/P:3)
[6]ロ長調:Pの旋律もSの伴奏も一貫してヘミオラによる2拍子。曲想は穏やか。[1′25″](S:1/P:2)
[7]ロ短調 Langsamer:感傷的でロマンティック。前半はP自身,後半は手を交差させながらの両者のデュエット。ロ長調に転じ次の曲に続く。[2′00″](S:2/P:3)
[8]ト長調 Einfach:Sは3拍目から始まるリズム・パターンを終始反復する。Pによる旋律は極めて簡素だが,合奏と表情付けは意外に難しい。[1′05″](S:2/P:1)
[9]変ホ長調 Langsam und ausdrucksvoll:重層的で穏やかな波のように上下に動く旋律はブラームス的。[2′00″](S:2/P:2)
[10]変ロ長調 Walzertempo:軽快な運動性に富み,リズムが面白くヴィルトゥオーゾ的。[1′00″](S:3/P:3)
[11]ト短調 Leicht bewegt:Pによるスタッカートで軽快に下降するアルペッジョの伴奏の下,Sによる旋律は焦燥感に満ちる。Pのアルペッジョのアクセントの不規則さが不安 を高めるが,コーダ風の曲尾ではト長調で,Pの旋律もSの伴奏も滑らかに変わる。[0′50″](S:3/P:4)
[12]ハ長調 Breit:華麗で豪胆,ダイナミックだが柔らかく弱音で終わる。[1′30″](S:2/P:3)
[13]ホ長調 Langsam und ausdrucksvoll:さわやかで落ち着いた旋律によるSとPの問答で始まり,重唱へと移行する。コーダで1曲目のモティーフが回想され,テンポを上げて華やかに終わる。[2′30″](S:3/P:3)

ディートリヒ Dietrich, Albert(1829~1908)ドイツ

マイセン近郊のゴルクで生れ,ライプツィヒ音楽院でハウプトマンやモシェレスに学び,デュッセルドルフではシューマンにも学ぶ。ブラームスの友人の一人であり,「回想録」も残している。多くはない作品中にはブラームスに献呈した「交響曲 Op.20」のほか,室内楽や協奏曲等もあるが,今日それらは忘れ去られ,師シューマンやブラームスと合作してヨアヒムに献呈された,ヴァイオリン・ソナタ「F.A.E.(自由だが孤独)」の第1楽章が知られる。
ソナタ Op.19(4楽章)
Sonate[1870刊]
連弾(オリジナル)=Walter Wollenweber 出版情報:Walter Wollenweber
★ロマンティックで極めて親しみやすく,さわやかさと力強さの絶妙なバランスが保たれている魅力的な作品。楽譜通りに反復すると演奏時間はやや長い大作だが,技術的に過度に難しくなく,Sも全楽章とも主題を弾き,主題の受け渡しをはじめ,それぞれのソロや手の交差もあり。連弾作品として弾いても聴いても楽しめる。初版は Rieter - Biedermann社よりだが,1979年に上記 W.W.社から再版され現在も入手可能。
[第1楽章]卜長調 Allegretto:優美な第1主題,ホ短調で力強い第2主題,二長調で滑らかな動きの第3主題のいずれもが,P~Sの順に提示されるのが特徴。再現部での第1主題の変イ長調での出現は印象的。優美な愛らしさの一方,迫力に満ちた劇的な一面も見せる。Pは48,203小節がやや難しい。[9′20″](S:3/P:4)
[第2楽章]スケルツォ Scherzo ホ短調 Vivace:歯切れ良く,力強く活発な動きを持ち,PとSとのリズム上の噛み合わせが緊密。ホ長調のトリオでの流麗なPの旋律と,半音階的に下降するSの対旋律が素晴らしい。主部とトリオの前・後半のそれぞれを反復する。[8′25″](S:4/P:4)
[第3楽章]ハ長調 Andante sostenuto:室内楽的で多声的な書法による冒頭の穏健な主題は,ほとんど1小節毎に転調する。PとSとの美しい旋律的な対話が魅力的で,中間部は熱く盛り上がる。次の楽章に続く。[3′50″](S:2/P:2)
[第4楽章]卜長調 Lento - Allegro vivace - Con fuoco, non troppo presto:おもに音階的な走句による11小節の経過部を経て,熱気と活力と歓喜に満ちた主部に入る。ソナタ形式の主部は,たたみかけるような力強さを持つ第1主題と,対照的なコラール風の第2主題を持つ。大迫力の展開部を経て,熱気に満ちたコーダで終わる。[7′50″](S:4/P:4)

ノスコフスキ Noskowski, Siegmund (1842~1912)ポーランド

ワルシャワで生れ,同地の音楽院でモニューシュコに学び,その後ベルリンでキールに学ぶ。1880年以降ワルシャワに戻って母校でポーランドの次世代の作曲家を育て,生徒の中にはシマノフスキやフィテルベルクの名もある。 またワルシャワ音楽協会を運営し,ワルシャワ・フィルハーモニーの指揮者も務めた。作曲家としては歌劇や3曲の交響曲,管弦楽曲や室内楽があり,細かく数えると100曲ほどのピアノ小品も残している。下記以外の連弾作品として「クラコヴィアク集 Op.25」「ポーランド組曲 Op.28」「マズル集 op.38」「6つのポロネーズ op.42」のほか,連弾と混声合唱のための「遍歴楽士 op.18」がある。
クラコヴィアク集 Op.7(全6曲)
Cracoviennes[1880刊]
連弾(オリジナル)=J.Rieter-Biedermann
★シンコペーションが特徴的なクラクフ地方に起源を持つ舞曲による曲集。いずれも軽快で躍動的なリズムを持ち,次々に登場する旋律は親しみやすいうえに実に味わい深い。Sも旋律を弾く機会が多く,両者の掛合いも面白く工夫されている。これまで全く顧みられなかったのが不思議なほど,楽しく魅力的な作品集。
[1]嬰へ短調 Moderato assai:Sの右手による,チェロに適するような深い抒情と憂愁をたたえた旋律で始まる。この旋律がロンドの主題のように幾度も現れ,またこの旋律の冒頭が,快活な旋律を中断して現れ,曲想に変化と深みを与える。調性が異なる速いテンポの快活な舞曲がいくつも登場し,長い反復部分を持つ。[5′35″](S:3/P:3)
[2]婚礼の騎手 Ein Hochzeitsreiter ホ長調 Allegro con fuoco:ポーランドでは自動車が普及するまで,花婿は馬で結婚式場に向かうのが一般的であったとされる。Sは終結部の4小節以外,すべて軽快な伴奏を担い,Pは歓喜に満ちた急速な旋律を弾く。Pの両手はオクターヴ離れたユニゾンの動きが多く,左手にも器用さが要求され,特に速いテンポで颯爽と弾くためには高度なテクニックが必要。[2′10″](S:4/P:4)
[3]へ長調 Allegretto poco animato:極めて魅力的な民謡風の明朗な旋律を持つ。Sは終結部で回想的に旋律を奏するほか,リズミカルな伴奏を担うが,伴奏型は実に変化に富み,多彩で飽きさせない。主題後半のモティーフの反復の際の,和音の変化が素晴らしく,盛り上がった末の最後の和音が弱音で終わるのに象徴されるように,明るくさわやかな詩情の中に,微かにはかなさが漂う佳品。[2′30″](S:3/P:3)
[4]変ロ短調 Moderato mesto e sosutenuto:冒頭のゆったりとした歩みのPによる旋律は,短調と長調と間を頻繁に行き来する趣深いもの。変ロ長調の部分では,SがPと手を交差させながら冒頭の旋律を自由に変奏し,Pは対旋律を加える。続く中間部の変ト長調の部分はテンポも速まり,極めてロマンティック。終り近くのPの両手の弱音による高音域の繊細で微かな輝きも印象深い。対位法的な処理が多く,P自身による,あるいは両者のデュエットが魅力的。[5′00″](S:3/P:3)
[5]変ホ長調 Allegro non troppo:冒頭の旋律はリズミカルで快活な性格で,軽快なアーティキュレーションが陽気な気分を高める。少しテンポを緩めたメロディアスで多声的な変卜長調~変ホ短調の部分が続き,主部となる。トリオは変イ長調で行進曲風。冒頭の旋律はPとSによるユニゾンで,アーティキュレーションを一致させるのが難しい。[4′15″](S:3/P:3)
[6]ロ短調 Allegro con spirito:民族舞曲風の活発なリズム上に,旋回するような動きの急速な旋律を持つ。広い音域が使われ,響きは重厚で力強い。ややテンポを落とした滑らかな旋律がロマンティックに歌われるロ長調の中間部を挟み,熱狂的に盛り上がって終わる。[2′50″](S:4/P:4)

ルテニアの旋律集 Op.33(全8曲)
Mélodies Ruthéniennes[1891刊]
連弾(オリジナル)=Augener & Co.
★ルテニアはウクライナ西部とポーランド南東部にまたがる地域の歴史的名称。「ガリツィアとウクライナ地方の民族の歌と舞曲による8つの性格的小品」の副題を持ち,いずれもシンプルな旋律(副題が示すように,原曲があるのだろう)が豊かに,そして変化に富んで和声付けされ,対位法も加えた熟達した連弾書法によって処理されている。
[1]聖歌とコロムイカ Cantique et Kolomyjka イ短調 Poco maestoso Allegretto animato:冒頭は5音音階による素朴な主題を,Sの左手以外の3手がそれぞれオクターヴ離れたユニゾンによる厚い響きで堂々と歌う。その後,この主題がP,S間で交互に歌われるさまは聖歌隊による合唱の雰囲気で,終り近くで民族舞曲の軽快なリズムが予告され,そのまま「コロムイカ」に続く。これはリズミカルで快活なウクライナの舞曲で,多彩な伴奏型と対旋律が作品の興趣を増している。[2′40″](S:3/P:3)
[2]歌 Chanson へ長調 Andantino cantabile:ゆったりとした旋律で穏やかに始まり,広い音域でオクターヴを多用して英雄的に大きく盛り上がるが再び静まって終わる。主部の6小節の伸びやかなフレーズがいかにも民謡風。[3′00″](S:3/P:3)
[3]聖歌と変奏 Cantique varié 変ロ短調 Andante con moto:「聖歌」といっても,重々しく語られる悲劇に満ちた叙事詩のような感傷的で民謡風の主題に,4つの変奏が続く。コンパクトな構成と極めてロマンティックで親しみやすい曲想が特徴。旋律を担当するのは,主題から各変奏毎にP・S・P~と交替する一方,伴奏も対位法的で,決して安直なものではなく,各変奏の軽・重,静・動の変化も大きい。最後の変奏は変ロ長調で,Sによる伴奏は流動的なリズムを持ち,特にロマンティック。4小節間の反復進行の cresc.の頂点がp という指示も蠱惑的。[4′10″](S:4/P:4)
[4]ルテニア舞曲 Danse ruthénienne ニ長調 Poco Allegro:力強く,シンプルなリズムのいかにも民謡風の旋律を持つ。同一フレーズの反復が多用されるが,和声を変えて変化を与えている。テンポを落とすト短調の中間部では曲想も静まるが,後半はテンポを戻してSによる伴奏に対位法的な処理を加えながら,賑やかに輝かしく終る。[3′00″](S:3/P:3)
[5]ロマンスと小歌 Romance et chansonnette ト短調 Andante cantabile-Allegro non troppo:「ロマンス」は哀調を帯びた旋律が表情豊かに歌われ,Sによる繊細な対旋律が悲哀の度を高める。その一方で変ホ長調の「小歌」は,5音音階による軽快でシンプルな民謡風の3小節フレーズが執拗に反復されるが,伴奏は反復毎に変化を伴い,飽きさせない。その後,伴奏のリズムが一層細分化されて「ロマンス」が再現され,ト長調の主和音のトレモロで消えるように終わる。[3′30″](S:4/P:3)
[6]トロパーク Tropak イ長調 Allegro gajo:タイトルは「トレパーク」のウクライナでの呼称。主部は明朗,快活で力強く輝かしい。Sは伴奏に徹するが,対旋律と反復の際の和声の変化が興味深い。対照的に感傷的な嬰へ短調の中間部は,ルバートやテンポの変化,反復時の各声部の強調など,面白く聴かせるための演奏上の工夫の余地が多くある。30と70小節目のSの右手,はじめの和音の最下音の本位記号は嬰記号の誤りではなかろうか。またgajo=gaioで「陽気な」。[2′00″](S:3/P:3)
[7]瞑想 Zadumka へ短調 Andante-Allegretto tranquillo:Andanteの部分では,Pによる熱を帯びた粘性の旋律に拍子の異なる小節が挟まれ,奔放な雰囲気と情熱を高め,Sによるラプソディックで変化に富む伴奏が,その傾向を強めている。Allegrettoの部分はリズミカルで軽快な曲想で,へ短調に始まり変イ長調に転じる。その後,両者が短縮されて反復され,テンポを速めて終る。Sに頻出するトレモロが嘆きを深める。ノスコフスキにはこのタイトルを持つ作品がほかにも数曲ある。[2′45″](S:4/P:4)
[8]田舎の踊り Danse rustique 変ロ 長調 Allegretto:快活で明朗な舞曲が続き,色とりどりの衣装の踊り手たちが,入れ替わりながら披露する祭りでの踊りを見る思いがする。中ほどの,ト短調のややゆっくりとした感傷的な部分では,1曲目の冒頭と同じく,Sの左手以外の3手がそれぞれオクターヴ離れてユニゾンで旋律を奏する厚い響きが登場する。[2′55″](S:3/P:3)

ノッテボーム Nottebohm, Gustav (1817~82) 独

ヴェストファーレン州のリューデンシャイトに生れ,グラーツで没した。ベルリン(1838~39)やライプツィヒ(1840~45)で学び,ライプツィヒではメンデルスゾーンやシューマンと知り合い,教えを受けた。1846年からはウィーンに定住し,ブラームスやヨアヒムの友人となった。音楽学者として著名で,資料に基づいて作品を校訂し,主題目録を作った最初期の一人で,その成果はキンスキーによるベートーヴェンや,ドイチュによるシューベルトの主題目録の基礎となり,ベートーヴェンのスケッチの研究が後世に与えた影響は計り知れない。作品は少なく,おもにピアノ小品とピアノを伴う室内楽。
バッハの主題による変奏曲 Op.17
Variationen über ein Thema von J. S. Bach[1865刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★ニ短調 Andantino:「フランス組曲 第1番」中の,小品ながら滋味溢れる「サラバンド」が主題で,ロマン派の格調高い変奏曲に仕立てられている。主題はピカルディ3度を廃した以外,原曲の改変はわずかで,右手のパートの音をSに配してP・S間のバランスを整えている。メロディアスな16分音符の連続がP・S交互に現れる第1変奏も,激情が噴出する第2変奏も両者の役割の交替が顕著。第3変奏はリズムは平静だが2度が悲劇的に響く。揺れるようなリズムを持つ第4変奏は,中間部でのニ長調への転調が曲想を際立たせている。続く第5変奏はニ長調で拍子も前と同じく 6/8 であり,自由なカノンによる穏やかな曲想。第6,7変奏は拍子も 2/4 に変わり,軽快でキビキビとした動きのもの。4声のフガートによる重々しい第8変奏を経て,トッカータ風で華麗な第9変奏で終わる。第8,9変奏はピカルディ3度で終止し,最後の壮麗さを引き立てている。なおライネッケも同じ主題による変奏曲を残しており,そちらは変奏毎の変化の振幅が大きいのが特徴だが,こちらからはよりスケール豊かな印象を受けるのは,単に変奏の数が一つ多いだけではなく,複数の変奏を通しての構成が意識されているためであろう。[18′10″](S:3/P:3)

バルギール Bargiel, Woldemar (1828~97)ドイツ

クララ・ヴィークの異父弟に当たり,クララの紹介によってシューマンやメンデルスゾーンと知り合う。ペルリンでジークフリート・デーンに,その後ライプツィヒではモシェレスやゲーゼに学び,1874年以降,ベルリン高等音楽学校でパウル・ユオンらを教えた。またブラームスの友人でもあった。作品は少なく,作品番号は47に止まるが,下記以外の連弾作品として「組曲 Op.7」「ジーグ Op.29」がある。また IMSLPには演奏時間30分を越える4楽章構成の大作,「交響曲 Op.30」の作曲者自身による連弾版があるが,連弾で高い演奏効果を発揮するのは難しいと思う。
ソナタ Op.19(3楽章)
Sonate[1862]
連弾(オリジナル)= Rieter-Biedermann
★ロマンティックな瑞々しさ,陶酔的で濃厚な抒情,響きの豪快さを併せ持つ佳品。PとSとの連携が極めて緊密で,技術的にも難しくなく,連弾作品として弾いても聴いても楽しめる。楽譜にはP,Sそれぞれに重複する音が散見される。
[第1楽章]卜長調 Moderato:冒頭の第1主題からPによる伸びやかな旋律と,半音階的に下降するSによる対旋律が登場し,連弾の醍醐味を満喫できる。第2主題の連打和音上でのPとSの対話も大いに楽しめる。七の和音の多用がロマンティックな気分を高め,オクターヴや厚い和音の使用が迫力を増している。[6′50″](S:3/P:3)
[第2楽章]変ホ長調 Lento:4小節半のフレーズの,弦楽四重奏的な書法による崇高な主題がSによって静かに弾き出され.Pも旋律的な動きで加わる。心ざわめく感傷的なト短調の部分や,大きな盛り上がりを経た後,静かに収まって終わり。次の楽章に続く。P.17で本位記号のいくつかが欠落と思われる。[6′20″](S:2/P:3)
[第3楽章]ト長調 Allegro molto - A11egro grazioso:16小節のリズミカルで軽快な経過句を経て,やはり軽快で流れるような主部に入る。快活に疾走する楽しい楽章で,ホ短調の歌謡的な中間部を挟む三部形式。後半は転調もコーダもなく,形式的にはシンプル。[4′05″](S:3/P:3)

レントラー Op.24-1
Ländler[1864刊]
連弾(オリジナル)= G.Schirmer
★イ長調 Moderato:Rieter-Biedermann社から初版が刊行された「3つの舞曲 Drei Tänze op.24」の1曲目だが,IMSLP のファイル名は "3 Dances brillantes" で,後世の連弾曲集からの抜粋。ゆったりと旋回するようなメロディを持つ親しみやすい小品でSも対旋律を弾く。へ長調のトリオはホルン5度を持つ牧歌的なもの。[3′40″](S:1/P:2)

フックス Fuchs, Robert(1847~1927)オーストリア

スロベニアとの国境に近いフラウエンタールで生れ,幼児期に義兄からフルート,ヴァイオリン,ピアノ等の楽器や通奏低音奏法を習う。18歳でウィーンに出てデッソフに学ぶ。弦楽のための「セレナード 第1番」(1874年)の成功で作曲家として認められ,後にはウィーン音楽院教授としてマーラーやシベリウスなど,多くの著名な作曲家を教えた。親交があったブラームスからも高い評価を受けていた。いずれも5曲の「交響曲」と「セレナード」のほか,「ピアノ協奏曲」や3曲の「ピアノ・ソナタ」をはじめとするピアノ作品を残している。ピアノ連弾作品も数多く,今日では不当に忘れ去られているが,復活すべき傑作も多い。
- ■5つの小品 Op.4(全5曲)
Fünf stücke[1872刊] - ■6つの小品 Op.7(全6曲)
Sechs stücke[1872刊] - ■セレナード 第2番 Op.14(4楽章)
Serenade No.2[1874] - ■ワルツ集 Op.25(全24曲)
Walzer[1880刊]
[1874]
- ■とても易しい小品集 Op.28(全12曲)
Sehr leichte stücke[1880頃] [1874]
- ■ウィンナ・ワルツ集 Op.42(全20曲)
Wiener Walzer[1886刊] - ■夢の絵 Op.48(全7曲)
Traumbilder[1890刊]
5つの小品 Op.4(全5曲)
Fünf stücke[1872刊]
連弾(オリジナル)=Kistner
★まったく性格の異なる5曲による,典型的なロマン派の連弾小品集。 P,S間の連携がリズム的にも旋律的にも緊密で,響きが多彩で美しく,ピアニスティック。また作品の質そのものとは関係がないが,各ページの小節の配置に譜めくりの便が考えられている。IMSLPのファイル名,"4 Pieces for Piano 4-hands"の曲数は誤り。
[1]へ長調 Mässig bewegt:付点リズムが多用された,軽快で快活な作品。ユーモラスな雰囲気がある。[2′25″](S:3/P:3)
[2]ニ短調 Lebhaft:連打和音による伴奏とスタッカートによる旋律が,力強い前進感を高めている。[2′00″](S:3/P:3)
[3]変口長調 Ruhig:牧歌的な明るさと穏やかさを持つ。[1′30″](S:2/P:2)
[4]ニ長調 Gemüthlich:付点リズムの多用による弾むような旋律が,PとSとのカノン風の動きで展開される。温かく気楽な雰囲気に満ちている。[1′50″](S:2/P:2)
[5]へ長調 Kräftig:「力強く」と指示されたリズミカルで精力的な作品。指定のテンポが速くないために,落ち着いた行進曲風だが,主題の気紛れで道化た性格が実に個性的でユーモラス。急激で大幅な音量の変化かおもしろく,随所で豪快な響きを発する。[3′45″](S:4/P:4)

6つの小品 Op.7(全6曲)
Sechs stücke[1872刊]
連弾(オリジナル)=Kistner
★3曲ずつ2集に分けられているが,曲の番号は1~6の通し番号。どちらか1巻ずつの演奏でも曲想や調性の変化が適度にあり,曲集としてのまとまりが感じられる。ロマンティックで親しみやすく,効果的な小曲集。全体的にテンポ指示は遅め。
[1]ト長調 Etwas langsam:32分休符で区切られた,付点リズムを多く含む軽妙な旋律を両者が弾き合う。気楽な散歩のような快適さに満ち,両者のリズム的な連携が非常に緊密。[2′25″](S:3/P:3)
[2]ホ短調 Leicht bewegt:リズミカルな伴奏上に,スタッカートを多用した繊細で神経質な旋律が軽快に流れる。多声的な旋律はP自身や,PとSとによって弾かれる。[2′30″](S:3/P:3)
[3]ハ長調 Äusserst ruhig:Pによる多くは6度,または3度重音の旋律が,滑らかに歌われ,極めてロマンティックな情緒に満ちている。[2′25″](S:2/P:3)
[4]イ短調 Krätig,nicht zu rasch:主部はP,Sともにオクターヴでの動きや厚い和音が多用され,前進感に溢れた決然としたリズムと相俟って壮快な響きを持つ,劇的な物語風の作品。極めて遅いテンポの嬰ハ短調,3/8拍子の中間部は,哀調と慰めを含んだ旋律が滑らかに歌われ,葬送の雰囲気。[5′20″](S:3/P:4)
[5]ホ長調 Langsam,breit:穏やかで宗教的な崇高感さえ持つ賛美歌風の佳品。[2′40″](S:1/P:1)
[6]ハ長調 Mässig bewegt:1集の3曲目と同様,Pによる精力的な旋律は6度や3度重音が多用されるが,こちらは軽快でリズミカルな舞曲風。 P,Sともに両手はオクターヴ離れたユニゾンの動きが多く,力強く豪壮に終わる。[2′50″](S:3/P:4)

セレナード 第2番 Op.14(4楽章)
Serenade No.2[1874] 原曲 弦楽合奏曲
連弾(自編)=Kistner, Universal
★フックスの親しみやすい「セレナード」は,当時大変な人気を博していた。全5曲の「セレナード」のうち,IMSLPには1~4番までの作曲者自身による連弾用編曲のファイルがあるが,総合的に連弾でも最も効果的な第2番を取り上げた。原曲に忠実で4手が接近しがちな編曲。Sは伴奏部をより多く担当するが,旋律を奏する箇所やPとの掛合いもある。
[第1楽章]ハ長調 A11egretto:Sによるスタッカートの軽快なリズムの伴奏上に,Pが心弾む楽しげな旋律を奏する。Pの旋律は重音(おもに3度)による動きが多い。[2′50″](S:3/P:4)
[第2楽章]ホ短調 Larghetto:主題は短調だが,単なる感傷に止まらない奥行きと深さを備えている。繊細に揺れ動くような中間部を経て,ホ長調での主題の再現部はスケール豊かで雄大だが,その後,収まってホ短調で静かに終わる。一部に両者の手の交差がある。[5′30″](S:3/P:3)
[第3楽章]ハ短調 A11egro risoluto:弦楽器群の総奏による精力的な主題や,短く区切られたアーティキュレーションによる軽快な音型,旋回するような音型の多用が,力強い民族舞曲的な雰囲気を高める。[3′00″](S:3/P:3)
[第4楽章]ハ長調 Presto:軽快,快活なタランテッラ。 P,Sともに連打(和)音が多く,Sも一部は旋律を弾く。[4′00″](S:4/P:4)

ワルツ集 Op.25(全24曲)
Walzer[1880刊]
連弾(オリジナル)=Kistner
★12曲ずつ2集に分けられた,ごく短いワルツの曲集。最も長い曲でも各パート1ページ半ほどで,技術的には易しい曲が多いが各曲の表情の変化は大きい。フックスの作品には,同一のモティーフやリズムパターンが反復されることが多いが,こうした短い作品ほど,魅力的な効果を高めている。1集はいかにも「ワルツ」らしい優美で甘美な曲が多いが,2集は長い曲が多く,また技術的にもやや高度で曲想もより多彩となり,「ワルツ」の優美さからは遠い作品も含まれる。ブラームスの「ワルツ集Op.39」への敬意であろうが,類似の音型があちこちに現れる。
■第1集 Heft 1■
[1]嬰へ短調 Ländler tempo:深い悲しみ。明るくなりかけて暗く沈み込む最後が秀逸。[1′40″](S:1/P:2)
[2]嬰へ短調:悲哀に満ちて,もの寂しい。[0′45″](S:1/P:2)
[3]イ長調:Sの右手による半音階的な対旋律が特徴。長調だが「明朗」には届かない。[0′50″](S:2/P:2)
[4]二短調:決然として激しい情熱を叩きつける。[1′20″](S:2/P:3)
[5]二長調:滑らかに流れる優美な旋律を持つ。[1′15″](S:1/P:2)
[6]卜長調:悠然とした旋律の,PとSとによるデュエット。[2′40″](S:2/P:2)
[7]ロ短調 Etwas bewegter:鍵盤を幅広く使い,激烈で雄大。転調を経てロ長調で静かに終わる。[1′20″](S:3/P:3)
[8]二長調 Ruhiger:感傷的に始まり,ロマンティック。[1′05″](S:1/P:2)
[9]ト長調 Etwas bewegter:軍隊ラッパの伴奏と,悠々とした旋律を,PとSとが役割を交替しながら弾く。スケール豊か。[1′25″](S:2/P:2)
[10]口長調 Etwas langsamer:弱音中心で密やかでロマンティック。転調が特徴的。[1′40″](S:1/P:2)
[11]変ト長調 Wie Anfangs:変ホ短調で始まる。甘美な追憶。[1′45″](S:1/P:2)
[12]変卜長調 Langsamer:PとSとが,ほぼ全曲でオクターヴ離れたユニゾンで旋律を奏するしみじみとした終曲。[1′15″](S:2/P:2)
■第2集 Heft 2■
[1]ハ長調 Walzer-Tempo:全24曲中,最もきらびやかで洒落ている。ポリリズムが軽やかに舞い翔ぶような効果を上げている。[1′30″](S:2/P:3)
「2」変イ長調 Ländler-Tempo:静かに揺れるリズムが穏やかな抒情をかもし出す。[1′10″](S:1/P:2)
[3]変イ長調:PとSとがオクターヴ離れたユニゾンで郷愁を誘う旋律を優しく歌う。Pの右手による高音域の装飾的なアルペッジョが効果的。[1′10″](S:1/P:2)
[4]へ長調 Etwas langsamer:大胆に歩みを進める堂々とした作品。意外な転調がおもしろい。[2′20″](S:1/P:2)
[5]イ短調 Ländler-Tempo:揺れ動くPと,憂鬱なSとのデュエット。[2′30″](S:1/P:2)
[6]イ短調:響きの薄い箇所でさえ,両手のオクターヴ離れたユニゾンの動きにより,ffで激烈に突き進む。[0′45″](S:2/P:2)
[7]イ長調 Ruhiger:8分音符の連綿とした静かな流れを持つ繊細な曲想。[2′00″](S:2/P:2)
[8]二短調:情熱が籠った,粘性に富む旋律を持つ。[0′50″](S:1/P:2)
[9]二長調 Langsam,sehr getrangen:誇らしい旋律を高らかに歌い上げる。後半はPとSとのデュエット。[1′00″](S:1/P:2)
[10]ロ短調 Bewegt:活発で力強い民族舞曲風。ロ長調に転調して終わる。[1′20″](S:3/P:2)
[11]変ホ長調 Langsam:SからPに連なる旋律を持つ。ロマンティックで甘美。[1′30″](S:2/P:2)
[12]ト短調 Mässig bewegt:暗い情熱に満ちて驀進する。急激な音量の変化やSによるsfが興奮の度を一層高める。[1′45″](S:3/P:3)

とても易しい小品集 Op.28(全12曲)
Sehr leichte stücke[1880頃]
連弾(オリジナル)=Max Brockhaus
★Pは親指を軸としたポジションの移動なしに弾ける連弾曲集。ただし,一つの固定されたポジションの5音のみで1曲を弾き通すのではなく,フレーズの切れ目などでポジションの移動があるため,Pには運指の表記がある。そのため1曲目から楽譜上の運指に従って鍵盤上での手の移動に注意を払う必要が生じ,また前半の6曲は両手がオクターヴ離れたユニゾンの動きだが,後半の6曲は両手が独立した動きとなるので,「とても易しい」というタイトルだが,後半は「バイエル」後半程度の難易度となる。Sによる伴奏は,和声も転調も凝ったもので,曲としてのおもしろみが大いに増すが,Pの強弱記号が抜けている箇所もある。初歩からの漸進的な教材として意図された曲集ではないようだが,ロマン派の連弾小品集としての価値がある。以下に4曲を取り上げてコメントを付した。
[7]変ホ長調 Maestoso:国家的な式典にふさわしい威厳と栄誉を備えた堂々とした曲。Sが張り切り過ぎると,全体のバランスを崩しがち。[1′30″](S:3/P:1)
[8]変口長調 Andantino:繊細でロマンティックな舟歌。[1′10″](S:2/P:1)
[10]ハ長調 Andantino sostenuto:詩情豊かで,創意と変化に富む和声付けの好例。[1′40″](S:2/P:1)
[11]ト長調 Un pocp lent:SとPとの,トリル音型の掛け合いの楽しい作品。速いテンポでは「二匹の蜜蜂」とでもいったタイトルが似合うかわいらしい曲となるが,この速度の指示は実に意外。和声の変化に耳を傾けつつ,指の平均と独立への注意を促すためであろう。[2′30″](S:2/P:1)

ウィンナ・ワルツ集 Op.42(全20曲)
Wiener Walzer[1886刊]
連弾(オリジナル)=Simrock
★10曲ずつ2巻に分けられているが,曲の番号は通し番号。最後の20番のみ見開き2ページだが,他はすべて見開き1ページというごく短いワルツ集。前・後半とも,あるいは一方を反復する曲がほとんど。技術的には易しい曲が多いが甘やかで洒落た旋律と,それを支える豊かで多彩な転調が実に魅力的な傑作。1巻の方がいかにも「ウィンナ・ワルツ」らしい曲が多く,2巻はテンポの指示からも分かるように,各曲の曲想はより多彩となる。Sも伴奏のみを担当する曲は少なく,主旋律や対旋律を弾く機会を多く持つ。数曲を抜粋しても,また1曲をアンコール等に取り上げても極めて効果的。
[1]ニ長調 Tempo di Valse moderato:前半の半音階的になだらかに上昇する曲線的な旋律と,スタッカートによる軽快な後半が対照的。ppからffまでの急激な盛り上がりが陶酔的。[1′45″](S:2/P:3)
[2]ト長調 Poco meno:両者が手を交差させながら旋律と対旋律を弾き出す。甘美で濃密なロマンに満ちている。[1′40″](S:2/P:3)
[3]ロ短調 Più mosso:激しい情熱が籠められ,転調を経て口長調で終わる。[1′00″](S:2/P:3)
[4]ホ長調 Tempo I ma sonore:スケール豊かで堂々とした曲想。Sも低音域で力強く旋律を歌う。[1′45″](S:3/P:3)
[5]変イ長調 Tranquillo e dolce:ためらうように半音階的に下降する繊細な旋律が,PとSによるカノンで登場する。親密な語らいの風情。[1′30″](S:3/P:3)
[6]嬰ハ短調 Vivace:運動性に富んだ,軽快に旋回するような旋律をPが弾く。その両手は終始,オクターヴ離れたユニゾンの動きで,重音も含むため流暢に颯爽と弾き切るには相当なテクニックが必要。頻繁な短・長調間の転調を経て,変ニ長調で終わる。[1′00″](S:2/P:4)
[7]変ニ長調 Tranquillo:静かに,子守歌風に揺れるリズム。強調する音の選びかたによって表情が大きく変わる。[1′55″](S:1/P:3)
[8]嬰へ短調 Più mosso e con fuoco:押さえ切れない激情がsempre ffで噴出する。[0′55″](S:2/P:4)
[9]ニ長調 Più tranquillo:いかにもウィーン風なリズムを備えた優美で魅力的なワルツ。[2′25″](S:2/P:3)
[10]口長調 Teneramente:弱音中心で,穏やかで落ち着いた抒情に溢れる。[1′40″](S:1/P:3)
[11]変ホ長調 Walzer-Tempo:オルゲルプンクトとホルン的な響きが,スケール豊かな田園的広がりを感じさせる。[2′55″](S:2/P:2)
[12]卜長調 Sehr langsam und innig:Sによる,表情豊かで雄弁な旋律で始まる。手を交差させながらPによる旋律も加わり,より多声的に処理されて終わる。[1′55″](S:2/P:3)
[13]変ホ長調 Ländler-Tempo:軽快なリズムとユーモラスな旋律が実にチャーミング。長調と短調の間を滑るように移り変わる。[1′20″](S:2/P:3)
[14]変イ長調 Ruhig und innig:優美で小刻みなステップによる舞踏のよう。[2′10″](S:2/P:3)
[15]嬰ハ短調 Langsam,sehr ausdrucksvoll:暗い情熱に満ち,粘性に富む旋律と重々しいリズムは,まるで「ハンガリー舞曲」の一節。ためらうような優雅な中間部を持つ。[2′00″](S:2/P:2)
[16]イ長調 Walzer-Tempo:穏やかな明るさに満ちて,8分音符の連続により,よどみなく流れる。[1′55″](S:2/P:2)
[17]ホ長調 Langsam und ausdrunckvoll:主役のSが,高貴で悠然とした旋律を担う。[2′45″](S:2/P:2)
[18]ニ短調 Bewegt:連打音を多用した軽快な旋律を持つ個性的な作品。[1′00″](S:3/P:4)
[19]嬰へ長調 Ländler Tempo:P自身が伸びやかな旋律をデュエットで歌い交わす。[1′55″](S:2/P:3)
[20]ト長調 Mässiges Walzertempo:両者が一緒にオクターヴ以上に上昇しては下降する息の長い旋律を弾く。終曲らしい華麗さと豪華さを持つ。[1′35″](S:3/P:3)

夢の絵 Op.48(全7曲)
Traumbilder[1890刊]
連弾(オリジナル)=Peters(1~3),Schirmer(4のみ)
出版情報:Kunzermann(全曲)
★舞曲的な性格の曲が多いが,各曲とも転調が巧妙,多彩で,スケールの大きさとともに豊かな幻想に満ちた,真摯で充実した作品。
[1]ハ短調 Un poco con moto,ma passionato:リズムは3拍子の民族舞曲風だが,「増三四の和音」の強調による屈託ありげな響きが幻想的な雰囲気を強める。音が低・中音域に集中する二長調の中間部は,深々とした豊かな抒情が極めて魅力的。[4′55″](S:3/P:3)
[2]変イ長調 Allegretto grazioso,con espressione:主部は,静かにゆったりと揺れるワルツ,またはレントラー風で,Pは大部分でオクターヴ離れたユニゾンの旋律を弾く。中間部では,旋律が希望を求めるように長調で上昇するが,希望はついえて短調に変わる。[6′15″](S:3/P:2)
[3]へ短調 Vivace:主部は憂鬱な雰囲気の急速なタランテッラ。へ長調の中間部は滑らかな動きで明るい雰囲気だが,不安定な3小節フレーズのため前進感が強い。[3′10″](S:3/P:3)
[4]ニ短調 A11egro scherzando:3拍子の軽快な民族舞曲風だが,スタッカートが多用された歯切れ良く軽快な旋律からは北欧風の冷気が感じられる。[3′10″](S:2/P:3)
[5]二長調 Andante sostenuto:半音階的な動きが多く,PとSとがゆったりとした情緒豊かな旋律をデュエットする。[2′40″](S:2/P:2)
[6]変口長調 Allegro con espressione:洒落て華やかなワルツ。[2′00″](S:3/P:3)
[7]二長調 Vivace:主部は2拍子の精力的な舞曲風,または速い行進曲風で,両者の両手とも,素早い音階的な動きが要求される。平静で滑らかな動きの中間部は,主部との著しい対照が印象的。[5′15″](S:4/P:4)

ポルディーニ Poldini, Ede(Eduard)(1869~1957) ハンガリー

生地のブダペストの国民音楽学校で学び,後にウィーンで,更にジュネーヴでも学び,1908年以降スイスに居を定める。現在では,クライスラーがヴァイオリンとピアノのために編曲した「踊る人形」(原曲は指揮者のニキシュに献呈された全7曲のピアノ独奏曲集,「人形芝居」の2曲目)のみが知られているに過ぎないが,数々の舞台作品と多数のピアノ小品は,当時広く人気を博した。ハンガリーの民族的要素は薄く,「忘れられた作曲家」の一人だが。親しみやすいデュオ作品は顧みる価値がある。
- ■風俗的小品集 Op.12(全5曲)
Genrestücke[1896刊] - ■5つの演奏会用小品 Op.13(全5曲)
Fünf Vortragstücke [1896刊] - ■2台のピアノのための練習曲(シューベルトの即興曲 作品90-2による)
Studie für 2 Klavier (über das Impromptu von Fr. Schubert, Op.90 No.2)[1902刊]
風俗的小品集 Op.12(全5曲)
Genrestücke[1896刊]
連弾(オリジナル)=Julius Hainauer
★各曲の曲想,音域,音量の変化の振幅が大きく,弾いても聴いても気軽に楽しめる,極めて親しみやすい,色彩的で洒落た音による細密画集。アンコールに1曲だけを取り出すのも効果的。ハイナウアー社の楽譜の表紙を眺めるのも楽しい。
[1]湖畔にて Am See 変ホ長調 Andantino: 6/8 拍子の典型的な「舟歌」。主部のPによる伸びやかな旋律が特徴。Sが旋律を担う中間部では転調に伴って心も波立つ。[4′00″](S:3/P:2)
[2]滑稽な物語り Curious Geschichte イ長調:半音階的に下降する4小節のフレーズが,調を変えながら変奏される愉快な作品で,リムスキー=コルサコフらによる「24の変奏曲と終曲」を連想させる。音域やテンポ,音量の変化が大きく,最後は fff で鍵盤の最低音のA音が登場。[1′30″](S:3/P:3)
[3]人形のワルツ Puppenwalzer 変ホ長調 Tempo di valse:有名な「踊る人形」の姉妹編とも言うべき作品で旋律も似ているが,よりメカニカルな曲想からは,いかにも人形の動きが感じられる。低音域の音が少なく,響きもかわいらしい。(2′25″)[S:2/P:2]
[4]ボスポラスの夜曲 Nachtmusik am Bosporus ホ短調 Allegretto:ソフト・ペダルを踏み通し,ほぼ全曲に渡ってSは ppp ,Pは pp の指示がある。デリケートでエキゾチックな響きの軽快な小品。8小節ずつのABABAのシンプルな構造で,Sが同じ和音を弾き続けるBでは右ペダルも踏み通す。[1′35″](S:2/P:2)
[5]ジプシー風 Zigeunerisch イ短調-ハ長調 Con fuoco-Più lent : 活力に満ちた情熱的な旋律を持ち,Pによるグリッサンドが華やかさを添える。反復が多く,効果的な演奏には演出上の工夫が必要。[3′30″](S:2/P3)

5つの演奏会用小品 Op.13(全5曲)
Fünf Vortragstücke [1896刊]
連弾(オリジナル)=Julius Hainauer
★5曲中,2曲が異国趣味の作品であることも含め,前述の「風俗的小品集 Op.12」と同傾向の作品。
[1]小姓の歌 Pagenlied ハ長調 Allegretto:Sによる軽快で活気に満ちたリズム上に,Pが陽気な旋律を奏する。その楽しい旋律の魅力は,ポルディーニが数々の人気オペレッタの作曲家であった事を十分に納得させ得る。[1′40″](S:2/P2)
[2]アンダルシアの女 Andalusierin ホ短調 Vivo-Tempo di Mazurka:弱音中心のひっそりとした曲想で,中間部の旋律にはスペイン情緒が漂う。[2′40′″](S:2/P:2)
[3]キルギスの剣舞 Kirgisischer Waffentanz イ短調 Allegro moderato:力強いリズムの勇壮な舞曲。Sの左手のオクターヴの進行,右手の厚い和音が迫力を増している。[2′00″](S:3/P:3)
[4]屋根の上の雀たち Die Spatzen auf dem Dache へ長調 A11egretto mderato:主部は軽快なスタッカートのかわいらしい曲想で,PとSとの掛合いが楽しめる。中間部はSのシンコペートされた和音による滑らかな伴奏上に,Pが晴れやかな旋律を奏する。[2′40″](S:2/P:2)
[5]紡ぎ歌 Spinnlied 変イ長調 Vivo:Sが素早く軽快で旋律的な動きを奏し,Pは伸びやかな旋律を柔和に奏する。中間部ではPも一部で素早い動きに参加する。[4′05″](S:3/P:2)

2台のピアノのための練習曲(シューベルトの即興曲 作品90-2による)
Studie für 2 Klavier (über das Impromptu von Fr. Schubert, Op.90 No.2)[1902刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Julius Hainauer
★変ホ長調 Allegro:2台のピアノ間の掛合いが楽しい上,原曲の素早い動きの旋律にオクターヴや3度,6度を重ねた響きが華やかさと色彩感を増す。口短調の部分で,はじめの(変ホ長調の)動きを転調させて2つの旋律を同時に出したり,「さすらい人幻想曲」の第3楽章の旋律を加える等の仕掛けも実に効果的で面白く,この種の編曲としての成功作。原曲そのものに素早く精密な動きが要求されるため,I,IIともに少なくとも原曲が弾ける力が必要。タイトル通り,細かい動きと表情をきちんと合わせるための実に有益な練習曲だが,単なる練習曲と見なしてしまうのは,誠にもったいない佳品。[4′00″](I:4/II:4)

マスネ Massenet, Jules(1842~1912)仏

「マノン」や「タイス」に代表される,フランスの人気傑作歌劇の作曲家。パリ音楽院でトマに学び,後に自身がパリ音楽院教授を勤め,ショーソンやアーン等を教えた。多数のロマンティックな歌劇と歌曲で知られるが,管弦楽曲や器楽曲も残し,ピアノ作品としては1曲の「ピアノ協奏曲」以外にも多くの小品を残した。下記以外の連弾作品に「舞踏会の情景(ペストの思い出)Op.17」がある。
小品集 組曲 第1番 Op.11(全3曲)
Pièces 1re suite[1866]
連弾(オリジナル)=Durant, Schnænewerk & Cie.
★緩・急・緩の対照的な楽章からなる連弾小曲集。随所にマスネらしい流麗な旋律が聴けるだけでなく,対位法的な書法が多く使われ,PとSの対話の機会も豊富。なお3と2は「チェロとピアノのための2つの小品」(1867刊)の編曲。
[1]へ長調 Andante:Sの右手により,つぶやくように歌われるデリケートな旋律上に,PがSの動きを忠実ではないまでも,拡大した旋律を伸びやかに歌う。Pの旋律はフレーズの終りに decresc.と dim.が重ねて記され,まるで賛嘆の「ため息」のよう。対位法的に書かれながらも堅苦しさは微塵も感じられず,中間部のSからPに受け渡されるアルペッジョの進行も極めて魅力的。最上のフランス風の優雅さと甘美な抒情に溢れた逸品。(2′10″)[S:3/P:3]
[2]卜長調 Allegretto quasi allegro:連続する付点リズムを備え,装飾音に彩られた旋律を持つ快活な舞曲で,曲想はバロック風でもあり,また民謡風でもある。中間部は厳密ではない3声のカノン。(3′10″)[S:3/P:3]
[3]変ニ長調 Andante:見開きわずかに2ページの小品でPが穏やかな主旋律を奏し,時折Sが対旋律や合いの手を加える。(1′00″)[S:2/P:2]

過ぎ去りし年(全12曲)
Année passée[1897刊]
連弾(オリジナル)=Heugel et Cie.
★「夏の午後 Après-midi d'été」「秋の日々 Jours d'automne」「冬の夕暮れ Soirs d'hiver」「春の朝 Matins de printemps」の4集(各3曲ずつ),全12曲で四季を綴った全曲の演奏時間約30分の大作。マスネの連弾曲はフランス風の軽妙で優美な作品ばかりという誤った先入観を打破する,迫力に富む重厚な作品も含まれている。極めて変化に富む各曲は完成度が高く,知名度こそ低いが,ロマン派の連弾作品の傑作であることは疑いない。
[1]木陰にて A l'ombre イ長調 Assez lent et mystérieux:風に揺れる木々の下で繊細に明滅する木洩れ日の光と影と緑のグラデーション。音階的な,あるいはアルペッジョの急速な動きの上に穏やかな旋律が歌われる。(3′00″)[S:3/P:3]
[2]麦畑にて Dans les blés イ短調 Modéré:鄙びた旋律による自由な変奏。カノンに続き劇的な変奏が登場し,この場所で起こった重大な出来事を想像させる。(3′00″)[S:3/P:3]
[3]大きな太陽 Grand soleil 二長調 Avec ampleur:赤々と燃えながらゆっくりと沈む壮大な夏の太陽。Sは基本的には下降する重厚な旋律を奏し,Pは幅広い和音を連打する。和音の変化は微妙な旋律を伴い,最後の和音は両者ともに ffff。(1′30″)[S:1/P:3]
[4]黄ばんだ葉 Feuilles jaunies 変ニ長調 Assez lent:3手のための作品。Pは右手で単音の旋律を弾くのみだが,頻繁に転調するその旋律はSの対旋律ともども,いかにもマスネらしい風情をたたえ,極めて優美でロマンティック。(1′40″)[S:2/P:1]
[5]11月2日 Deux novemble 嬰へ短調 Triste, assez lent:この日は「万霊節」。Sによる遠い鐘の音で始まり,重々しい聖歌風の旋律が聞こえる。少しテンポが速まる嬰ヘ長調の中間部では,束の間,明るさが増すが,再び死者への思い出に沈む。(3′50″)[S:2/P:2]
[6]楽しい狩り Joyeuse chasse 二長調 Très animé:躍動的なリズムに満ち,力強いホルンの音がこだまする。いわゆる「狩の歌」でP,Sともに水が流れるようなモティーフの使用は個性的。(2′55″)[S:4/P:4]
[7]クリスマス Noël 変ホ長調 Très modéré:4手のユニゾンによる敬虔な合唱で始まる。宗教的な喜びが込められた変奏では,対位法的処理によって自由に動く声部が加わる。(2′00″)[S:2/P:3]
[8]夢見ながら En songeant へ短調 Très lent:深刻で痛切な旋律と和声は,S~P~Sと弾き継がれる幅広いアルペッジョを挟んで続く。Pの最後に登場する旋律は「マノンヘの愛の動機」。(2′40″)[S:3/P:3]
[9]人々はワルツを踊って… On valsait… へ長調 Mouvt.de valse:優雅で華麗なワルツ。Sも旋律を弾く機会が多い。(2′15″)[S:3/P:3]
[10]初めての巣づくり Les premiers nids ハ長調 Vif,alerte et gai:軽快に鳴き交わすつがいの小鳥。リズムも旋律もPとSとの掛合いが多く,ざわめくような中間部は木々を揺らす風でもあろうか。(3′05″)[S:4/P:4]
[11]リラの花 Lilas 卜長調 Très modéré et caressant:16分休符で繊細に区切られる甘美な旋律からは花の香りが匂い立つかのよう。それぞれの左手は右手を越えて短いアルペッジョで軽く伴奏を加える。個々の技術的以上に,堅苦しくならずに優美に弾いてピタリと合わせるのは非常に難しい。(1′15″)[S:3/P:3]
[12]復活祭(大ミサの散会) Pâques(Sortie de la Grand' Messe) 二長調 Modéré:鳴り渡る鐘の音と,高らかに歌われる歓喜に満ちた旋律。快活なフガートを挟み,豪壮に盛り上がって全曲を閉じる。Sには88鍵の最低音が頻出する。(2′20″)[S:4/P:4]

マルトゥッチ Martucci, Giuseppe(1856~1909)伊

変奏曲 Op.58
Variazioni[1902刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Ricordi
★変ホ長調:IMSLPのファイル名は“Tema con Variazioni”(ピアノ独奏曲)で,2P版を編曲としているが,改編の度合いがかなり大きい事もあり,ここでは「オリジナル」とした。2台のピアノの音響のパワーを駆使し,明晰さと楽天的で豪快な力強さを特徴とする大作。IIのソロによる,弦楽合奏がふさわしい穏やかな性格の Andantino の主題部は,8小節の旋律が2度現れる。2度目は変ホ短調で登場し,転調を経て主調に戻るので,主題部自体が変奏曲的性格を持つ。第1変奏はIのソロにより,主題が5連符の流れに溶け込んでいる。第2変奏からは2台のピアノが共奏し,短いリズム的モティーフの掛合いの中に2小節の流麗なソロが置かれる。この作品は2台のピアノの対等な扱いも特徴の一つで,前半と後半では掛合いの先と後,ソロの分担が逆になる。第3変奏は深々とした響きで悠々と歌われる旋律に,他方がリズミカルで華やかな伴奏を添える。ここでも半音階的に下降するソロがテンポを落として登場し,幻想的な雰囲気を高める。第4変奏は力感と活気に満ちた「狩の歌」風のリズムで,第5変奏はスタッカートの輝かしい分散和音の部分とレガートな旋律が交互に置かれる気紛れな気分なもの。6/4拍子の第6変奏は半拍ごとに変化する和音による瞑想的な部分と,微風のように軽快な動きの部分が交替する。第7変奏はI・IIそれぞれが両手交互のリズミカルで軽快な和音奏。第8変奏は「ショパン風に」と書かれ,一方の厚いバス音上に他方が幅広いアルペッジョとノクターン風の極めてロマンティックで陰影に富む旋律を奏する。しかし神経質で線の細い曲想ではなく,9/4拍子で1ページに2小節ずつという配置のためもあり,視覚的にも骨太で雄大な印象を受ける。最後の第9変奏は両手交互の打鍵によるエネルギッシュなトッカータ風なもので,コーダでは厚い和音とオクターヴの多用によって主題が再現され,豪壮に曲を閉じる。(12′30″)[I:5/II:5]

モシェレス Moscheles, Ignaz(1794~1870)チェコ

プラハ音楽院でディオニス・ヴェーバーに,ウィーンではアルブレヒツベルガーとサリエーリに師事し,またベートーヴェンと懇意になる。 1826年から20年間をロンドンで過ごし,ピアニストや教師として活躍した。その後,かつてベルリンで教えたこともあるメンデルスゾーンによってライプツィヒ音楽院にピアノ科主任教授として招かれ,その地で没した。作曲家としても作品番号は150にも及び,8曲の「ピアノ協奏曲」や多数のデュオ作品を含むピアノ作品を残したが,今日それらの大部分は忘れ去られたままになっている。ピアノ・デュオ作品は多数なだけでなく,様式的にも古典派的な性格が強いものから完全にロマン派様式のものまで,作品の規模も初歩的な小品からヴィルトゥオーゾ的な大作まで,それらの様態はさまざまだが,いずれも興味深く,注目すべき作品が多い。
- ■協奏的大二重奏曲 Op.20(4楽章)
Grand Duo Concertant[1812頃刊] - ■華麗なロンド Op.30
Rondo brillant[1814刊] - ■トリオ付きの6つのワルツ Op.33(全6曲)
6 Walzes avec trio[ ? ] - ■大二重奏曲 Op.35(4楽章)
Grand Duo[1815] - ■大ソナタ Op.47(4楽章)
Grande Sonate[1853刊] - ■美しい結合 序奏付きの華麗なロンド Op.76
La belle union Rondeau brillant précédé d'une introduction
[1828頃刊] - ■協奏的二重奏曲 ヴェーバーのメロドラマ「プレチオーザ」のジプシーの行進曲による華麗な変奏曲 Op.87b
Duo Concertant Variations brillantes sur la marche bohémienne tirée du mélodrama Preciosa de C.M.de Weber[1833] - ■序曲 オルレアンの少女 Op.91
0uverture Die Jungfrau von Orleans[1835刊]原曲 管弦楽曲 - ■ヘンデルを称えて Op.92
Hommage à Händel[1822] - ■お伽話 Op.95-5
Un conte d'enfant[1893刊] - ■ヴェーバーを称えて オイリアンテとオベロンの動機による大二重奏曲 Op.102
Hommage à Weber Grande duo sur des motifs d'Euriante et d'Oberon
[1842刊] - ■交響的大ソナタ Op.112(4楽章)
Grande sonate symphonique[1846刊] - ■滑稽な変奏曲,スケルツォと祝典行進曲 Op.128
Humoristische Variationen Scherzo und Festmarsch[1856] - ■踊り シラーの詩による性格的小品 Op.129
Der Tanz Charakterstück nach Shiller's Gedicht[1858] - ■ドイツ民謡による交響的英雄行進曲 Op.130
Symphonisch-heroischer Marsch über deutsche Volkslieder[1860刊] - ■かわいいおしゃべりさん Op.142-1
Die Kleine Schwätzerin[1900刊]
協奏的大二重奏曲 Op.20(4楽章)
Grand Duo Concertant[1812頃刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Artaria(I・II分冊)
★M.Giuliani(マウロ・ジュリアーニ イタリアの名ギター奏者で作曲家)との共作で,楽譜の表紙には「ピアノ(フォルテ)とギター,または2台のピアノのために」とあるために「オリジナル」としたが,ギターでこの楽譜を使って演奏するとは考えられず,「ピアノとギター用」の楽譜から,ギターのパートをIIとして,ピアノ用にモシェレス自身が手を加えたのであろう。それでもなおIIにはギターに適した音使いが随所に見られるところが誠にユニーク。タイトルの示す通り,2台のピアノが協奏的に対等に扱われ,華やかで楽しい旋律が次々に繰り出される親しみやすい作品。現在のピアノと違い,当時の楽器はギターとの二重奏でも違和感は少なく,ジュリア一ニはウィーンに住んだ時期もあり,フンメルとも共作で同種の作品を残している。
[第1楽章]イ長調 Allegro maestoso:決然としたリズムの和音に続き,両者が短い会話のようなパッセージを弾き交わして始まり,やがて行進曲風だがかわいらしい第2主題に至る。これに続くIの華麗で繊細なパッセージや,IIのいかにもギター的なカデンツァが聴かせどころ。展開部では少しテンポを落としてイ短調の感傷的な主題が登場し,両者が主役の座を競うように弾き合う。形式的にも自由度が高いだけに,堅苦しい演奏では作品の魅力が半減する。(14′00″)[I:4/II:4]
[第2楽章]スケルツォ Scherzo ホ長調 vivace:両者が戯れ合うかのように,リズムも旋律も極めて明朗。(4′30″)[I:4/II:4]
[第3楽章]イ短調 Largo espressivo:付点リズムの重々しい短い序奏の後,Iの左手による荘重な連打音に乗せて,両者が16分音符が連なる旋律を弾く。その旋律の動きは過度に感傷的ではなく抑制が利いている。(3′30″)[I:3/II:3]
[第4楽章]牧歌 Pastorale イ長調 Allegretto espressivo:IIによって弾き出される旋律がカノン風に扱われる冒頭は,静かに吹き鳴らされるアルペンホルンの響きが山々に谺する,まさに牧歌的な風情だが,おもに使われる音符が8分音符の3連符~32分音符と細分化されるに従って,Iは急速なパッセージが鍵盤上を奔放に駆け回り,IIはギターのトレモロを模した音型が目立つようになる。IIの終り近くには,ジュリア一二の「24の練習曲 Op.48」の24番が使われている。それぞれの楽器の名手が優れた腕前を披露するための名技的で華麗な楽章。(10′00″)[I:5/II:4]

華麗なロンド Op.30
Rondo brillant[1814刊]
連弾(オリジナル)=Hofmeister
★イ長調 Allegretto:楽しい旋律が転調を伴って次々と現れる快活な作品。冒頭の主題がとてもユーモラス。Pは急速に,そして流暢に動き回る箇所が多く,Sは伴奏が中心だが,主題や対旋律を弾く機会もある。P.11のPの下段のテープの修復で隠された部分は,恐らく休符であろう。Pはかなり高い音域に達し,それが作品の輝かしさを増している。(7′40″)[S:4/P:5]

トリオ付きの6つのワルツ Op.33(全6曲)
6 Walzes avec trio[ ? ]
連弾(オリジナル)=Artaria
★モシェレスによる易しい教育的作品の好例。技術的に易しく,優美で落ち着いた雰囲気の旋律は変化に富み,Sも伴奏を担うばかりでなく旋律を弾く機会もある。8小節や16小節等の各フレーズは反復され,曲尾にD.C.は書かれていないが,「トリオ」の後,冒頭に戻り(フレーズの反復なしで),「トリオ」の前で終わるのが一般的であろう。
[1]ハ長調:トリオの後半はイ短調に転調してハ長調に戻る。(1′40″)[S:1/P:1]
[2]へ長調:1曲目よりも旋律の動きもリズムもやや複雑になる。主部の力強いファンファーレと二短調のトリオの繊細な旋律の対照や,トリオでのPとSとのカノン風の動きが興味を引く。(2′45″)[S:2/P:1]
[3]変口長調:トリオはP,Sによるffの和音と,弱音の優美な旋律が交互に現れる。(2′15″)[S:2/P:2]
[4]卜短調:熱情的で鬱屈した主部を持ち,卜長調のトリオの伸びやかな民謡風の旋律が印象的。トリオの中間部,Sが旋律を弾く二長調の箇所でのSのオルゲルプンクトとPの右手による長いトリルが実に効果的。(2′40″)[S:1/P:2]
[5]ホ短調:これまでの4曲と比べ,急に時代が前に進んだ感があり,甘美でメランコリックな曲想はいかにもロマン派の小品らしい。ホ長調のトリオでの半音階的進行と,PとSとの対話がおもしろい。(4′50″)[S:2/P:3]
[6]ハ長調:旋回するような華やかな旋律の主部を持つ。トリオでは力強くファンファーレが鳴り響く。(3′40″)[S:2/P:3]

大二重奏曲 Op.35(4楽章)
Grand Duo[1815]原曲 室内楽曲
2台ピアノ(編曲者不明)=Hofmeister(I・II分冊)
連弾(自編)=Hofmeister
★「ピアノ六重奏曲」の編曲で,2P版は原曲のピアノ・パートをIとして,他の楽器のパートをIIに編曲したもの。当然,2P版のほうが原曲への忠実度は高いが,連弾版も音域的な制限のために旋律線を変えたり,オクターヴを単音にした箇所が一部にあるものの,ほぼ原曲に忠実。PとSとのリズム上の噛み合わせが面白い部分もあるが,やはりSは伴奏的な動きが多い。
[第1楽章]変ホ長調 A11egro con spirito:清々しくおおらかな明るさと軽快な運動性を持つ。同一のモティーフの反復箇所が多く,畳み掛ける迫力を持つ反面,冗長感は否めない。ホ長調の部分でのテンポの変化は連弾版のみに見られる。(12′15″)[I:4/II:4][S:3/P:4]
[第2楽章]メヌエット Menuetto ハ長調 Molto moderato:主部は厚い和音とffが多用されて力強く進行する。原曲ではチェロとホルンが,2P版ではIIが旋律を奏するヘ長調のトリオでは,終り近くの同一リズムの反復が極めて魅力的。この楽章では,IとSの右手は連続する16分音符によって和音を充填する箇所が多く,その流れをニュアンス豊かに,同時にうるさくないように弾く必要がある。表記の演奏時開が長いのは各部の反復が多いため。(7′00″)[I:3/II:2][S:2/P:2]
[第3楽章]変イ長調 Adagio:原曲でもピアノによる,特徴ある印象的なトレモロの序奏部に,情緒纏綿とした素晴らしい旋律が続く。この旋律を連弾版では両者が手を交差させてオクターヴ離れたユニゾンで弾く。2P版でははじめはIIが担当するが,後半の細かい装飾的な動きはIの担当。次の楽章に続く。(5′40″)[I:3/II:2][S:2/P:3]
[第4楽章]変ホ長調 Allegro non troppo:音階的な動きを多く使った旋律が続く明るく軽快で優美な楽章だが,同じ音型の連続が多く,提示部の反復を省略してもいささか長い。特にPの右手には流暢な運動性が要求される。2P版では両者の掛合いが楽しい。(12′00″)[I:4/II:3][S:3/P:4]

大ソナタ Op.47(4楽章)
Grande Sonate[1853刊]
連弾(オリジナル)=Cranz
★20代前半の作品で,その当時は人気が高く,モシェレスは1839年にショパンとともにこの作品を演奏した。このCranz版は2~4楽章の一部がカットされた改訂版。モシェレスのデュオ作品は冗長と思える作品もあるが,この作品はカットなしでもまったく冗長さを感じさない。古典派の落ち着いたたたずまい,初期ロマン派の新鮮な抒情,溢れる熱気と迫力,そしてピアニスティックな華やかさを併せ持つ傑作。
[第1楽章]変ホ長調 A11egro spiritoso:晴れやかで堂々とした第1主題と旋律的でマーチ風の第2主題を持つ。第1主題に続いて,長調に変えられてはいるが,モーツァルトの「交響曲 40番」の冒頭の有名なモティーフが出現する。第2主題の魅力的な転調はシューベルトを予感させる。特にPとSの連携が緊密で,華麗でピアニスティックな演奏効果を発揮する,迫力に富む楽章。(11′00″)[S:4/P:4]
[第2楽章]卜短調 Andantino quasi allegretto:民謡風の主題に長調の技巧的な2つの変奏が続く。変奏に至る前の半音階的な下降が幻想的。伴奏の音が厚く,バランスには注意が必要。(4′45″)[S:4/P:4]
[第3楽章]ホ長調 Adagio:劇的な短い序奏に続き,Pが左手で安らぎに満ちた旋律を弾き始め,右手の旋律とデュエットとなる。楽譜に記された「四分音符=92」の指示は速すぎるように思う。次の楽章に続く。(2′40″)[S:2/P:2]
[第4楽章]変ホ長調 A11egro:力強さと軽快で素早い動きが特徴的な終曲。連打音による旋律がユーモラスであるとともに華やかさを増している。速度が上がるコーダは特に技巧的。(6′00″)[S:5/P:5]

美しい結合 序奏付きの華麗なロンド Op.76
La belle union Rondeau brillant précédé d'une introduction[1828頃刊]
連弾(オリジナル)=Probst
★Largo の序奏は短いが重々しいファンファーレの後,歌謡的な旋律が次第に緊張の度を高め,半音階的な下降を経て変へ長調を通って変ホ短調を準備する。そして両者の短いカデンツァ間に変ホ長調に向かい,Al1egretto grazioso のロンドが続く。主題は軽快で極めて優美なもので,変ハ長調のクープレは特に優しく甘美に響く。主題は調性や装いを変えて幾度も登場するので,作品としての統一感も強い。対位法的な部分も多く,PとSとの連携も極めて緊密で,Sもシンプルな伴奏は少なく多くの技巧的な見せ場を持つ。迫力あるストレットで緊迫した後,ハ長調の室内楽的な部分でテンポを落として落ち着くが,その後はヴィルトゥオーゾ的に盛り上がって終わる。両者の,特にPの右手には軽快で急速な動きが要求される。(12′00″)[S:5/P:5]

協奏的二重奏曲 ヴェーバーのメロドラマ「プレチオーザ」のジプシーの行進曲による華麗な変奏曲 Op.87b
Duo Concertant Variations brillantes sur la marche bohémienne tirée du mélodrama Preciosa de C.M.de Weber[1833]
2台ピアノ(オリジナル)=Kistner(I・II分冊)
連弾(オリジナル)=Schlesinger
★ハ短調 Andante maestoso ハ長調 Allegretto:メンデルスゾーンとの共作で,ヒンソン(Hinson)によれば序奏と第1,2変奏はメンデルスゾーンが,第3,4変奏はモシェレスが作曲し,終曲は2人による合作。2台のピアノとオーケストラのための版もあり,2P版の表紙には「任意のオーケストラ付き」と書かれ,オーケストラの部分の音符には各楽器名も記されている。ハ短調の序奏は複付点音符の和音により重々しく始まり,いかにもメンデルスゾーンらしい感傷と情熱とに満ちた旋律をIが,あるいはPが担い,明るく軽快なハ長調の主題に続く。第1変奏は2人が素早い動きのパッセージを華麗に弾き合い,IIが主役の第2変奏は,分散オクターヴによるハ短調の情熱的なもの。再びハ長調となる第3変奏はIが主役となり,重音やオクターヴによる軽快な動きを披露し,第4変奏はテンポを落として前半は音階的な動きを弾き合い,次第に高揚して Allegro vivace の名技的で華麗な終曲に続く。連弾版は2P版の音をわずかに簡略化してあり,また2P版の第1変奏では特にIIが広い音域を弾くのに対し,Sのアクロバティックな奏法を避けるために狭い音域の動きに変えている。両版はアーティキュレーションや強弱記号も微妙に変えられ,反復の箇所も同じではないが,大きな違いは終曲で,小節数でほぼ3/4に縮小され,登場する主題も異なるが,決して簡略化ではなく,むしろヴァリアンテの性格が強く感じられる。両版ともに華麗で輝かしく,ピアニスティックで名技的な演奏効果を発揮する。(16′20″)[I:5/II:5],(15′00″)[S:4/P:4]

序曲 オルレアンの少女 Op.91
0uverture Die Jungfrau von Orleans[1835刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Kistner
★へ長調:シラーのロマン的悲劇による。序奏は2段構えで,まずへ長調,Andante religioso で平静に始まるが,しだいに短調へ傾斜し,悲しみと不安の度が増すと,Tempo di marcia, moderato の部分に入る。この部分もヘ長調だが,やはり短調への傾斜と減七の和音の多用で緊迫感が強まる。続く Allegro spiritoso の主部は,それまでとはまったく対照的に明朗で活力に満ち,ハ長調の流麗な第2主題も魅力的な上,ピアノでも効果的。その後,行進曲の部分と主部が再現されるが,最後は序奏のはじめの部分がヘ短調の葬送行進曲となって現れ,無垢な魂が天上に召されるように上昇するトレモロによって終わる。P・S間の連携が緊密で,また多様でもあり,両者の掛合いの機会も多く,曲の内容も変化に富む上に,気高い雰囲気がある。(10′00″)[S:4/P:4]

ヘンデルを称えて Op.92
Hommage à Händel[1822]
2台ピアノ(オリジナル)=Steingräber
★卜短調 Andante patetico ト長調 Allegro con fuoco:1822年,クラーマーが「ソナタ」の第1,2楽章をモシェレスに見せ,終曲に相当する楽章の作曲をモシェレスに依頼した。それに応えてモシェレスが急いで作曲した楽章を加えた作品が,同年の5月9日にロンドンで初演され,その後モシェレスはこの楽章に序奏部を加えて独立した作品,「ヘンデルを称えて」とした。序奏部は,フランス風序曲的な複付点リズムの重厚さと甘美な和声が絶妙に融合されている。主部はヘンデル風の力強い晴れやかさに満ち,序奏にも登場する旋律がさまざまな調で展開され,その疾走感が素晴らしく魅力的。作品はチェルニーに献呈され,モシェレスはこの作品をメンデルスゾーンとも演奏しており,昔日の巨匠たちの共演にふさわしい華麗な傑作。(12′00″)[I:4/II:4]

お伽話 Op.95-5
Un conte d'enfant[1893刊] 原曲 ピアノ独奏曲
連弾(編曲者不明)=Armand Colin
★変ホ長調 Allegretto grazioso:IMSLP のファイルに作品番号等の記載はないが,
「12の新しい性格的大練習曲 Op.95」(1836作)の5曲目の編曲。この「練習曲集」はシューマンによって高く評価された。原曲は,おもに右手の3~5指で明るくさわやかな旋律を弾きながら,1~3指で敏捷,軽快に内声のロマンティックな和音を充填する練習曲。この編曲は旋律やバスの一部をオクターヴ化した以外は原曲に忠実で,2手用の音符を4手に配分したため。原曲の難しさは大きく軽減されるが,Pの両手とSの右手は接近しがち。原曲もこのタイトルを持ち,メカニカルな練習曲ではなく完全にロマン派の性格的小品。(3′10″)[S:3/P:3]

ヴェーバーを称えて オイリアンテとオベロンの動機による大二重奏曲 Op.102
Hommage à Weber Grande duo sur des motifs d'Euriante et d'Oberon
[1842刊]
連弾(オリジナル)=Kistner
★ヴェーバーの歌劇,「オイリアンテ(以下E)」と「オベロン(以下O)」のさまざまな動機に基づく華麗なショー・ピースだが,歌劇の有名な旋律を単にピアニスティックに飾り立てた作品ではなく,動機を展開したり,2つの動機を同時に使い,また「大二重奏曲」の名の通り,Sにも旋律を担当させるだけでなく両者の手の交差も用意されている。全体は,大別すると続けて演奏される5部から構成され,各部のテンポも急-緩-急-緩-急と変化に富む。冒頭はEの「序曲」や両オペラの有名な旋律が使われ,輝かしく活気に満ちた序曲的な性格を持ち,続く第2部はEのアドラーの甘美なロマンツェ,「花咲く巴旦杏(はたんきょう)の下で」が実に豪華に,そしてピアニスティックに装飾され,最後はOのレチア姫の躍動的な歓喜の旋律で豪壮に幕を閉じる。颯爽と弾くにはP,Sともに高度なテクニックが必要。Eの1幕の最後,王女オイリアンテの「楽しい調べ」に基づく第4部(約2分)は省略も可。(14′10″)[S:5/P:5]

交響的大ソナタ Op.112(4楽章)
Grande sonate symphonique[1846刊]
連弾(オリジナル)=Schlesinger-Brants
★タイトル通り,交響的な偉容と響きを特徴とする大ソナタで,全曲の演奏時間は30分を越える。"The Piano duet"の中でルービン(E.Lubin)は「大ソナタ Op.47」とともに高く評価しているが,「Op.47」と比べるとピアニスティックな要素が少なく,技術的にも難しいだけでなく,変化を伴うものの同一フレーズの反復と新たに展開される楽想が多く,まとまりがなく冗長になりがち。 P,S間の,特にリズム的な連携が非常に緊密に書かれているが,説得力のある演奏のためには,デュオとしての極めて高度な実力が必要。
[第1楽章]口短調 Andante patetico Allegro agitato:トレモロと付点リズムによる重々しく,かなり長い序奏は転調と曲想の変化を経て,6/8拍子の主部に続く。主部は軽快な騎行するリズムに始まるが,主題や経過句はオーケストラ的な性格が強い。コーダは極めてピアニスティックで迫力に富む楽章。(10′30″)[S:4/P:4]
[第2楽章]二長調 Andante espressivo:Sの多彩な伴奏に乗せて,Pが付点リズム による息の長い旋律を弾く。この旋律は,時にはSも担当するが,転調やテンポの変化を伴いながら,無限に続くかのよう。非常に美しいが,飽きさせないように弾くのは難しい。(6′30″)[S:4/P:4]
[第3楽章]卜長調 Allegretto Scherzoso alla tedesca antica:「古いドイツ舞曲 風に」の指示だが,無骨な曲想ではなく,繊細な動きを持つだけに軽快に弾くのは技術的に難しい。より流麗な舞曲風のトリオを持つ。 P,Sともに頻出する両手の重音を滑らかに弾く必要がある。(4′30″)[S:4/P:4]
[第4楽章]終曲への序奏 Introduction al finale Andante patetico tempo I,終曲 Finale 口短調 A11egro con brio:[第1楽章]の序奏が回想され,コラール風の主題も堂々と登場する。「終曲」は大胆なリズムで力強く始まり,「序奏」のコラール風の主題から派生して更に拡大された主題も登場し,まさに雄大なスケールの「交響曲」の感が強まる。技術的にも極めて難しい。(10′00″)[S:5/P:5]

滑稽な変奏曲,スケルツォと祝典行進曲 Op.128
Humoristische Variationen Scherzo und Festmarsch[1856]
連弾(オリジナル)=Kistner
★二長調:「メヌエットのテンポで」と指示された主題は付点リズムを多く含み,急激な強弱の変化が滑稽感を高めている。第1変奏はPとSとのリズミカルな対話が続き,第2変奏は半音階的な和声の上に連打音による旋律が乗る。ト短調の第3変奏は熱気に満ちて粘着質。再び二長調の第4変奏はオクターヴによる付点リズムで堂々とした進行で始まるが,しだいに穏やかさを増して収まり,「スケルツォ」に続く。この部分はそれぞれが2ページ半の短いもので,3拍子の明快で歯切れの良い主題,2拍子の軽快でやはり歯切れの良い主題,そして「変奏曲」の主題が交互に登場する独特なもの。後半は3拍子の主題が旋律的に拡大され,ファンファーレが鳴り響く活力に満ちた「祝典行進曲」に入る。ここでは幅広い和音が頻出し,その迫力と前進力,そして高音域を駆使した輝かしい響きが取り柄。「変奏曲」と「スケルツォ」はP・S間のフレーズのやり取りの機会が極めて多い。(14′30″)[S:4/P:4]

踊り シラーの詩による性格的小品 Op.129
Der Tanz Charakterstück nach Shiller's Gedicht[1858]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★ニ長調 Allegro vivace:輝かしく短い序奏の後,6/8拍子の活力に満ちた渦巻くような旋律が現れ,途中に少しテンポを落とす箇所もあるものの,終始,快適なリズムで前進する開放的で楽しい小品。Sも伴奏ばかりでなく,快活な旋律を弾く。楽譜の表紙には「2手版がオリジナル」との表記があるが,アルトマン(W.Altmann)の目録ではオリジナル連弾作品に分類されている。(4′30″)[S:3/P:3]

ドイツ民謡による交響的英雄行進曲 Op.130
Symphonisch-heroischer Marsch über deutsche Volkslieder[1860刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Kistner
★卜長調 A11egro moderato:1797年に初演されたハイドンの歌曲「神よ,皇帝を護りたまえ」(弦楽四重奏曲「皇帝」の第2楽章の主題にも使われ,一時はオーストリア国歌となり,現在のドイツ国歌としても使われている)の有名な旋律が,重厚,華麗に展開される。この旋律はハイドンによる完全な創作ではなく,クロアチア北部の民謡に基づいている。音が厚い編曲で,Sも旋律を弾く機会があり,Pとの連携も緊密。(6′30″)[S:3/P:3]

かわいいおしゃべりさん Op.142-1
Die Kleine Schwätzerin[1900刊]
★変ロ長調 A11egretto grazioso:「3つの性格的な連弾曲」の第1曲。Pによるスタッカートの明るく軽妙な旋律が,いかにも小さな子供の楽しい「おしゃべり」のよう。Sが滑らかな旋律を弾く箇所では,Pはやはりスタッカートによる「合いの手」を入れる。(3′15″)[S:3/P:3]

モシュコフスキ Moszkowsky,Moritz(1854~1925)ポーランド

- ■ワルツ集 Op.8(全5曲)
Walzer[1875] - ■3つの小品 Op.11(全3曲)
Drei stücke[1876] - ■4つの連弾小品 Op.33(全4曲)
Vier vielhändige Klavierstücke[1883] - ■組曲 第1番 Op.39(全5曲)
Première suite[1886刊] - ■2つの小品(行列とガヴォット)Op.43(全2曲)
Deux morçeaux(Cortège et Gavotte)[1887] - ■たいまつの踊り Op.51
Fackeltanz[1893刊] - ■万華鏡 Op.74(全7曲)
Kaleidoskop[1904] - ■先生と生徒 Op.96(全8曲)
Le maître et l'élève[1920]
ワルツ集 Op.8(全5曲)
>Walzer[1875]
連弾(オリジナル)=Peters
★全5曲がワルツでありながら,各曲の曲想は極めて変化に富む。明かるさの中にも,あちらこちらから甘美な憂愁が浮かび上がり,初期の作品ながらいかにもモシュコフスキらしい魅力を備えている。
[1]イ長調 A11egro moderato:4手による幅広い和音の,輝かしく堂々として祝祭的な響きで始まる。対照的に中間部の旋律は柔和で優美。[2′30″](S:2/P:3)
[2]イ短調 Pesante e lugubre:Pの左手とSの右手により,オクターヴ離れたユニゾンで弾かれる憂愁に沈んだワルツが3回登場する。このワルツの旋律は半音階的に下降するもので,3回はそれぞれf,mp,ppと指示され,それらの適切な表現が肝要。その間に挟まれて2度,より感傷的なワルツが奏されるが,ここではSの右手による,やはり半音階的に下降する対旋律が印象的。両者ともに弱音の精妙なコントロールが要求される。[2′20″](S:2/P2)
[3]ホ長調 A11egro grazioso:Pが弾き出す軽妙な旋律を,1小節遅れてSが追い掛けるカノンによるワルツ。こうした技法によりながらも曲想はあくまで優美で洗練されていて,モシュコフスキの優れた作曲技法を示す好例。中間部の旋律の民族的な色合いも味わい深い。Pの両手はオクターヴ離れたユニゾンの動きが多く,左手にも素早い動きが要求される。[3′00″](S:3/P:4)
[4]ト長調 vivace assai:活力に満ちた華麗なワルツ。主部のワルツの3拍目のアクセントが,一層活気を増す。[2′00″](S:1/P:3)
[5]二長調 Pomposo ed energico,ma non troppo allrgro:4小節のファンファーレに,Sの厚い和音上のPによる直線的に屈折した儀式張った旋律が続く。流れるように優美で柔和なヘ長調の中間部を持ち,Sのトレモロで堂々と全曲を締めくくる。Pは両手のオクターヴ離れたユニゾンの動きが多く,重音を多く含むので,左手にも器用さが必要。[3′00″](S:3/P:4)

3つの小品 Op.11(全3曲)
Drei stücke[1876]
連弾(オリジナル)=Hainauer
★3曲とも異なる舞曲のリズムを持ち,連弾作品としては「ワルツ集 Op.8」と有名な「スペイン舞曲集 Op.12」の間に位置するが,それら2作と比べ,やや大掛かりで技術的にも難しく,凝った作風を示す。
[1]ポロネーズ Polonaise 変ホ長調 Brioso ed energico:Sによる伴奏はオクターヴのバスと厚い和音が多用されて力強く進行し,Pの旋律はオクターヴ離れたユニゾンによって活力と迫力に満ちている。ロ長調のトリオではバスや和音の動きも,そしてリズムも凝ったもので,華麗な演奏効果を発揮する力作。[4′30″](S:3/P:4)
[2]ワルツ Walzer ハ長調 A11egro grazioso:調性や曲想が異なる3つに区分されるワルツが続いた後,はじめの部分が再現されコーダが付されて終わる。前曲とは対照的に,薄く繊細な響きで,旋律も和声も極めてロマンティックで洒落ており,遠い過去を静かに回想するかのようなワルツが多く表れる。[6′20″](S:2/P:3)
[3]ハンガリー舞曲 Ungarischer Tanz ロ短調 Allegro con fuoco:Sによる伴奏の力強いリズム上に,Pが旋回するような急速な旋律を奏する,典型的なチャールダーシュ。[2′30″](S:3/P:4)

4つの連弾小品 Op.33(全4曲)
Vier vielhändige Klavierstücke[1883]
連弾(オリジナル)=Hainauer
★シューマンの「12の連弾小品 Op.85」と同じく,行進曲が1曲目に置かれるが,シューマンとは違い,2曲目以降が急激に難しくなる。これほど難易度の異なる作品群を曲集としてまとめた例も珍しい。
[1]子供の行進曲 Kindermarsch へ長調 Allegro:元気一杯で,また可愛らしい曲想が微笑ましく,PとSとの頻繁なリズム的応答が楽しい作品。曲集中,この曲のPにはオクターヴの和音が皆無(Sにはわずかにある)なのは,「子供の小さな手」が意識されているためであろう。[3′10″](S:2/P:2)
[2]フモレスケ Humoreske 二長調 Allegretto:おもにSによる伴奏部分のリズムのオスティナートが特徴で,Pによる旋律は伸びやかで明朗なもの。 con graziaからcon fuoco,pからff,スタッカートからレガートといった大きな振幅の表情の変化がユーモラス。[3′10″](S:3/P:4)
[3]タランテッラ Tarantelle ト短調 Allegro molto:ヴィルトゥオーゾ的で活気に満ち,Sも伴奏の和音を弾くだけでなく,対旋律を弾く機会も多い。ト長調の快活な中間部の後半では ff で豪快に盛り上がる。[4′30″](S:3/P:4)
[4]紡ぎ歌 Spinnerlied イ長調 Vivo:Pによる和音の上の音を繋げた軽快な旋律は,両手に分けて続けられるために,メロディ音とそれ以外の音のバランスも,旋律の自然で流暢な繋がりも非常に難しい。Sは無窮動的な16分音符の連続に終始する。スリリングなヴィルトゥオーゾ的難曲でありながら,その表情は優美と洗練の極み。[3′20″](S:4/P:5)

組曲 第1番 Op.39(全5曲)
Première suite[1886刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Hainauer
★美しく極めてピアニスティックな響きと管弦楽的な多彩さを併せ持つが,各曲が長く(特に1曲目は実質26ページで「ワルツ集 Op.8」全曲のページ数と同じ),連弾曲として効果的,印象的に聴かせる演出が難しい。優れたデュオによる「発掘」を待ち続ける「隠れた名曲」と言える。 IMSLPの「2台ピアノ用編曲」の表記は「連弾用編曲」の誤り。ミスブリントも散見されるが,IMSLPにはスコアもあり対照できる。
[1]へ長調 Allegro molto e brioso:全編が心地好い前進感に満ち,快活で力強い第1主題と流麗で極めてロマンティックな二長調の主題の対照が素晴らしい。波が寄せ返すようなゼクエンツ(反復進行)がロマンティックな陶酔感を高める。[9′00″](S:3/P:4)
[2]二短調 Allegro giojoso:2拍子の軽快なリズムの伴奏上に,スタッカートと半音階的進行を多用した繊細な旋律が奏される。一部に両者の手の交差もあり,Sは伴奏だけでなく歌謡的で息の長い旋律も担当する。"giojoso" は見慣れない発想標語(スコアも同じ)だが,"gioioso "の誤り?[6′10″](S:3/P:4)
[3]主題と変奏曲 Tema con variationi イ長調 Andante:原曲では木管群と弦楽器群によって開始される主題は,穏やかで粘性に富み,8つの変奏に続く。各変奏はテンポも性格も異なり,なかでもイ短調の第5変奏は「ハンガリー風 All'ongarese」と書かれ,劇的で躍動的なチャールダーシュであるのが,いかにも異国趣味の音楽を得意としたモシュコフスキらしい。続くへ長調の第6変奏は大きく性格を変え,「ノクターン」あるいは「ロマンス」といった風情となり,最後の第8変奏では回帰した主題が対位法的に一層豊かに処理され,しみじみと歌われて静かに終わる。[11′50″](S:3/P:4)
[4]間奏曲 Intermezzo イ長調 Allegretto con moto:主部は優雅な3拍子の宮廷舞曲のステップを思わせる。イ短調の中間部ではシンコベーションの和音上に感傷的な旋律が歌われてセレナードの趣。ここではSが多く旋律を担う。[5′30″](S:2/P:3)
[5]無窮動 Perpetuum mobile へ長調 Vivace:タイトル通り,ヴィルトゥオーゾ的なスピード感が特徴の軽快無比の爽快な作品。4手とも素早く軽快で精密な動きが要求される。[5′45″](S:4/P:5)

2つの小品(行列とガヴォット)Op.43(全2曲)
Deux morçeaux(Cortège et Gavotte)[1887]
連弾(オリジナル)=Peters
★2曲とも短調を基調とし,極めてピアニスティックであると同時に色彩的だが,寒色系の色合いが強い。演奏される機会は少ないが,まとまりが良く迫力に富む充実した傑作。「行列」には自身によるオーケストラ版もある。
[1]行列 Cortège イ短調 Allegro ma non troppo:スタッカートや連打音,半音階的進行の多用が冷たい感触を際立たせる一方,練習記号Cの少し前から滑らかな旋律が現れ,トレモロを伴って熱く盛り上がる辺りはヴァーグナーを連想させる。2つの主題の雰囲気の対照が実に見事で効果的。[5′15″](S:3/P:3)
[2]ガヴォット Gavotte イ短調 Moderato:スタッカートを多用した旋律は,冷たく取り澄ました表情だが,高音域の音が少なく,中・低音域での動きが多いので落ち着いた響きを持つ。イ長調の中間部ではSのオルゲルプンクト上に,Pが歌謡的な息の長い旋律を奏する。[4′50″](S:3/P:3)

たいまつの踊り Op.51
Fackeltanz[1893刊]原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Peters
★変ホ長調 A11egro molto moderato:Sによるバスも,Pの旋律もオクターヴの重複が多く,堂々とした響きの力強い舞曲で,そのリズムはポロネーズに似る。しかし細かな動きを持つ繊細な主題も多く,Sの左手からPの右手へと4手で弾き継ぐ旋律や,Sによる旋律もあり,PとSとの連携が巧妙なため,連弾作品として両者ともに弾いて楽しめる。コーダではSの左手によるトレモロを加え,華やかに,そして豪壮に終わる。[6′10″](S:3/P:4)

万華鏡 Op.74(全7曲)
Kaleidoskop[1904]
連弾(オリジナル)=Peters
★内省的で真摯な曲想,多彩でありながら繊細な響き,そして豊かな幻想に満ちた内容の濃い傑作。各曲はまったく異なる気分を持ち,それらの対照も素晴らしく,PとSとの連携も極めて緊密な魅力的な小品集。「ピアノ連弾のための細密画」のサブタイトルを持つ。
[1]変ホ長調 Molto Allegro e con fuoco:Pによる滑らかに上昇して曲線を描く旋律は,やはりSによる旋律的な動きの伴奏に支えられる。中間部の旋律は連打音が特徴だが,主部に戻る箇所のスケール豊かな広がりは比類がない。熱気に溢れて盛り上がり,堂々と曲を閉じる。[1′30″](S:3/P:4)
[2]ト短調 Presto:Sによる軽快な伴奏に乗って,アルペッジョで下降するPによる繊細な旋律は「木の葉の舞い」を連想させる。[1′10″](S:3/P:4)
[3]二長調 Andante:「ロマンス」風の豊かな抒情と幻想に満ち,「『スペイン舞曲集』の作曲家」のイメージを一新する傑作。すべての声部が「歌」による対位法的な作品だけに,表情豊かに滑らかに弾き切るのは至難。[2′30″](S:3/P:4)
[4]嬰へ短調 Allegro moderato e grazioso:憂愁を含んだ旋律を持ち,短調と長調の間を微妙に移ろう。ボレロのリズムが明瞭となった後にSのソロが置かれる。嬰へ長調に転調するが消え去るように終わる。[3′00″](S:3/P:4)
[5]口長調 Allegro con spirito:連打音を多く含む,スタッカートによる軽快な旋律を持つ。[2′20″](S:3/P:4)
[6]ホ短調 Mesto:単なる感傷を越える悲痛なマズルカ。反復が多く,飽きさせない演奏には演出上の工夫が必要。[3′15″](S:3/P:4)
[7]イ長調 Tempo di Valse:優美を極めたワルツ。凝った転調やリズムの変化が興味深い。[2′20″](S:3/P:4)

先生と生徒 Op.96(全8曲)
Le maître et l'élève[1920]
連弾(オリジナル)=Enoch
★S(生徒)は,全曲で固定された一つのポジションの5つの音のみでバスを弾く教育的作品で,その動きはオクターヴ離れたユニゾンか,片手のみに限られる。一方P(先生)にはペダル指示があり,旋律とほとんどの曲で多声的な動きによる伴奏部を弾く。Sの音だけからは想像を越えるほど充実した魅力的な小品集となっている。い
[1]前口上 Prologue:ハ長調 Allegro brioso:Sはいかにも「指の練習」的な音の動きで始まる。明朗な曲想の堂々とした響きの小品。[1′45″](S:1/P:3)
[2]楽興の時 Momento musical ハ短調 Molto Moderato:哀しく,また優しい歌。Pは3声の動きがかなり複雑。[1′20″](S:1/P:3)
[3]メロディ Mélodie 変ホ長調 Allegro Moderato:シューマン風の優しく繊細な抒情に満ちている。[1′45″](S:1/P:3)
[4]舞踏曲 Air de ballet 卜短調 Andante con moto:きびきびとした動きの主部とト長調の優美な中間部を持つ。[1′40″](S:1/P:3)
[5]アラベスク Arabesque 変口長調 Allegretto animato: 軽快なリズムの優雅な動き。16分休符で区切られる旋律は,宙を舞い飛ぶ感がある。[2′00″](S:1/P:3)
[6]子守歌 Berceuse 二長調 Andante:シンプルなバス上に,重音による柔らかな響きの旋律が歌われる。微妙な転調が魅力的。[2′15″](S:1/P:4)
[7]ワルツ Valse イ長調 Tempo Moderato:ゆったりとしたテンポの優雅なワルツ。薄明りの中に次第に消え去るかようなコーダが印象深い。[2′00″](S:1/P:3)
[8]タランテッラ Tarantella ハ長調 Molto vivace:力強く快活に進行する。曲集中,最もテンポが速いがPの伴奏は最も単純。[1′00″](S:1/P:3)

モスクワで生れ,モスクワ音楽院ではヴァイオリンをフジーマリーに,作曲をアレンスキーとタネーエフに,その後ベルリン高等音楽学校でバルギールに学ぶ。短期間,ロシアで教職に就いた後,1934年に健康を害して引退するまでの間,ベルリン高等音楽学校で教えた。3曲の「ヴァイオリン協奏曲」や2曲の「交響曲」などの管弦楽曲のほか,各種の室内楽曲も残した。生涯ロマン派の様式を守り,「ロシアのブラームス」とも呼ばれたが,ロシアとドイツが混合された作風は独特の個性的な魅力がある。弟のコンスタンチンは画家として知られる。
- ■舞踏のリズム集 Op.14(全7曲)
Tanzrhythmen[1900刊] - ■ソナタ Op.22a(5楽章)
Sonate[1902刊] - ■新舞踏のリズム集 Op.24(全5曲)
Neue Tanzrhythmen[1904刊] - ■舞踏のリズム集(第3シリーズ) Op.41(全5曲)
Neue Tamzrhythmen(Dritte Folge)[1908刊] - ■古い時代から Op.68(全5曲)
Aus alter Zeit[1918] - ■いつもいっしよ Op.75(全9曲)
Die Unzertrennlichen[1923刊]
舞踏のリズム集 Op.14(全7曲)
Tanzrhythmen[1900刊]
連弾(オリジナル)=Schlesinger
★以下の3集の「舞踏のリズム集」は,いずれも音が厚い書法でピアニスティックな演奏効果は極めて高い。曲想は親しみやすく,生き生きとしたリズムに溢れ,各曲は変化に富み,これまでほとんど知られていないのが誠に残念。
[1]嬰へ短調 Alla marcia:スラヴ的な哀調を帯びた旋律が,重厚な響きを伴って荘重に歌われ,曲集の序奏にふさわしい。前・後半とも反復される。[3′00″](S:3/P:3)
[2]ロ長調 Allegretto:Sによるリズミカルな伴奏上に,Pがユーモラスな民謡風の旋律を奏しつつ,次第に興奮を高める。Pの右手による分散オクターヴがピアニスティックで華やか。[2′05″](S:4/P:4)
[3]ホ短調 Tempo di Valse:力強く,激しい情熱が込められたホ短調のワルツが度々登場し,その間に2種の柔和なト長調のワルツが置かれた,いかにも後期ロマン派らしいワルツ。反復を省くと1分ほど短縮可。[4′30″](S:3/P:3)
[4]変ニ長調 Allegro:5拍子。Sによる軽快な伴奏上に,Pが同一のリズム・パターンを反復する,さわやかで軽やかな間奏曲といった風情。ソフト・ペダルが踏み通される。[1′10″](S:2/P:3)
[5]変ロ長調 Allegro molto-Meno Allegro:ユニゾンで雪崩れ落ちる短い序奏も,多数のシュネラーに彩られたワルツの旋律も気紛れな性格と華麗な効果に満ちている。中間部のSによる旋律は実に重々しい。[3′55″](S:3/P:4)
[6]変ト長調 Allegretto con moto:リズミカルで軽快な民俗舞曲風の作品。気楽で楽しげな旋律はPの両手によりカノン風に扱われ,まるで2人の踊り手による舞踏を見るよう。中間部は変ロ短調の主和音がSのトレモロにより弾き通される。[3′00″](S:2/P:3)
[7]二長調 Moderato:曲線的な旋律を持つロマンティックなワルツ。中間に登場するロ短調のワルツはスケール豊か。反復が多いが,多声的な書法によるため,各声部の強調等による変化が生かせる。[4′30″](S:3/P:3)

ソナタ Op.22a(5楽章)
Sonate[1902刊]
2台ピアノ(自編)=Schlesinger
★「ピアノ六重奏曲 Op.22」からの編曲。基本的には原曲に忠実で,原曲のピアノパートを一方のピアノに,弦楽パートを他方に配置したものだが,機械的な配分ではなく,音型や強弱の指示,オクターヴの付加や音域の移動など,細部ではかなり改変されており,オリジナル作品としての資格を備えている。響きが厚く,情熱と力感に満ちたロマン派の大曲。両者が同一の音域で動く部分も多く,バランスには注意が必要。
[第1楽章]ハ短調 Moderato:力強く情熱的。粘度の高い旋律にも和音にもオクターヴが多用され,響きは重厚。 3/2拍子,Moderato で悠然と進行する。多発する3度や6度の重音の進行がブラームス的。[13′15″](I:5/II:5)
[第2楽章]へ長調:Andantino quasi Allegretto のシンプルなロシア民謡風の主題による変奏曲。多くの変奏でIとIIの役割が交替される。第1変奏は主題にリズミカルで流動的な伴奏が加わり,第2変奏は対位法的な細かい動きの装飾的な伴奏を伴う。第3変奏は少しテンポが速まり,旋律は活発な舞曲風のリズムとなり,軽快で躍動的な伴奏を持つ。第4変奏はオクターヴの進行と連打和音を伴い,輝かしくピアニスティック。へ短調,Grave の第5変奏は重々しい歩みのフガート。[8′30″](I:5/II:5)
[第3楽章]メヌエット Menuetto へ長調:この楽章が,主部は第6変奏,トリオは第7変奏となるのが構成上の特徴。主部は軽快で歯切れ良い旋律と,短いトリルが頻繁に付加されたきらめくような対旋律を持ち,変ニ長調のトリオは息の長い流れるようなロマンティックな旋律を持つ。[4′00″](I:3/II:3)
[第4楽章]間奏曲 Intermezzo へ長調 Moderato piacevole:この楽章が第8変奏であり,オクターヴのユニゾンによる大胆な歩みの旋律と,両手によって交互に奏される幅広い和音による力強い伴奏を持つ。中間部では両者ともに3度重音による動きが続く。コーダで主題が重厚な響きで力強く回想される。[2′30″](I:5/II:5)
[第5楽章]終曲 Finale ハ短調 Allegro non troppo:精力的で活発な短い序奏に,流れるような軽快なリズムの第1主題が続く。第2主題は息の長い歌謡的なもの。厚い和音,広い音程の跳躍が多く,終始エネルギッシュに,熱気に満ちて展開される。重苦しくないよう,流暢に弾くためには高度なテクニックが必要。[9′30″](I:5/II:5)

新舞踏のリズム集 Op.24(全5曲)
Neue Tanzrhythmen[1904刊]
連弾(オリジナル)=Schlesinger
★全曲に拍子やリズム上のユニークな工夫が見られ,各曲が極めて個性的で魅力的。アンコール等にどの1曲を取り出しても効果的だが,曲集全体も各曲が多彩な変化に富み,全曲演奏は一層効果を高める。
[1]ハ長調 Allegro:8小節のフレーズは 1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,4/4,3/4,2/4 と1拍ずつ増え,また1拍ずつ減る変化を持つ拍子が反復される。誠にユニークでユーモラスな拍子とリズムながら,人工的な不自然さは一切感じられず,むしろ民族舞曲風の生き生きとした生命力が感じられる。滑らかで旋律的な部分やコラール風の部分も登場するが,各部の反復が多い。[4′10″](S:3/P:3)
[2]へ長調 Quasi valse lento:時折,2拍子の小節が挟まれるお洒落で優美なワルツ。Pのためらうような動きの3度重音による旋律は,シンプルながらも過去を懐かしく回想するかのよう。イ短調の中間部のPによる急速に旋回するような旋律は,「疾走する憂愁」といった風情。続いて両者が手を交差させながらSがその旋律を担うと,Pは優美な対旋律を加え,次にその役割は交替される。甘美で素晴らしく洗練された魅力的な作品。[2′20″](S:3/P:3)
[3]ロ短調 Allegro non troppo:7拍子による作品。曲集中,最大の作品だが八分音符によるグルーピングは,3+2+2(歯切れ良く活発な主部),2+3+2(ト長調の牧歌的な部分),2+2+3(ホ長調のファンファーレ風の部分)と変化に富む。主部でのPの両手はオクターヴ離れたユニゾンの動きが多いため,左手にも素早い動きが要求される。ロ長調のファンファーレ風のコーダで輝かしく終わる。[6′45″](S:4/P:5)
[4]変ホ短調 Allegretto: 2/4,6/8,3/4,5/8拍子の変化が反復され,Sによる鈴を嗚らすような八分音符の一貫したリズム上に,ほとんど第7音を欠き,時に第4音が半音上げられる音階による旋律をPが奏する。その旋律やリズムは中近東~中央アジアあたりの民族音楽の雰囲気で,効果的な装飾音も異国情緒を盛り上げる。中間部は同じ旋律が変卜長調で極めてロマンティックに和声付けされており,前後の部分との対照をより際立たせている。[2′30″](S:3/P:3)
[5]ハ長調 Moderato:5/4 拍子の落ち着いた主題とそれに続く6つの変奏。第3変奏まで,次第にロマン的情緒と流動性を増し,快活で力強い A11egro molto の第4変奏の後,一転してへ短調,Adagio,5/1(!)拍子の暗い情緒に満ちた第5変奏では,バスに置かれた主題が引き伸ばされて奏される。最後の第6変奏はハ長調,Vivace。冒頭のバスが再登場し,活発な民族舞曲がPのグリッサンドを交えて輝かしく展開され,Sのトレモロ上で壮麗に終わる。各変奏の流れと変化が素晴らしく効果的で,聴く者を飽きさせない。[6′00″](S:4/P:4)

舞踏のリズム集(第3シリーズ) Op.41(全5曲)
Neue Tamzrhythmen(Dritte Folge)[1908刊]
連弾(オリジナル)=Schlesinger
★上記の2集と比較して,各曲の個性がより際立ち,Sも旋律的な比重が高まっている。
[1]卜短調 Risoluto:力強く,しかも鬱屈した雰囲気の主部と,変口長調の明朗な中間部を持つ。主部では8分の4,5,6,3と頻繁に拍子が変わり,Pには両手ともに3度重音の動きが頻出。2拍子のリズミカルな中間部ではSにも旋律を弾く機会がある。[3′00′](S:4/P:5)
[2]ハ長調 Vivace molto:運動性に富んだ,甘美で華麗なワルツ。時折,2拍子のフレーズが挟まれる。手を交差させながら,Sも旋律を弾く機会が多く,2拍子の中間部でも両者の旋律的,リズム的な掛合いが多い。[4′20″](S:3/P:3)
[3]イ長調 Allegretto grazioso:付点リズムが多用された軽妙な行進曲風。小品ながら旋律,リズムともにPとSとでユニゾンの動きが極めて多く,2人が「合わせる」ための高度な練習曲。[1′40″](S:3/P:3)
[4]踊る5度 Tanzende Quinten 変ニ長調 Tempo di Valse lento:全曲ソフト・ペダルが踏み通され,Pによる旋律は両手が5度の音程に保たれ,中音域より上の音が使われるため,繊細で密やかなオルゴール風に聴こえるユニークで魅力的な作品。Sによる伴奏も対旋律も極めて効果的。優美でロマンティック。[3′00″](S:3/P:4)
[5]悲劇的ワルツ Tragischer Walzer 変ロ短調 Appassionato:悲劇的な主要主題は,重厚な和音とグリッサンドのような急速な上行音階が織り込まれ,激しい情熱に満ちたもの。過去を回想するかのような長調の甘美な主題群は,緊張感を一層高める。華麗なカデンツァも置かれ,ヴィルトゥオーゾ的でスケール豊か。[6′05″](S:4/P:5)

古い時代から Op.68(全5曲)
Aus alter Zeit[1918]
連弾(オリジナル)=F.E.C.Leukart
★舞曲を連ねた古典的な「組曲」。曲想はいずれもロマンティックで親しみやすい。全体的に音が厚く,響きは多彩でリズムは生命力に満ち,各曲の対照も際立っている。楽譜はミスプリが散見される。
[1]ブーレ風ソナタ Sonata alla Bourreé ロ短調:タイトル通りソナタ形式で,キビキビと動く第1主題と二長調の滑らかな第2主題に,第1主題のモティーフがカノン風に扱われ,第2主題の3度重音の動きが加わる短い展開部が続き,その後に再現部が置かれる。リズミカルでスムーズな前進感の強い楽章。[4′05″](S:4/P:4)
[2]メヌエット Menuetto ト長調:柔和で優雅な曲想。対位法的な書法が多く使われ,9小節以降では対旋律のモティーフが4手に次々に現れ,連弾の魅力が満喫できる。ハ長調のトリオはSのオルゲルプンクト上で展開される両者によるカノン。[4′40″](S:2/P:2)
[3]シャコンヌ(バッソ・オスティナート) Ciacona(Basso ostinato) ホ短調 Andante:3/4 拍子の10小節の低音旋律がユニゾンで重々しく提示され,5つの変奏が続く。第2変奏まで和声の豊かさと音量を増して悲劇的に展開され,第3変奏では一転して弱音でリズムも流麗となり,第4変奏では 9/8 拍子の軽妙で前進的なリズムによるカノンとなる。ここでは低音旋律は拍で数えて2倍に引き伸ばされるが,更に4/4 拍子の第5変奏では小節で数えて4倍に引き伸ばされ,明確な旋律を欠くものの,緩いトレモロによる和声の動きが次第に上昇しつつ幾度かの長い cresc.を経てppからffに至ると,長いdimin.により再びppに収束し,次の楽章に続く。和声は暗いが,時折の(短)2度の響きが刺激的で,時に陶酔的なまでにロマンティック。[5′15″](S:3/P:3)
[4]タンブラン Tambourin ホ長調:Pの右手により,澄んだ響きの明るい旋律がリズミカルに奏される。軽快なリズムは活力に満ち,頻出する滑らかな5連符が旋律の躍動感と流動感を増す。Sは左手でドローンを奏し続けるが,後半には効果的な対旋律を弾く機会もある。最後に「シャコンヌ」の一節が出現して陰鬱に終わる。[1′30″](S:1/P:3)
[5]ガヴォット Gavotte ロ短調:スタッカートが多用された主題は軽快だが,哀調を帯びたスラヴ風の雰囲気が強く感じられる。ト長調~ホ短調の滑らかな主題をPが奏する間,Sの伴奏もメロディアスな動きとなる。重厚な和音を伴って堂々と終わる。[4′55″](S:2/P:3)

いつもいっしよ Op.75(全9曲)
Die Unzertrennlichen[1923刊]
連弾(オリジナル)=Schlesinger
★はじめの2曲では,Pは両手でオクターヴ離れたユニゾンの旋律を弾き,極めて易しい教則本風に始まるが,徐々に典型的なロマン派の連弾小曲集の趣となる。終わりの2曲以外はP,Sともに調号を使わず,臨時記号を使用。
[1]おはよう Guten Morgen ハ長調 Moderato:穏やかな曲想。Pは6音を使用。ポジション移動は2回だけ。[0′45″](S:1/P:1)
[2]おやすみ Gute Nacht イ短調 Lento:深刻なエレジー風で悲痛。Pの音域もやや広がり,ポジション移動の回数も増える。[0′50″](S:1/P:1)
[3]春の踊り Springtanz ハ長調 Allegretto:フレーズが3小節等,不規則なため新鮮で生き生きとした感じが強まる。アーティキュレーションも急に難しくなり,前2曲と異なり,超初歩的ではない。[0′35″](S:1/P:1)
[4]メヌエット Menuetto 卜長調 Vigoroso:優雅さよりも快活な明るさが際立つ。ハ長調のトリオではSが力強い旋律を弾く。[1′20″](S:1/P:1)
[5]忘れな草 Vergissmeinnicht ホ短調 Moderato:感情の起伏は大きい。Pには両手の独立した動きも登場する。[1′00″](S:1/P:1)
[6]レントラー Ländler ハ長調 Con energia:Pの旋律に装飾音も登場する。中間のへ長調への転調のあたりは,極めてロマンティック。[1′15″](S:1/P:1)
[7]タランテッラ Tarantella イ短調 Allegro:Pは大部分で両手でオクターヴ離れたユニゾンの快活な旋律を弾く。見開き4ページとなり,大きく盛り上がって終わる。[0′55″](S:1/P:1)
[8]五月祭 Maitag へ長調 Moderato:この曲から調号を使用。Sの右手による八分音符の和音の「刻み」に乗せて,Pはテヌート記号が多用されたロマンティックな旋律をたっぷりと歌う。[1′25″](S:1/P:1)
[9]一列縦隊 Im Gänsemarsch ニ短調 Allegro non troppo:Pが先行する歯切れ良く活気に満ちた主題によるカノン。途中,変ロ長調の滑らかな新たな主題からSが先行する。和声を充填する自由な声部を持ち,息の長い cresc. を経て力強く終わる。[1′45″](S:3/P:3)

レスピーギ Respighi, Ottorino(1879~1936)イタリア

- ■ローマの噴水
Fontane di Roma[1916] - ■ローマの松
Pini di Roma[1924] - ■リュートのための古風な舞曲とアリア 第1組曲(全4曲)
Antiche Danze ed Arie per Liuto I Suite[1917] - ■リュートのための古風な舞曲とアリア 第2組曲(全4曲)
Antiche Danze ed Arie per Liuto II Suite[1923]
ローマの噴水
Fontane di Roma[1916]
原曲 交響詩
連弾(自編)=Ricordi,出版情報:プリズム社より「レスピーギ ピアノ連弾作品集」として「ローマの噴水」「ローマの松」「リュートのための古風な舞曲とアリア 第1組曲」を所収。全てスコア形式。
★原曲はレスピーギの代表作の「ローマ三部作(噴水,松,祭り)」の第一作で,色彩豊かな管弦楽法と印象派風の曲想が特徴。連弾でも十分に色彩的,効果的で演奏される価値は十分あり,レスピーギ自身とカゼッラによる連弾演奏の録音も残されている。下記の4部から成り,続けて演奏される。編曲は原曲にほぼ忠実なもので,原曲中のピアノの音型も効果的に取り入れられている。Sの左手にオクターヴ以上の音程の和音も現れるが,両者の手の交差もいかにも連弾曲的。基本的にスコアと同じテンポ指示だが,遅いものは特に工夫が必要。頻繁に調性やテンポ指示が変わるものはそれらの表記を省略した。
[1]夜明けのジュリアの谷の噴水 La fontana di Valle Giulia all' alba:原曲でトレモロ上で木管楽器によって静かに歌われる柔軟なリズムの旋律は,連弾でも効果的。[4′00″](S:4/P:4)
[2]朝のトリトンの噴水 La fontana del Tritone al mattino:軽快に飛び回るようなリズムと,輝かしいアルペッジョやグリッサンドが,朝の光にきらめく噴水を容易に連想させる。[3′00″](S:4/P:4)
[3]昼のトレヴィの噴水 La fontana di Trevi al meriggio:全曲が「英雄的に上行する単一のモティーフの反復とそれらの音色と装飾の変化」と言っても過言ではないが,連弾でも変化に富み,迫力も十分で雄大なスケール。途中,Pの2拍子とSの3拍子が同時に進行する。[3′30″](S:4/P:4)
[4]たそがれのメディチ荘の噴水 La fontana di Villa Medici al tramonto:原曲ではハープとチェレスタによる清澄な音色の伴奏上で,ノスタルジックな旋律が甘美に歌われる。トリルを交えた鳥の囀りも聞こえ,遠い鐘の音が鳴り響く中,すべては夜のしじまに消えて行く。各楽器によって奏される旋律はPとSとの対話になっていて,連弾としても楽しめる。[4′55″](S:4/P:4)

ローマの松
Pini di Roma[1924]
原曲 交響詩
連弾(自編)=Ricordi(スコア形式)
★原曲にほぼ忠実な編曲だが,総譜の音をできるだけ取り入れた編曲ではなく,連弾曲としての効果的な響きや弾きやすさを優先しており,「ローマの噴水」よりも省略の度合いは大きく,アーティキュレーションやデュナーミクも細部で微妙に変更されている。基本的にスコアと同じテンポ指示だが,遅いものは特に工夫が必要。頻繁に調性やテンポ指示が変わるものはそれらの表記を省略した。やはり下記の4部から成り,続けて演奏される。
[1]ボルゲーゼ荘の松 I Pini di Villa Borghese:17世紀にボルゲーゼ公によって作られたローマ市中心部にある名園で遊ぶ子供たち。コントラバスを廃した原曲の響きは誠に軽快で輝かしい。連弾でもピアニスティックで色彩感豊かで輝かしいが,P・Sともに生き生きとしたリズムで颯爽と弾くのは技術的にも非常に難しい。[3′00″](S:5/P:5)
[2]カタコンブ付近の松 Pini presso una catacomba:速い動きがなく,技術的には難しくないが,冒頭の弦楽器群とホルンとの荘重な対話をはじめ,ゆっくりとした旋律のニュアンスの表現と両者の「縦」の合わせは難しい。[6′30″](S:3/P:2)
[3]ジャニコロの松 I Pini del Gianicolo Lento:作曲者の解説によれば「満月をシルエットにして立つ松」。原曲のピアノのカデンツァも効果的に取り入れられ,柔軟なリズムによる,非常に美しく多彩な響きの印象派のピアノ曲に聞こえる。[6′50″](S:4/P:4)
[4]アッピア街道の松 I Pini della Via Appia 変ロ長調 Tempo di marcia:朝霧の中,朝日を浴びて遠くから行進してくる執政官の偉容を誇る軍隊の幻影。ppppで始まり ffffのクライマックスに至り,連弾でも迫力十分でスケール豊か。[4′40″](S:3/P:3)

リュートのための古風な舞曲とアリア 第1組曲(全4曲)
Antiche Danze ed Arie per Liuto I Suite[1917]
原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Ricordi
★もともとは16世紀のリュートのための舞曲や歌を,管弦楽用に自由に編曲した作品が原曲。原曲の1,2,4曲にはチェンバロが使われており,作曲者自身による連弾用編曲は原曲にほぼ忠実ながら,強弱記号や特にア-ティキュレーションが微妙に変更されていて,決して安直なものではないことが分かる。明晰なタッチと透明感のある響き,多彩なアーテ ィキュレーションが要求され,特にPの両手は接近しがちだが,古い音楽が逆に新鮮に感じられ,連弾曲としても効果的。なお,スコアにある数字による速度記号は連弾版にはない。
[1]小舞踏曲「オルランド伯爵」 Balletto detto "Il Conte Orland" ニ長調 AIlegretto moderato:S.モリナーロの作品に基づく。二部形式で第二部の前半はニ短調に転調されて反復される。スタッカートの付された主題は典雅な雰囲気で,その歩みは落ち着いたもの。[2′45″](S:3/P:3)
[2]ガリアルダ Gagliarda ニ長調 Allegro marcato:V.ガリレイ(著名な天文学者の父)の作品に基づく。ガリアルダ(ガイヤルド)は北イタリア起源の3拍子の速い舞曲。主部は原曲も連弾版もシンフォニックで壮麗な響きを持ち,ニ音のオルゲルプンクトを持つ Andantino mosso の中間部は柔らかな田園風。[3′45″](S:3/P:3)
[3]ヴィラネッラ Villanella ロ短調 Andante cantabile:作者不詳の16世紀末の作品に基づく。ニ長調の中間部を挟み,主部は悲痛な歌がゆったりと歌われ,後半はわずかな変奏を伴う。主部は合わせとバランスが非常に難しい。[5′20″](S:3/P:3)
[4]パッソ・メッゾとマスケラーダ Passo mezzo e Mascherada ニ長調 Allegro vivo - Vivacissimo:作者不詳の16世紀末の作品に基づく。「パッソ・メッゾ」ではキビキビとしたタッチと俊敏な指の動きが必要で,フレーズのP・S間の掛合いが多い。「マスケラーダ」では Allegretto の穏やかなものも含み,いくつもの快活な舞曲が登場し,トゥッティによるファンファーレで晴れやかに力強く終曲を締め括る。タイトルは「酔った歩みと仮面舞踏会」「パッソメッゾ舞曲と仮面舞踏会」の訳もある。[4′10″](S:4/P:4)

リュートのための古風な舞曲とアリア 第2組曲(全4曲)
Antiche Danze ed Arie per Liuto II Suite[1923]
原曲 管弦楽曲
連弾(自編)=Ricordi
★16~17世紀のイタリアとフランスのリュートのための舞曲や歌を,管弦楽用に自由に編曲した作品が原曲で,1,2,4曲にはチェンバロ連弾が使われている。連弾版もスコア同様,数字による速度記号を持ち,無論,一部の音の省略はあるものの編曲の忠実度は高い。技術的にはやや難しいが,親しみやすく変化に富み,明快な曲想と溌剌としたリズムを持ち,連弾曲として極めて効果的。
[1]優雅なラウラ Laure soave ニ長調 Andantino:F.カローゾによる舞踏組曲。落ち着いた旋律で始まり,溌剌としたガリアルダ,サルタレッロ,17世紀にフランスで流行した短い舞曲のカナーリオといった性格の異なる舞曲が続いた後,はじめの旋律がより柔和でロマンティックに回帰するが,この部分はPの両手の音の重複が多い。タイトルは「香り高い月桂樹」の訳もある。[4′00″](S:4/P:4)
[2]田園舞曲 Danza rustica ホ長調 Allegretto:J-B.ベサールの作品による。Sによるホ音とロ音の執拗でリズミカルな,いかにも民謡風の伴奏上に,Pによる,軽快なアーティキュレーションを施された旋律が奏される。それにはテトラコードや旋法風の音階が使われ,村の名人たちが次々に得意の楽器を披露する風情で,活気に満ちて誠に楽しく新鮮。[4′00″](S:4/P:4)
[3]パリの鐘・アリア Campanae parisienses - Aria ハ長調 Andante mosso - Largo espressivo:鐘の音を模した「パリの鐘」は作者不詳。中間部の,敬虔な雰囲気のゆったりとした3拍子の「アリア」は M.メルセスの作品。技術的に難しくはないが,合わせとバランスは非常に難しい。[5′30″](S:2/P:2)
[4]ベルガマスカ Bergamasca ニ長調 AIlegro:B.ジャノンチェッリ(通称ベルナルデッロ)の作品。北イタリア起源の舞曲で,生き生きとした旋律と快活なリズムに満ち,曲想は多彩でピアニスティック。2小節のバスの動きが執拗に反復される。[4′25″](S:4/P:4)

レントヘン Röntgen, Julius(1855~1932)オランダ

ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサートマスターのオランダ人ヴァイオリニスト,エンゲルベルトを父としてライプツィヒに生れ,9歳で作曲を始め,ラハナーに作曲を,ライネッケにピアノを学ぶ。1877年からオランダに移りアムステルダム音楽院の院長も勤め,ピアニストとしてもリサイタル,協奏曲,室内楽等のいずれにも頻繁に出演して高い評価を受けた。作風は後期ロマン派に属し,「ニュー・グローヴ」によれば21曲の交響曲,7曲のピアノ協奏曲,21曲の弦楽器のためのソナタを含む極めて多数の作品を残した。下記のピアノ・デュオ作品は,いずれも親しみやすくピアニスティック。
- ■少年時代より Op.4 第1集(全7曲)
Aus der Jugendzeit Heft1.[1873刊] - ■序奏,スケルツォ,間奏曲と終曲 Op.16
Introduction, Scherzo, lntermezzo und Finale[1876] - ■主題と変奏曲 Op.17
Thema mit Variationen[1878刊] - ■スケルツォ Op.33
Scherzo[1900刊]
少年時代より Op.4 第1集(全7曲)
Aus der Jugendzeit Heft1.[1873刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★ドイツ・ロマン派風の親しみやすく変化に富む小曲集で,全曲は3集20曲。1集の7曲は全曲で演奏時間約10分とやや短いが,内容的にはリサイタル用プログラムとしての資格が十分にある。
[1]献呈 Widmung ホ長調 Andante:Sによる波のようなアルペッジョの伴奏上に,Pがオクターヴ離れた両手のユニゾンでゆったりとした情緒豊かな旋律を弾く。 P,Sともに技術的には全く難しくはないが,深い情感と情熱に満ちた和声と旋律を表情豊かに合わせて弾くのは難しく,またそれだからこそ連弾の楽しみも味わえる。[1′45″](S:2/P:2)
[2]気軽 Leichter Sinn イ長調 vivace:軽快で素早い動きのワルツ。Pはオクターヴ離れた両手のユニゾンで旋律を弾くので左手にも器用さが必要。[1′00″](S:3/P:4)
[3]激烈 Ungesüm 嬰へ短調 Allegro con fuoco:Sによるアルペッジョ,Pによる旋律は1曲目と同様だが,曲想は全く対照的で切迫した激しい感情に満ちている。[1′05″](S:3/P:1)
[4]朝の挨拶 Morgengruss ニ長調 Allegro ma non troppo:SとPが歌い交わす爽やかで親密な挨拶。[1′15″](S:2/P:1)
[5]昔の舞曲 Alter Tanz ロ短調 Allegro:f のアウフタクトの直後に1拍目がp となるため,ためらうような風情がある。ガヴォット風の快活な舞曲で,Sが旋律を担当するロ長調の中間部での持続低音とPのドローンにはトルコ趣味が感じられる。[2′00″](S:3/P:3)
[6]お願い! Bitte! ト長調 Allegretto cantabile:シューマン風の親密な優しさ,穏やかさに満ち,Sの対旋律も魅力的。はじまりはベートーヴェンの「ソナタ Op.109」の冒頭を彷彿させる。[1′05″](S:2/P:1)
[7]若い喜び Jugentlust 変ホ長調 Leggiero,ma non troppo vivace:スタッカートが多用された旋律の弾むリズムにも,中間部の心踊る旋律の流動的なリズムにも,まさに「若い喜び」が溢れている。[1′50″](S:4/P:4)

序奏,スケルツォ,間奏曲と終曲 Op.16
Introduction, Scherzo, lntermezzo und Finale[1876]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★P,S間の連携が極めて緊密に作られ,役割の交替も頻繁にある。各楽章間の緩急や硬軟,緊張と弛緩の変化の振幅が大きく,深いロマン性と圧倒的な迫力,そして燃焼度の高さを備えたスケール豊かなリサイタル用の注目作。
[1]序奏 lntroduction 変ホ短調 Lento:滑らかな主題による3声のフガートの深刻な歩みで始まり,対位法的に荘重に展開される。Pの左手とSの右手によるオクターヴ離れたユニゾンの動きが多く,両者の表情を一致させる必要がある。次の楽章に続く。[2′45Prime;](S:3/P:3)
[2]スケルツォ Scherzo 変ト長調 Allegro molto vivace:明快で躍動的。 P,S間での短いモティーフの問答や掛合いが多いが,軽快なリズムの伴奏上の爽快で息の長い旋律も魅力的。夢見るようにロマンティックなトリオI,シンコペーションが特徴的で活発な民族舞曲風のトリオIIを経て,急速なコーダで熱狂的に終わる。[6′30Prime;](S:4/P:4)
[3]間奏曲 lntermezzo 変ロ短調 Allegretto un poco tranquillo:主部は16分音符による密やかで繊細な足取りで,短調と長調の間を滑るように移ろい,半音階的な下降が幻想を深める。対照的に中間部は激しい動きのスケルツォ風。変ホ長調の薄明りの中で終わる。[6′10Prime;](S:4/P:4)
[4]終曲 Finale 変ホ短調 Allegro, ma non troppo, un poco maestoso:複付点リズムを持つ悲槍で勇壮な行進曲風の主題と8つの変奏。主題の旋律は前・後半ともまずPに,次いでSに置かれる。続く変奏では,明暗や緩急の変化の妙を示しながら徐々に緊張感を高めて行く。静かでゆったりとした対位法的な動きの第7変奏で一旦,沈静化されるが,第8変奏では次第に細分化されるリズムをP,Sが弾き合って緊張度と燃焼度を高め,最高潮に達するとSの左手によるトレモロ上に主題が再現された後,変ホ長調に転じて圧倒的な迫力に満ちて華麗に終わる。[12′50Prime;](S:4/P:4)

主題と変奏曲 Op.17
Thema mit Variationen[1878刊]
連弾(オリジナル)=Breitkopf & Härtel
★変イ長調 Andante un poco tranquillo:派手さはないが底光りするようなロマン性に満ちた真摯な作品。主題は前・後半とも8小節で,3度や6度重音による,ゆったりと呼吸するかのような動きの穏やかなもので,途中の変ハ長調への転調が新鮮で印象深い。Pが主題を担当して始まり,第1変奏ではSが主題を担当。以降の変奏では次第に動的なエネルギーを獲得し,カノン風な処理,両者のソロ,手の交差などの各種の技法を織り込み,テンポや一部は調性を変えつつ変奏される。旋律も伴奏も両者が2オクターヴ離れたユニゾンで弾く精力的で輝かしい第8変奏はユニーク。Pによる3度重音の揺れるような動きのLento の第11変奏の後,両者が交互にしみじみと主題を回想するコーダを経て静かに終わる。[10′30Prime;](S:4/P:4)

スケルツォ Op.33
Scherzo[1900刊]
2台ピアノ(オリジナル)=Breitkopf &Härtel(I・II分冊)
★ロ短調 Vivace:スタッカートが付された厚い和音,2台のピアノ間で反進行するアルペッジョが多用された活発で精力的な主部と,滑らかな動きの息の長いフレーズを持つ平和な中間部を持つ。I,IIのフレーズの交替の機会が多く,リズム上の変化が少ないため,特に学習用に最適な作品。コーダでロ長調に転じて力強く輝かしく終わる。[6′50Prime;](I:4/II:4)