|
||||||||
|
全6曲のうち,3,4,5番がヴィクター・バビン*2),残りは順にフェルディナント・ティオリエ,イシドール・フィリップ,ヘルマン・ケラーによる編曲で,最後にアンコールのようにメアリー・ハウによる(これだけは結構有名な編曲である)「羊は安らかに草を食み」が入っている。バビンは6曲とも2台ピアノ用に編曲しており,国立音楽大学図書館*3)には全曲の楽譜が揃っている。 バッハ作品のデュオ用編曲は,最近はすっかり人気と関心を失い,プログラムに乗せられることもめったにないが,20世紀の前半までは盛んに演奏されて,聴衆を大いに楽しませていた。その様子はナクソス・ヒストリカル・シリーズのCD,「J.S.バッハ作品のピアノ編曲集 第2集 Naxos 8.111119」*4)からも伺うことができ,この盤にはバビン(とヴロンスキー)自身の演奏による「第5番」が収録されている。 「6つのトリオ・ソナタ」は,なによりも作品が素晴らしい上に,これらの編曲はいずれも効果的で,2人のピアニストが楽しく弾けるように工夫されている。オリジナル,編曲を問わず,バッハを台むバロック時代の2台ピアノ作品のレパートリーは決して多くはなく,しかも演奏時間が10分程度という手頃な作品の数は更に限られている。そうした2台ピアノ作品のレパートリーを補う意味からも,このフーガ・リベラ盤は貴重である。 ベルギー出身のクロディーヌ・オルロフとドイツ生れのブルカルト・シュピンラーによる演奏は,全くうるさくなく,響きが輝かしく透明でバランスも良く,繊細でしかも柔軟な解釈で弾いていて,観賞用としても十分に価値のあるものだ。時には楽譜通りではなく,即興的な装飾音を加えたりするのも楽しい。解説書の内容も優れており,特に編曲者ついて詳しく触れていて,私はこの盤でティオリエの名を初めて知ったし,ケラーの「第1番」の楽譜は持っていたものの,フィリップやケラーがこれらの編曲を残していたことも知らなかった。
ブラームスの「ピアノ協奏曲」の方は既に複数のCDがあるが,やはりタールとグロートホイゼンによる演奏は聴き応えがある。このロマン派屈指の大協奏曲と対峙して,少しも気負ったり力んだりする様子もなく,それでいて極めて明晰に,そして鮮やかにこの難曲を弾き切っている。第2楽章の底光りのするような深々とした抒情も印象的だ。 そしてシューベルト!楽譜として実質わずか18ページしかないこの小品のそれぞれが,これほどまでに多彩で雄弁であったとは。大作で難曲の「ピアノ協奏曲」の方は気軽に挑戦できなくても,シューベルトの演奏の魅力と難しさのエッセンスのような「20のレントラー」から学べるものや,そこから得られる楽しみや感動もまた多い。新たなレパートリーを開拓するための資料としてのみならず,観賞用としても,もちろん第一級のCDである。
|
||||||||
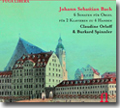 最近聴いたデュオのCDのなかで強く印象に残ったものが2枚ある。ひとつは
最近聴いたデュオのCDのなかで強く印象に残ったものが2枚ある。ひとつは この盤に収められた
この盤に収められた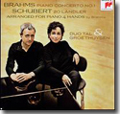 もう1枚は
もう1枚は