|
||||||||
|
前回のパラトア兄弟*1)は,バビンによる編曲が気に入っているようで,「平均率のオペラ」(The Well-Tempered Opera Koch Schwann 3-6720-2)と題されたCDでも,前述の「ばらの騎士よるワルツ」のほか,リムスキー=コルサコフのオペラ「雪娘」中の「道化師の踊り」,チ 2種類の「ばらの騎士」を比べると,ルール・ピアノ・フェスティバルのライヴのほうが,いかにもライヴらしい,興が乗った雰囲気でいっそう自由に弾いている。
バビンはモスクワで生れ,ヴロンスキーは現ウクライナ出身だが,ともにベルリンに渡り,シュナーベルに師事している。二人は1933年に出会い,その後はアメリカに渡って演奏活動のみならず教育面でも活躍するが,バビンはベルリンでシュレーカーに作曲も師事し,ヴロンスキーはパリでコルトーにも師事している。 文化会館のLPではバビンの編曲によるチャイコフスキーの「4つのワルツ」(「弦楽セレナード」「オネーギン」「白鳥の湖」そして「花のワルツ」),「道化師の踊り」「ばらの騎士」が聴けるが,このLPの表記では「道化師の踊り」のタイトルが「かるわざ師の踊り」になっている。 バビンによるこの編曲は,軽快で急速な連打音や両手の交差が頻出し,腕自慢のデュオがアンコールにでも弾いたら,大いに聴衆の耳と目を楽しませて,拍手喝采を浴びることは間違いないし,少なくともこの編曲の視覚的な印象は「かるわざ師の踊り」のほうがふさわしいと思う。 デュオの演奏家としての長い実体験に裏打ちされているだけでなく,シュレーカーに作曲を師事したバビンの編曲は極めて優れたもので,今日,ほとんど演奏されないのは実に残念だ。 幸い「4つのワルツ」(Boosey & Hawkes社刊)は国立音大の図書館*4)に所蔵されている。これらは,いずれも音そのものは原曲に完全には忠実でないものの,巧妙な装飾によって演奏効果も高く,こうした楽しいレパートリーは今でも十分に存在価値があるはずだ。 そうそう,先日ブージー&ホークス社のサイトを見ていたら,長年に渡って品切れ状態だったこの楽譜が売られているのを見つけた。12月末現在で1曲が3,000円ほどである。*5)国立音大まで足を運び難い場合は,こちらで買った方が簡単であろう。なお,例のLPの「ばらの騎士」は,なぜかオットー・ジンガー編と書いてあるが,やはりバビン編である。 バビンの編曲はこればかりでなく,バッハによるオルガン作品,「6つのトリオ・ソナタ BWV.525〜530」も2台のピアノのために編曲しており,こちらも全曲の楽譜が国立音大に所蔵されている。バロックのピアノ・デュオ作品は数少なく,それを補う意味からも貴重なレパートリーである。これら6曲の「トリオ・ソナタ」は各曲とも3つの楽章を持ち,1曲の演奏時間はほぼ10分程度なので,デュオ・リサイタルの最初に置くのも効果的である。
この歴史的CDは,バッハ作品のソロとデュオ用のピアノ編曲集だが,バートレット&ロバートソンによるメトニコフ編の「フーガ ト短調」や,ルボシュッツ&ネメノフによるメイヤー編の「シチリアーナ」といった過去の偉大なデュオによる貴重な演奏が聴ける。 ヴロンスキー&バビンによる演奏はほかにもCD化されており,ラフマニノフなどを収録した実に興味深い「デュオ ヴロンスキー&バビン」(Duo Vronsky & Babin Dante HPC026)もあり,これについては別の機会に触れたい。
|
||||||||
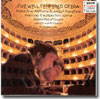 ャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」の「ワルツ」を弾いている。
ャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」の「ワルツ」を弾いている。 上野の東京文化会館の音楽資料室*2)には,そのバビンとヴロンスキー(Vitya Vronsky 1909-92)*3)の二人が弾いた「楽しいピアノのデュエット(原題 :176 Keys Music for two Pianos)」という,いささか古いが,実に楽しい内容のLPがある。
上野の東京文化会館の音楽資料室*2)には,そのバビンとヴロンスキー(Vitya Vronsky 1909-92)*3)の二人が弾いた「楽しいピアノのデュエット(原題 :176 Keys Music for two Pianos)」という,いささか古いが,実に楽しい内容のLPがある。 そして「第5番 ハ長調」は,「J. S. バッハ作品のピアノ編曲集 第2集」(J. S. Bach: Piano Transcriptions Volume2 NAXOS Histrical 8.111119)*6)のCDでヴロンスキー&バビンによる演奏で聴ける。
そして「第5番 ハ長調」は,「J. S. バッハ作品のピアノ編曲集 第2集」(J. S. Bach: Piano Transcriptions Volume2 NAXOS Histrical 8.111119)*6)のCDでヴロンスキー&バビンによる演奏で聴ける。