|
||||||||
|
ショパン生誕200年のメモリアル・イヤーの今年,さまざまなリサイタルやコンサートが催されたが,唯一の連弾作品である「四手のための変奏曲」は,いつもの年よりも演奏される機会が増えたのであろうか?
そして肝心の補完だが,P の5小節目から登場するモティーフを冒頭の S で使っているため,序奏部分での統一感が強まっている。そして半音階的な和声進行が多く,P とS との掛合いの機会を設けているので連弾作品として凝った印象を受ける。コーダ部分の補完は S が残されているため,和声的に変化を加える余地はほとんどなく,両版を比べても一方が他方の「変奏」のように感じられる。 ともあれ,モーツァルトの未完の「ラルゲットとアレグロ」もそうだが,補完が多種多様になることは,それだけ選択の機会も増えて誠に喜ばしい。なお全音版の解説で知ったのだが,イタリアのベッティネッリ補完の楽譜も出版されているとのこと。
こうした編曲を楽譜も見ずに,「生徒の勉強用に2台に分けて易しくした」と思い込んでいる人もいるようだが,恐らくサン=サーンスは他のヴィルトゥオーソ・ピアニストと一緒にこの傑作を弾いて,相手との音楽的な刺激のやり取りを楽しみたかったのであろう。実際,サン=サーンスはリストの「ソナタ ロ短調」も2台用に編曲しているが,こちらはルイ・ディエメとともに弾いた記録が残されている。 例えば,もしラフマニノフとホロヴィッツが私的な楽しみのためにこれら2曲の「ソナタ」を弾き,それを扉の陰から覗くことができたら,と想像するのは楽しい。この2人の巨人なら,いったいどんな風にお互いを挑発し合い,そして共感し合っただろうか? エグリとペルティスによるCDには,ほかに「タランテラ Op.43」の連弾版が入っている。解説によるとこの編曲はショパン存命時代に出版され,ショパン自身による編曲とする証拠はないが,極めて優れた編曲とのこと。聴いてみると,この2人による演奏の見事さも加わって,ヴィルトゥオーソ的で壮快な作品が,またひとつ連弾のレパートリーに加わった。多分この楽譜はショット社から出ている「連弾によるショパン Chopin vierhändig 」*6) に所収されているものと思う。 今年も残り少なくなったこの時期になって,やっとショパンの連弾曲について書いたが,ショパンの連弾作品を楽しむのは,メモリアル・イヤーの喧騒が収まってからでも決して遅くはない。
|
||||||||
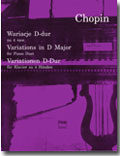 PWM(ポーランド音楽出版社)*1)
PWM(ポーランド音楽出版社)*1)
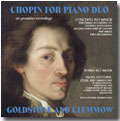 また
また