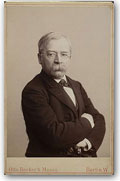|
|||||||||
|
シブリー*1) でも IMSLP*2) でも,ユオンの「舞踏のリズム集」の楽譜の表紙や裏表紙も見られる。こうしたネット上の楽譜は,楽譜の本体だけのケースも多いが,時には表紙や扉,そして裏表紙からも貴重な情報が得られることがある。
ユオンの「舞踏のリズム集」を知ると,その師のバルギールがどんな連弾曲を書いていたのか,といった興味から,連弾曲の「ジーグ」がどんな作品なのかを知りたくなるのは当然たが,残念なことに今のところシブリーにも IMSLP にも,この作品は見当たらない。しかし,どちらにも連弾作品の「ソナタ Op.23」*4) があるのは誠にありがたい。 クララ・シューマンの異父弟のバルギール(1828〜97)は両親やデーンのほか,ライプツィヒ音楽院でモシェレスやゲーゼといった人たちから学んでいる。 1864年に出版されたこの「ソナタ」に関しては,なぜかマグローの大著*5) にも出ていないので,情報はほとんどない。同時代のドイツ・ロマン派系のピアノ・デュオのための「ソナタ」としては,まずブラームス(2台,1864年)やフォルクマン*6) (連弾,1868年,ただし「ソナチネ」)の作品が上げられる。 多少とも知られているフォルクマンや,ずっと有名なブラームスの作品に比べると,パルギールの「ソナタ」は,まったくと言って良いほど知られていない。しかし実際に弾いてみると,なかなかの傑作で,特に第1楽章の新鮮でさわやかな抒情は,20年ほど後の,チェコのフィビヒ*7) の連弾のための「ソナタ」に匹敵しよう。 バルギールの「ソナタ」は全3楽章。第1楽章はト長調,3/4拍子,Moderato。その冒頭,P の右手による伸びやかに上昇する第1主題と,S の右手によって下降する相反する動き(再現部では P と S の役割が交替)が,いかにも連弾曲らしいし,36小節以降の第2主題の陶酔的なロマンも素晴らしい。それだけでなく,ちょっとしたモチーフの P と S との掛合いも楽しめるため,試しに最初の1ページだけを弾いてみても,連弾演奏の醍醐味が満喫できるほどだ。技術的にも決して難しくなく,どちらか一方がメロディ,他方が伴奏と片寄っていないので,中級以上なら十分に楽しんで弾ける上,レッスンに用いれば楽しいだけでなく,とても良い勉強になる。しかしこの作品,4手が接近しがちなのと,S の低音部に密集した音が多いので, 全体の響きが重苦しくならないように注意する必要がある。 第2楽章は変ホ長調,4/4拍子,Lento 。 S のソロで弦楽四重奏風に静かに始まるが,途中で気分も音量も大きく盛り上がる。第3楽章はト長調,6/8拍子。 Allegro molto の16小節の序奏に続いてAllegro grazioso の主部に入る。この楽章は楽想も響きもかわいらしい。 演奏時間は反復を含めて各楽章が7分30秒,7分,5分30秒ほど。第1,2楽章の演奏時間が長いが,指示されたテンポが遅めのため,速いテンポを採ればかなり短縮できる。
|
|||||||||