|
|||||
|
新たな年の初めには,聴いた後に晴れやかでしかも豊かな満足感が残るCDがふさわしいと思う。
この編曲に関しては拙著,「ピアノ・デュオ作品事典」にも記載があるとおり,アリアの大部分の装飾音が省略されており,原曲が良く知られているだけに,それが違和感の最大の原因であろう。 ところがタール&グロートホイゼン(以下T&G)盤ではそれらの装飾音を再び付け加えて弾いているのだ。やはりこのアリアには繊細でしかも豊かな装飾音が良く似合う。 この巨大な作品は,ト短調の瞑想的で悲痛な第15変奏(ラインベルガーもレーガーも「アダージョ」のテンポを指示している)で前半を終える。演奏会ではここで休憩を挟み,後半として次の「序曲」から始めるのが一般的だ。 T&G盤ではCDにもかかわらず,次の変奏へと続く「間」が考え抜かれており,アタッカとしてすぐ次の変奏に続き,大きなクライマックスを形成するかと思えば,この休憩の箇所には比較的長い「間」が置かれている。
全曲中,最難曲の第14変奏の華麗なヴィルトゥオジティはまったく目覚ましく,同時に9小節目のラインベルガーによる「leggiero(軽く)」の指示を実に見事に実現している。 あえてラインベルガー版のアーティキュレーションや強弱の指示を無視している箇所も多いが,ここには生き生きとして血の通ったバッハ像があり,演奏時間が一時間を越えるこの大曲を一気に聴かせてしまう。それはまるでバッハ,ラインベルガー,レーガーといった最高の食材が,T&Gという最高の板前によって整えられた,豪華なお節料理のようだ。実際,変奏が進むに連れて千変万化する曲想が楽しめるさまは,重箱の蓋を開けると色とりどりのさまざまな豪華な料理が姿を表すさまにも似ている。 第30変奏の「クォドリベット」の終結部で,レーガーによる「non dim.」の指示を無視して静かに収まり,滑り込むように冒頭のアリアに回帰するさまには,宗教的な崇高ささえ漂い,これも新年向きである。 そして国内盤はズザーネ・ポップ女史による詳細で優れた解説が日本語で読めるのも嬉しい。レーガーの権威でもある女史による解説は,レーガー自身による「ゴルトベルク変奏曲」の2P版の演奏に関わる史実から,「ブランデンブルク協奏曲」のレーガーによる連弾用編曲のCDの女史による解説でも同様だが,当時のレーガーの心理面にまで触れられており,資料としても極めて貴重な解説である。 ******************************** ところで,年末に得た話題,それも複雑な思いに駆られる話題がある。 「71.連弾革命!」*2)でご紹介した「連弾レボリューション」のCDが,「レコード芸術」の本年1月号で,2人の評者から極めて高い評価を得た。私自身もこのCDにかかわっただけにまことに喜ばしいが,これを知った直後に,茨城県日立市の「VIVA!!ピアノデュオコンサート」*3)が昨年で最後になったと聞いた。 ピアノ・デュオ界にとって極めて有意義な活動であり,「連弾レボリューション」の演奏者の宮原姉妹を知ったのもこのコンサートだっただけに,本当に残念でならない。
|
|||||
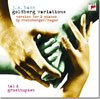
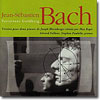 私の手元にはほかに2種の同曲のCD(レヒラー&アイゼンローア RBM CD 463087)とファルール&パウレッロ ASSAI 222062)*1)があり,それらも決してまずい演奏ではなく,いやむしろT&G盤よりもテキストに忠実で,誇張された表情もなく誠実な演奏を繰り広げ,反復の際に変化を加える工夫もなされてはいるのだが,長年の連弾演奏で鍛えた耳の良さと広大なダイナミックレンジのためであろうか,T&G盤のテクスチュアの透明感と演出の面白さは群を抜いている。
私の手元にはほかに2種の同曲のCD(レヒラー&アイゼンローア RBM CD 463087)とファルール&パウレッロ ASSAI 222062)*1)があり,それらも決してまずい演奏ではなく,いやむしろT&G盤よりもテキストに忠実で,誇張された表情もなく誠実な演奏を繰り広げ,反復の際に変化を加える工夫もなされてはいるのだが,長年の連弾演奏で鍛えた耳の良さと広大なダイナミックレンジのためであろうか,T&G盤のテクスチュアの透明感と演出の面白さは群を抜いている。