|
|||||||||
|
収録曲目を調べずに買ったので,届いた時,楽譜が手元にある2台のピアノのための「組曲 Op.111」や「アラベスク Op.119」が入っていなかったので,ちょっとガッカリしたが,実際に聴いてみると演奏も良くて収穫は大きかった。 2台ピアノ作品の収録曲は,「ソナタ 第2番 Op.107(1941)」「2つの小品Op.106(1939)」「ワルツ ハ長調 Op.108(1941)」「主題と変奏曲 Op.139(1951)」である。
ラフマニノフ(1873〜1943)の「交響的舞曲」は,今や2台のピアノのためのレパートリーとしてもお馴染みだが,1940年の作曲と聞かされても,特に「時代遅れ」とは感じないのではなかろうか。 そのボウエン*2)は「イギリスのラフマニノフ」とも呼ばれたそうだが,こうしたあだ名は結構多い。「イギリスのドビュッシー」はシリル・スコット,「北のヨハン・シュトラウス」はハンス・クリスティアン・ロンビ,「アメリカのベートーヴェン」はアンソニー・フィリップ・ハインリヒといった具合である。当然ながら,いずれも「本人」よりは異国の「他人」の方が無名という点で共通している。
こうしたあだ名は誰がどんな目的(もしかすると名前や楽譜を売るための知名度アップのため?)で言い始めるのか知らないが,悪意や椰楡の気持ちはないにしても,言われた当人はどう感じるのであろうか? ボウエン自身,「イギリスのラフマニノフ」とも呼ばれてどう感じていたのであろうか。ラフマニノフはボウエンよりも9歳年上で,ボウエンより少し短い生涯だった事を割り引いても,作品数ではボウエンの方が多く,細かく数えた事はないが作品番号ではボウエンの方が3倍ほど多い。 そして劇音楽(無し?)や声楽曲は少ないが,ボウエンはオルガンもホルンもヴィオラも上手く,オーケストラの楽器はすべて演奏できたというだけあって,器楽作品のジャンルは広い。 二人とも20世紀の半ばまで後期ロマン派風の作品を書き続けた点は共通しているが,ラフマニノフの作品にはロシアの土の臭いが感じられる一方で,ボウエンの作品にはそれが感じられない。 ボウエンが影響を受けた作曲家の中に,リヒャルト・シュトラウスの名があるが,それを作品を聴いて実感したのは,2年前の4月の「日英ピアノデュオの架け橋」*5)におけるワークショップでの,笠原純子&友田恭子による連弾のための「組曲 第2番 Op.71」の演奏であった。*6)
ワークショップの限られた参加者だけが,この素晴らしい演奏を聴けたのだが,3月30日には青森で,来月10日は東京でのリサイタルで再びこの作品が取り上げられる。*7) そこではより多くの聴衆がボウエンの連弾作品の魅力に接する事ができるに違いなく,来年が没後50年というメモリアル・イヤーに向けて,再評価への大きなステップとなろう。
|
|||||||||
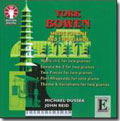 かなり前から気になっていたCDを,先日入手した。それは"YORK BOEN Music for One and Two Pianos CDLX7218"*1)である。
かなり前から気になっていたCDを,先日入手した。それは"YORK BOEN Music for One and Two Pianos CDLX7218"*1)である。 いずれも後期ロマン派風の濃厚な叙情に満ちた作品で,こうした作品が20世紀半ばに作曲されたとは,少なからず意外でもある。21世紀の今では,20世紀の音楽を含めてすべては過去のものになってしまっているし,現在は多様化の範囲が更に拡大し続けているので,こうした作品に対するある種の違和感はずっと少なくなっていると思う。
いずれも後期ロマン派風の濃厚な叙情に満ちた作品で,こうした作品が20世紀半ばに作曲されたとは,少なからず意外でもある。21世紀の今では,20世紀の音楽を含めてすべては過去のものになってしまっているし,現在は多様化の範囲が更に拡大し続けているので,こうした作品に対するある種の違和感はずっと少なくなっていると思う。 話は脱線するが,デンマーク人のロンビ(1810〜74)*3)は,今年が生誕200年でもあり,ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートでその作品が演奏された。そしてインターネットを通してデンマーク王立図書館(The Danish Royal Library)*4)のアーカイブで,その作品の楽譜(連弾版もある)に接する事ができる。
話は脱線するが,デンマーク人のロンビ(1810〜74)*3)は,今年が生誕200年でもあり,ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートでその作品が演奏された。そしてインターネットを通してデンマーク王立図書館(The Danish Royal Library)*4)のアーカイブで,その作品の楽譜(連弾版もある)に接する事ができる。