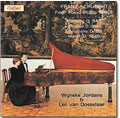|
|||||
|
前回の続きとなる,ドビュッシーの「易しい」方の新しいデュオ・レパートリーのご紹介の前に,今回はこちらを先に。
それ以前,1980年代の後半にサティの音楽がブームとなった時期にサティのデュオ作品のCDも数多く発売され,それらの中にはボテボテとした響きで締まりのないリズムの演奏もあったが,このデュオによる実に颯爽とした演奏が際立っていたのが強く印象に残っていた。
ラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」「子供と魔法から『ワルツ』と『5時(フォックス・トロット)』」,イベールの「小さな白いロバ」,そしてサン・サーンスの「動物の謝肉祭」の連弾版が収録されている(ほかに作曲者自身の編曲によるミヨーの「屋根の上の牡牛」)。
今度はべートーヴェンでその内容は,オリジナル連弾曲全曲,つまり「ヴァルトシュタイン伯爵の主題による8つの変奏曲」「3つの行進曲」「ソナタニ長調」「『君を思う』の主題による6つの変奏曲」,そして更に興味深いのが「交響曲 第4番」「エグモント序曲」の連弾版である。 最後の2曲の編曲者はウィリアム・ワッツ (William Watts)で,解説によると,ワッツは1813年にロンドンで創立されたロイヤル・フィルハーモニック協会でヴィオラを弾いていたとのこと。そう言えば,このワッツの編曲による「七重奏曲」の連弾版が私の楽譜棚にもあるのを思い出した。この中古の楽譜を買った時から,CDの解説を読むまで,ワッツの経歴については何も知らなかったのだが。 さて,「交響曲」も「序曲」も,いかにも連弾らしい表情豊かで緻密な演奏で大いに楽しめたが,デセラーとヨルダンスはこのCDの演奏に,現代のピアノではなく,フォルテ・ピアノを使っている。
豊かに響くが決して重々しくない中音域以下,華やかだが金属的ではない高音域の音を聴くともし当時,普及していた楽器が現代のピアノと同じであったら,連弾の大流行はなかったのではとさえ思ってしまう。 実は私はフォルテ・ピアノには触れた事もないので,想像で言っているだけなのだが,その当時,連弾を弾いた多くのアマチュア・ピアニストたちが,今の楽器で連弾を弾く時と同じようにバランスに細心の注意を払い,神経をすり減らして弾いていたとは,どうしても思えないのだ。 それでは連弾を気軽に楽しむというわけにはいかないし,といってバランスの悪い重苦しい響きの演奏では,弾いても楽しくはなかったのでは,と思うのだ。 それはそうとフォルテ・ピアノの音はハープの音にとても似て聴こえる瞬間がある。例えばドゥシェック (J. L. Dussek 1761〜1812)の2台のピアノのための「ソナタ ヘ長調」のように,「ハープとピアノのための,あるいは2台のピアノのための」と指定された作品もあり,現代のコンサート・グランドの音だけしか考えないと「ハープとピアノでは音質が相当違い,響きはバラバラなのでは」と思ってしまうが,当時のフォルテ・ピアノとハープによる演奏では,それほど違和感はなかったのであろう。
|
|||||

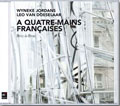 そのほかにも注目に値する,優れた内容のCDが多く,フランスの連弾曲を集めたCD (A quatre mains Françaises CHALLENGE CLASSICS CC 72104)*2)もその一例で,このCDの特徴は全曲が「編曲もの」であることだ。
そのほかにも注目に値する,優れた内容のCDが多く,フランスの連弾曲を集めたCD (A quatre mains Françaises CHALLENGE CLASSICS CC 72104)*2)もその一例で,このCDの特徴は全曲が「編曲もの」であることだ。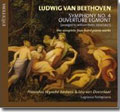 この2人による新しいCD (Beethoven: Symphony No.4 ETCETRA KTC1396)*3)が,最近発売された。
この2人による新しいCD (Beethoven: Symphony No.4 ETCETRA KTC1396)*3)が,最近発売された。