|
|||||
|
今年,2009年はヨーゼフ・ハイドン(1732〜1809)の没後200年のメモリアル・イヤーでもあったが,今年も残り少なくなってきた。 そのハイドンには2曲の連弾作品があり,その1曲が「ディヴェルティメント」や,版によっては「ソナタ」のサブタイトルを持つ「先生と生徒 Il maestro e lo scolare」である。 この作品は2楽章構成で,第2楽章は短い「メヌエット」だが,第1楽章は変奏曲のスタイルをとり,セコンド(先生)の弾くフレーズを,直後にプリモ(生徒)が反復するという,そのタイトル通りの特徴的な書法で構成されている。
IMSLPにも「先生と生徒」と題されたファイルがある*2)が,ここには第1楽章しかなく,これで全曲と信じ込んでこの作品を聴くと,第2楽章が始まると「アレッ?」と思うことになろう。 インターネットは確かに手軽で便利だが怖い! それはさておき,「先生と生徒」の自筆譜は失われているため,H版,W版ともに初期の出版譜や手稿譜に基づいており,資料の取捨選択によって両版にはかなりの違いがある。 細かなアーティキュレーションの差は当然としても,最も大きな違いは,第1楽章の変奏がH版は8つに対し,W版は第7変奏までである。といってもH版がW版にはない新たな変奏を備えているわけではなく,第8変奏は主題に戻って反復するに過ぎない。 そしてS・Pともに自分の両手を交差させて弾くために,「跳躍と両手を交差の練習曲」としても格好な活動的な変奏は,W版では第5変奏だが,H版では第6変奏となり,両版では第5,6変奏の順番が入れ替わっている。 この作品の音源も数種類のCDがあるが,新しいもので入手しやすいのはナクソス盤の「ハイドン・ピアノ変奏曲集 HAYDN: Piano Variations NAXOS 8.553972」*3)であろう。 ナクソス盤の変奏の順はW版に沿っているので,そうとは知らずにH版を見ながらこのCDを聴くと,ここで混乱することになる。それ以前に,W版は主題の13小節目のSの左手のバスのC音に嬰記号が付く(14小節目のPも同様)が,H版には嬰記号がない。ハーモニーが全く変わってしまうだけにこの違いは大きく,H版とナクソス盤の組合わせで聴く人は,まずここで驚くことになる。 IMSLPのファイルは基本的にはW版に近い。この変奏曲の主題,アウフタクトの最初の音を取り去ると,調性は違うもののヘンデル(1685〜1759)の「調子のよい鍛冶屋」(「チェンバロ組曲 第5番」ホ長調の第4楽章。1720年刊)の主題と,音型がまったく同じである。 H版の「序文」によると「先生と生徒」は1766/7年の作品であり,連弾作品として極めて初期の作品に属する。その時代,「調子のよい鍛冶屋」(このタイトルはヘンデルの命名ではないが)がどれほど人気があったのかは分からないが,明らかにレッスン用に意図されたこの変奏曲の主題に,「調子のよい鍛冶屋」のメロディを使ったのは,パパ・ハイドンのユーモアなのだろうか? 2009年も残りあと少し。
|
|||||
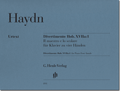
![[ウイーン原典版47(音楽之友社刊)]「ハイドン ピアノ曲集」表紙](image/70-2.jpg) 手元に全音の連弾ピースの楽譜もあったはずなのだが,いくら探しても見つからず,ウィーン原典版(音友)の「ハイドン ピアノ曲集」*1)所収(文中,以下W版)のものと見比べる事しかできなくなってしまった。その全音ピースも,同社のサイトによるとカタログから姿を消している。
手元に全音の連弾ピースの楽譜もあったはずなのだが,いくら探しても見つからず,ウィーン原典版(音友)の「ハイドン ピアノ曲集」*1)所収(文中,以下W版)のものと見比べる事しかできなくなってしまった。その全音ピースも,同社のサイトによるとカタログから姿を消している。